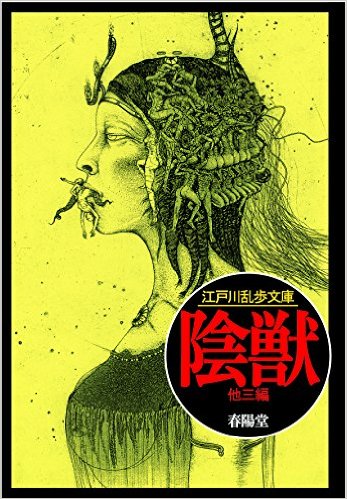第6回 「陰獣」、探偵作家たちのなかで【後編】
江戸川乱歩研究者 落合 教幸

「陰獣」は、ある作家が事件を回想するかたちで書かれている。こうした枠を乱歩はしばしば使用しているが、ここでも語り手の寒川という作家と、謎の作家である大江春泥の対比を簡潔に提示するのに有効に使われているといえるだろう。
当時の評論では、探偵小説を本格と変格とに分けるものが現れていた。そのさきがけのひとつといわれるのが、評論家の平林初之輔の文章で、乱歩のほか、小酒井不木、横溝正史、城昌幸の作品を挙げ、怪奇的なそれらを不健全派とした。それに対して、正木不如丘や甲賀三郎の作品を健全派としている。その後、小酒井不木や甲賀三郎などが、本格と変格の語を使用して、こうした区分が一般的になっていった。
本格探偵小説の書き手としては、甲賀三郎が知られていた。甲賀は乱歩と同時期に登場し、「琥珀のパイプ」などが有名である。のちに実話犯罪小説「支倉事件」や、通俗的といえる「姿なき怪盗」なども書いているものの、本格探偵小説を重視する姿勢は一貫していた。
「陰獣」の主人公の寒川は、理知的な本格探偵小説の書き手ということで、この甲賀三郎に近いところがある作家となっている。
探偵作家の寒川は、上野の博物館で仏像を見ているときに、女性と知り合いになる。寒川の作品の愛読者だという静子は、実業家の小山田六郎の妻だった。寒川と静子は文通をするようになる。
最初の出会いで寒川に強い印象を与えたのが、彼女の白い肌の美しさと、垣間見える蚯蚓腫れのような跡だった。
乱歩の作品には、初期から戦後まで、女性が重要な役割を演じるものがいくつかある。この「陰獣」もそのひとつである。これ以前に書かれた作品では、たとえば「お勢登場」のお勢が、そうした存在のひとりと言える。のちの「黒蜥蜴」や「化人幻戯」でも印象的な女性が描かれていく。いずれも悪女ということになるのだが、その立場や欲望するものが異なってもいるので、それぞれを見ていくのも興味深いだろう。
静子のもとに、旧知の平田一郎から手紙が届いたという。その手紙には、ある夜の静子の行動が詳細に書かれていた。
これまで乱歩を読んできた読者であれば、「人間椅子」をここで想起するかもしれない。「人間椅子」では、女性作家のもとに奇妙な書簡が届く。そこには、椅子の中にひそむ男が、あたかもその女性の生活に密着しているかのような記述があるのだった。
静子のもとに手紙を送ってきた平田は、以前に静子と恋仲だった。自分のもとを去った静子に対し、復讐をすると書かれていた。この平田という男は、大江春泥という作家として活動していたとも記されていた。
謎の作家大江春泥は、江戸川乱歩を連想させるようになっている。そしていくつもの場面で、大江春泥が以前に発表した作品を思わせる仕掛けが登場して、重要な意味を持つのである。つまり、乱歩の短篇を数多く読んできた読者であれば、「一枚の切符」「D坂の殺人事件」「屋根裏の散歩者」といった作品とのつながりを見つけることができるようになっているのだ。
屋根裏に潜んだ男が、生活を観察しているというのは「屋根裏の散歩者」で、落としたボタンが犯人を特定するカギになるというのも共通している。そしてもちろん静子の肌にある傷が「D坂の殺人事件」で重要な意味を持つ、性的な傾向とも通じているわけである。
このように、初期乱歩の総集編のように楽しむこともできるのである。これら二つの作品では、明智小五郎が事件を解決することを思えば、明智の不在を意識して見ても面白いかもしれない。
語り手の寒川と、謎の作家大江春泥とは、本格探偵小説と変格探偵小説の作家として対立している。乱歩が自分の中に複数の顔があることを自覚していたことを考えれば、個別の作家を当てはめるのではなくて、それぞれの人物に乱歩が投影されているという見方もできる。二人の作家だけでなく、「江戸川乱歩」や本名の「平井太郎」の中の文字が、何人かの登場人物の名前の中にも見られる。意地の悪い見方をすると、当時の乱歩はすでに髪の毛が薄くなっているので、かつらをつけて殺された小山田六郎にも乱歩を重ねることができるわけだ。
自分の作品について客観的に評価することは難しく、乱歩もそのことを何度か書いている。後には乱歩も自作のなかで高い評価をすることになる「陰獣」だが、発表当時はそれまでの作風から飛躍することはできなかったと感じていたようだ。そうしたその頃の乱歩の自己認識が、「新青年」との距離を残していくことになったのかもしれない。
この後から乱歩は、求めに応じて一般向けの娯楽的な長篇を書くようになっていく。「孤島の鬼」「蜘蛛男」「魔術師」「黄金仮面」「吸血鬼」といった長篇がこの時期に書かれた。これらの小説は読み物として多くの読者を獲得したが、一方でそれまで乱歩に期待していた探偵小説の愛好家たちにとっては歓迎されなかった。
だがしばらく後、「陰獣」は井上良夫の評価を得ることになる。探偵小説専門誌「ぷろふいる」1934(昭和9)年8月号で取り上げられ、結末の部分に不満は残るものの、傑作であると評された。乱歩にとってこの年少の友人の影響は大きく、時期的に見れば、これが『新青年』の連載長篇「悪霊」中絶で落ち込んでいた乱歩に、『中央公論』で「石榴」を書かせる動機のひとつとなった可能性もある。「石榴」のほうの評価はさまざまだったが、否定的な評価のなかでも、「陰獣」は高く評価されているのを見ることができるのは興味深い。
1935(昭和10)年に柳香書院から刊行された『石榴』には、その前年に書かれた「石榴」に加え、「陰獣」「心理試験」が収められた。つまり乱歩はこれらの作品を自身の純探偵小説の代表的なものだと考えるようになっていたということだろう。
この頃の乱歩は、自分が探偵小説の現役作家ではなくなったと感じるようになっていた。その後、評論などで探偵小説に貢献していくことになる。そうした動きにもこの「陰獣」は関わっていると考えられるのである。
この年、乱歩は探偵作家としての前半期をまとめ、後半期へと進んでいく。この連載の第1回で見たように、初期の短篇の時代と、中期の長篇の時代を経て、後期の評論と少年物の時代に移行していくことになる。
この年、乱歩は、傑作集などの編集にかかわるとともに、多くの評論を書いている。そして翌年からは初めての少年物「怪人二十面相」の連載が始まる。随筆・評論と少年物は、戦争による中断を挟んで、乱歩の晩年まで続いていくのだった。
「陰獣」は乱歩前半期の、中心となった作品といえるかもしれない。

江戸川乱歩文庫『陰獣』(春陽堂書店)より
<終>
┃この記事を書いた人
落合教幸(おちあい・たかゆき)
1973年神奈川県生まれ。日本近代文学研究者。専門は日本の探偵小説。立教大学大学院在学中の2003年より江戸川乱歩旧蔵資料の整理、研究に携わり、2017年3月まで立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの学術調査員を務める。春陽堂書店『江戸川乱歩文庫』全30巻の監修と解説を担当。共著書に『怪人 江戸川乱歩のコレクション』(新潮社 2017)、『江戸川乱歩 幻想と猟奇の世界』(春陽堂書店 2018)、『江戸川乱歩新世紀-越境する探偵小説』(ひつじ書房 2019)。
1973年神奈川県生まれ。日本近代文学研究者。専門は日本の探偵小説。立教大学大学院在学中の2003年より江戸川乱歩旧蔵資料の整理、研究に携わり、2017年3月まで立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センターの学術調査員を務める。春陽堂書店『江戸川乱歩文庫』全30巻の監修と解説を担当。共著書に『怪人 江戸川乱歩のコレクション』(新潮社 2017)、『江戸川乱歩 幻想と猟奇の世界』(春陽堂書店 2018)、『江戸川乱歩新世紀-越境する探偵小説』(ひつじ書房 2019)。