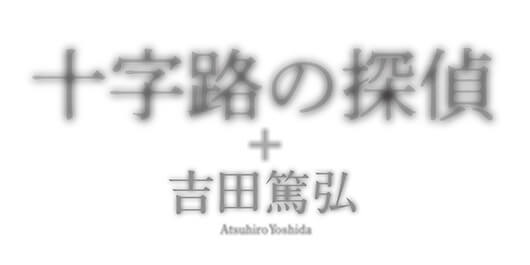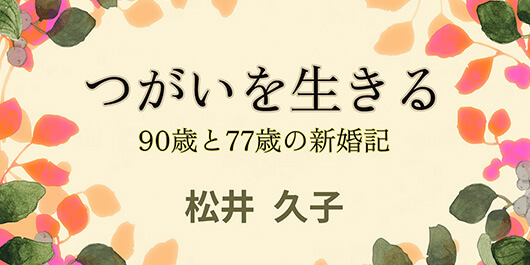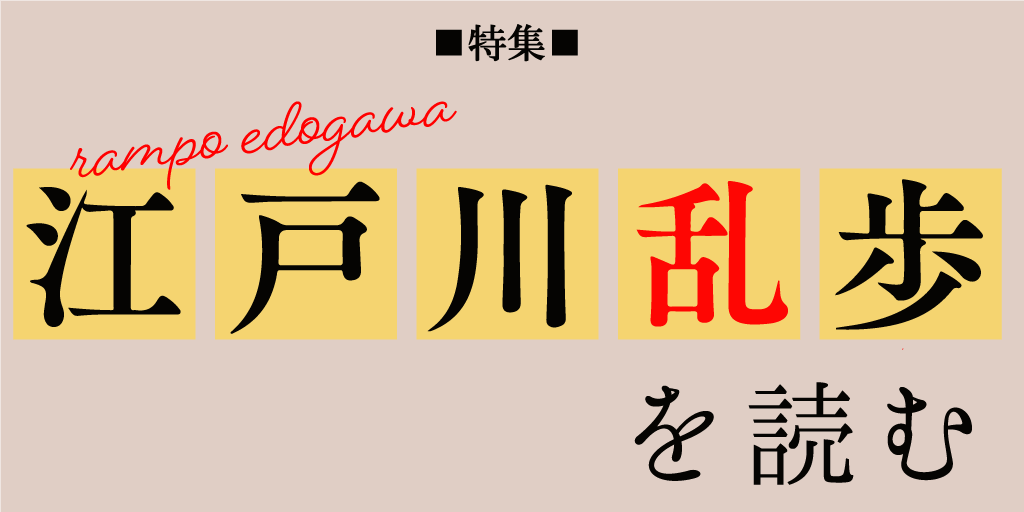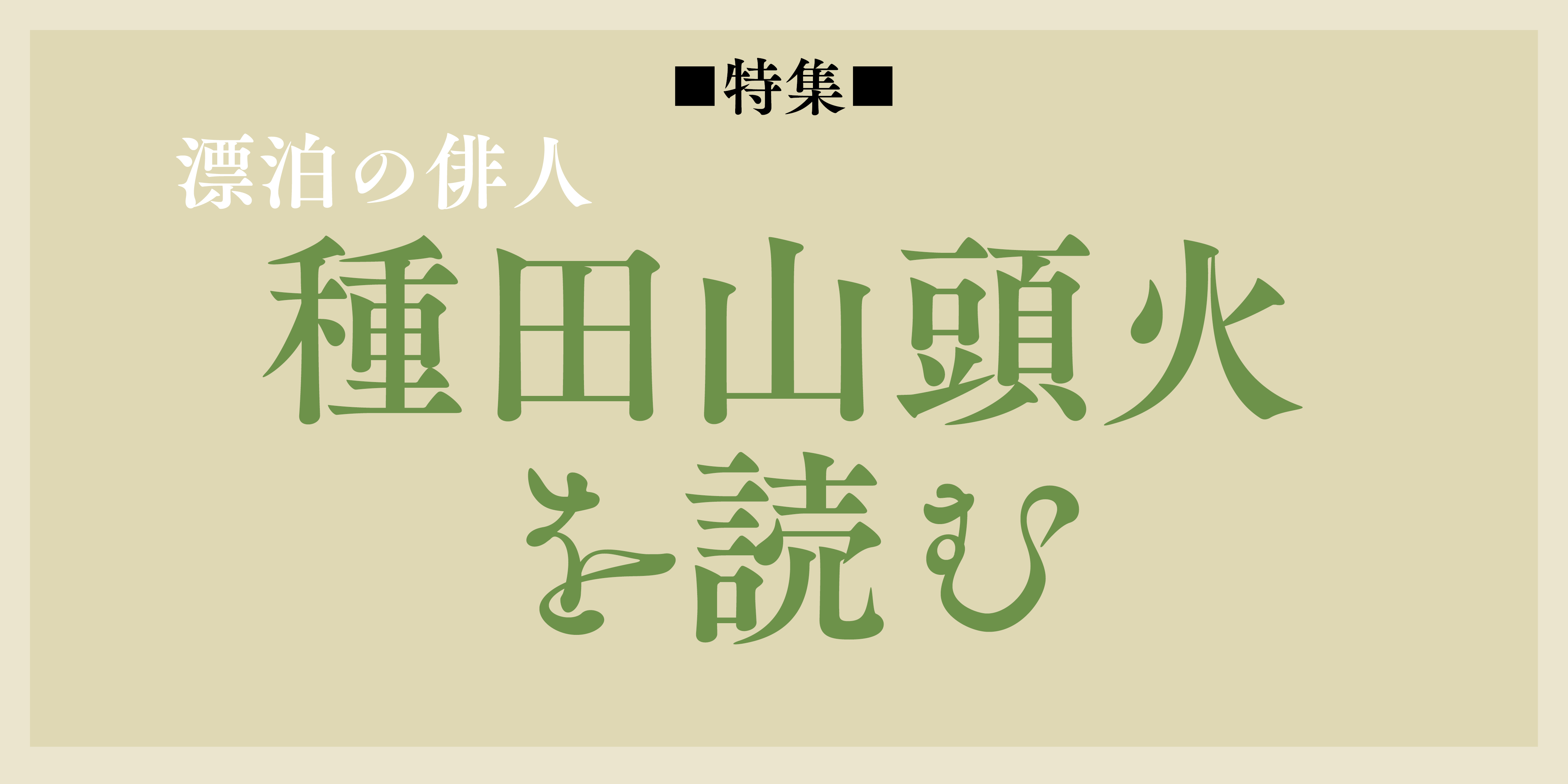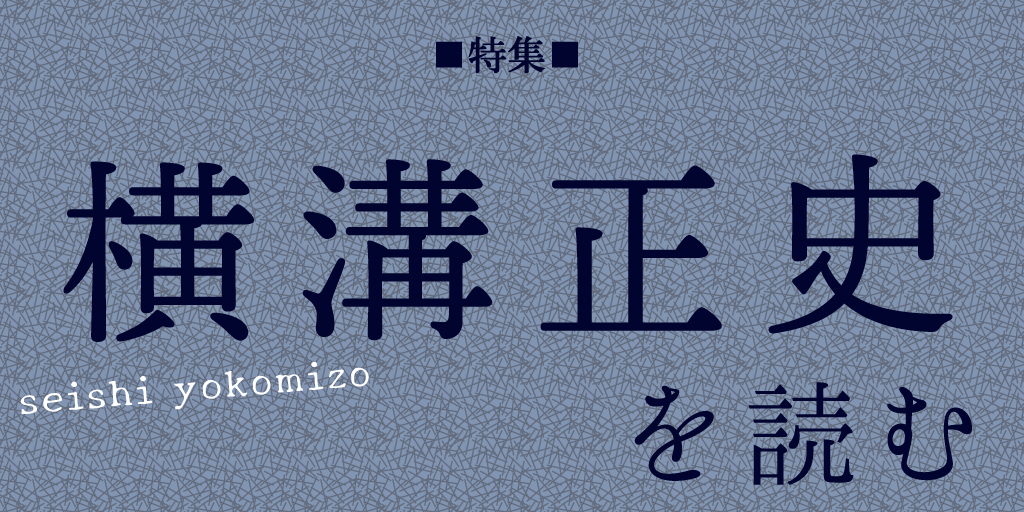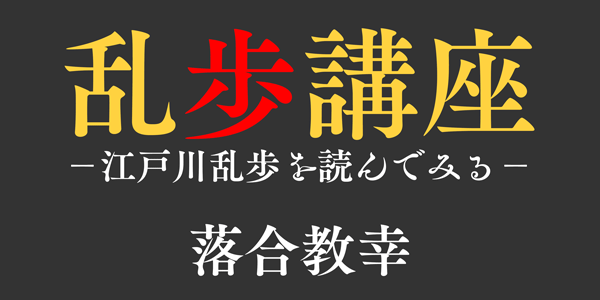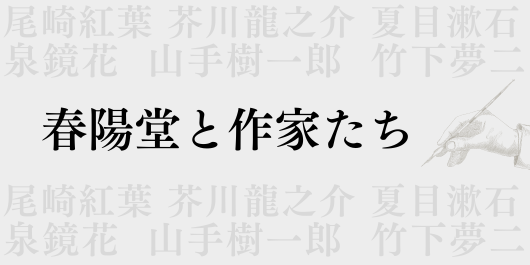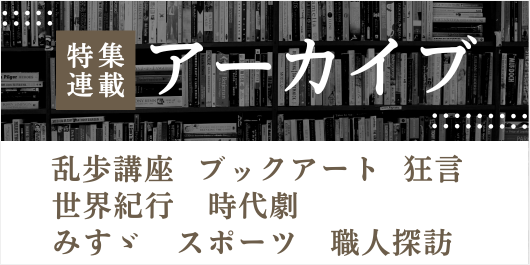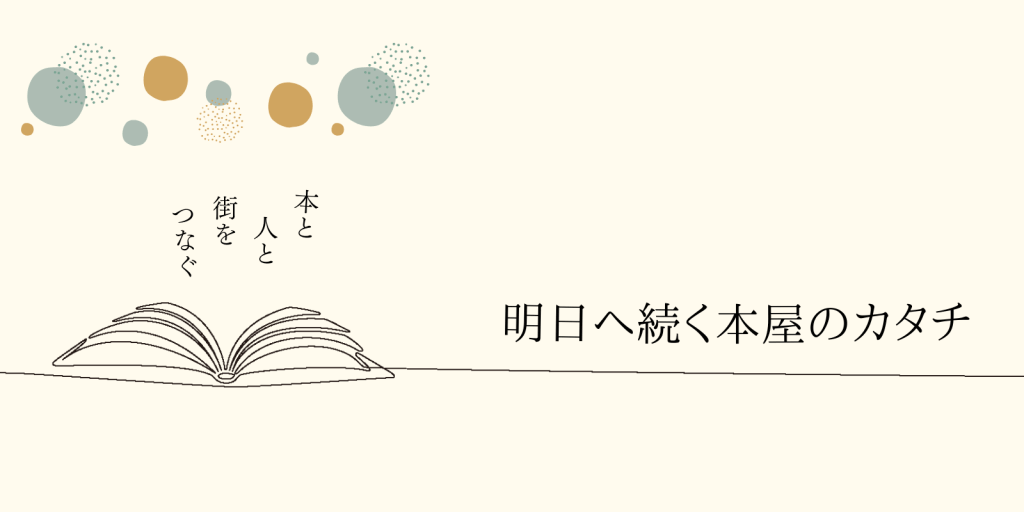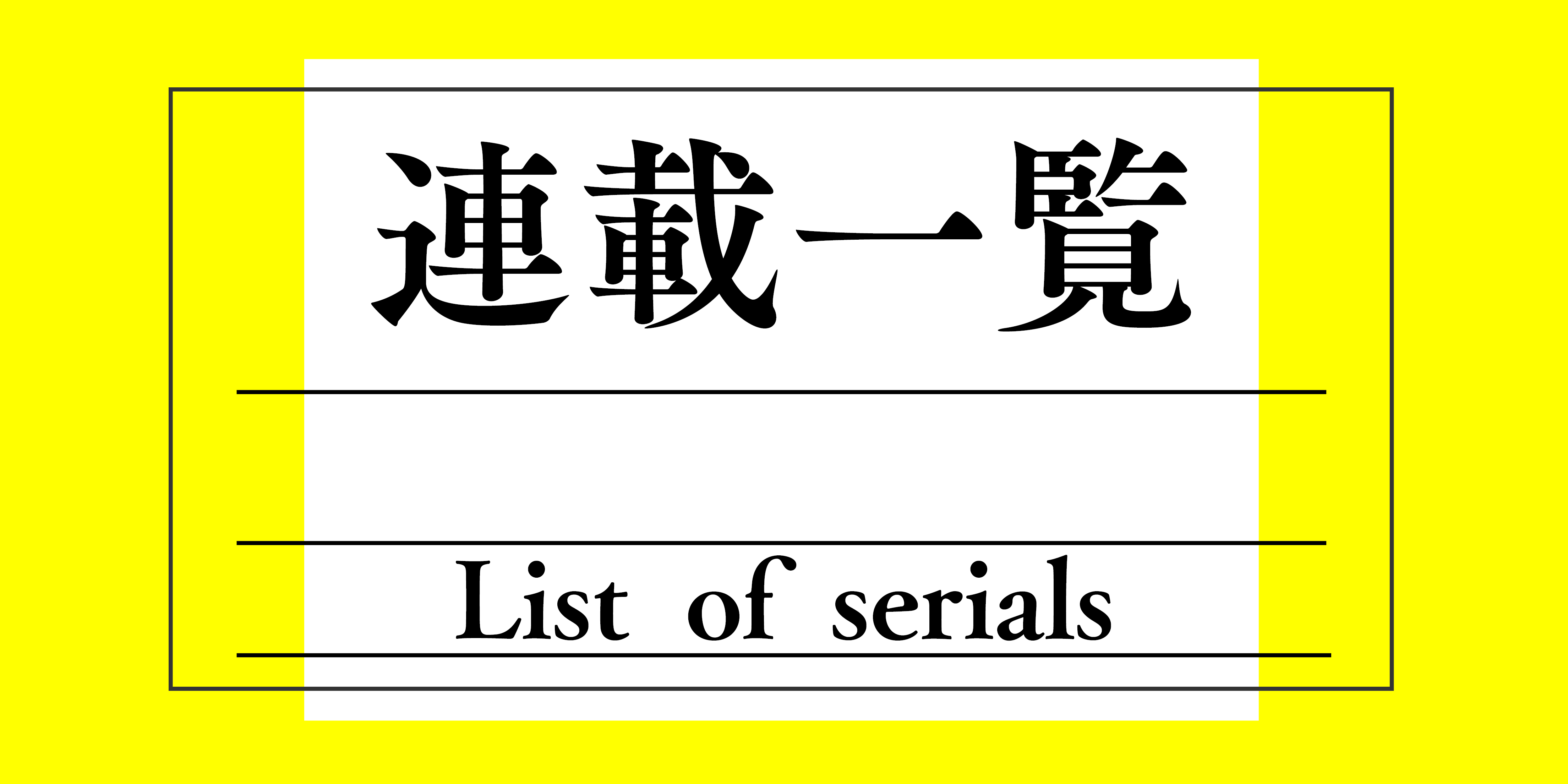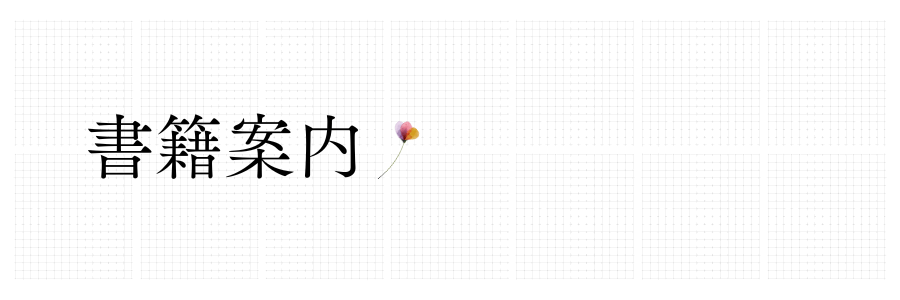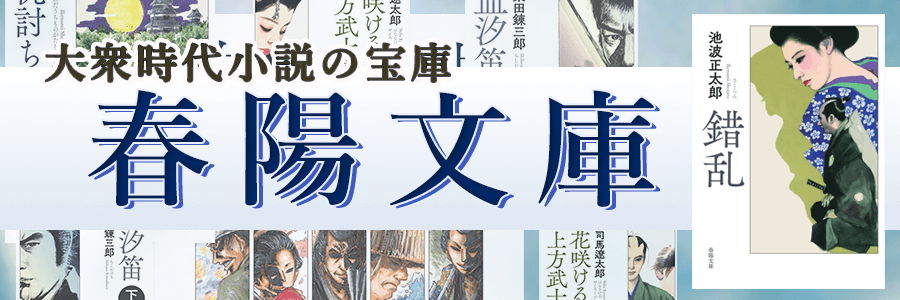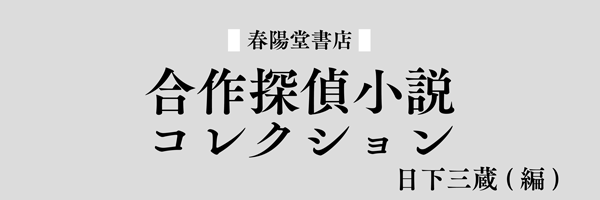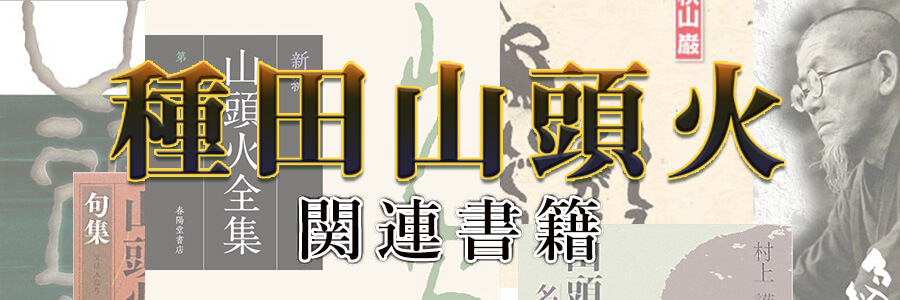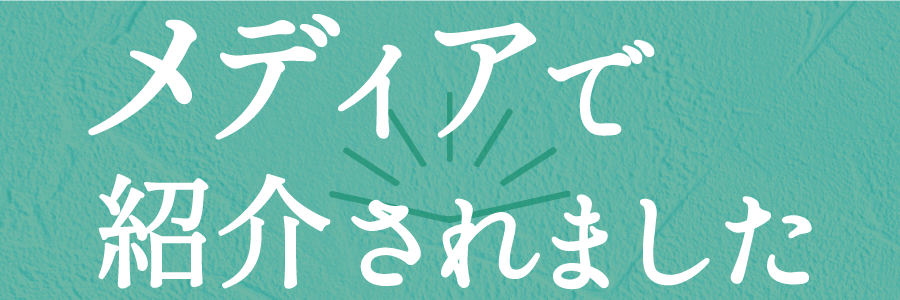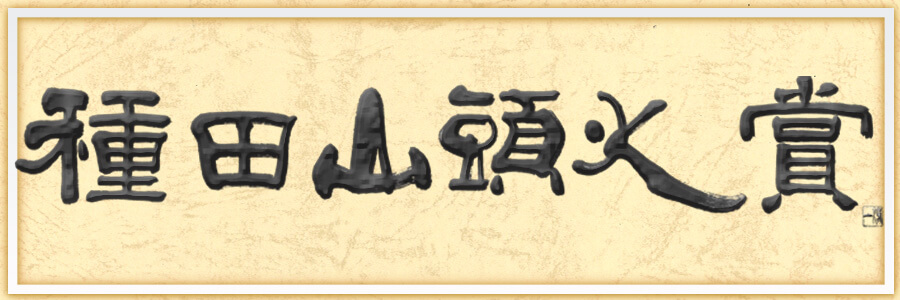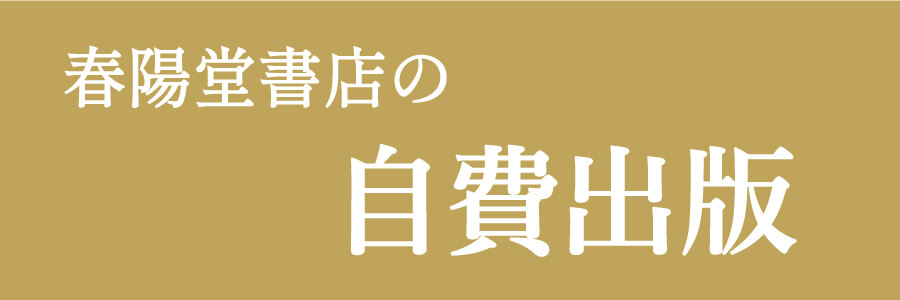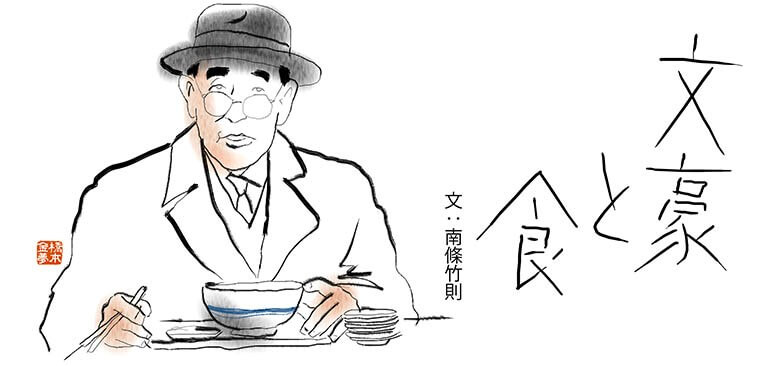
南條 竹則
第3回 鏡花と焼芋【前編】
余は凡ての菓子のうちで尤も羊羹が好だ。別段食いたくはないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも半透明に光線を受ける具合は、どう見ても一個の美術品だ。*1
これは漱石の「草枕」の一節である。羊羹という菓子に対する最高の讃辞と言えるだろうが、上等な羊羹は高価い。書生時代の泉鏡花にとって「餅菓子などは贅沢」だったとすると、羊羹などまさに高嶺の花だ。
「書生の羊羹」という言葉はそこから来ている。これは鏡花が小説「薄紅梅」の中で紹介する焼芋の別名である。

糸七には作家を志す学士で矢野弦光という友達がいる。
二人はある日、吉原へ行った帰り、弦光の家で飲み直すが、腹ごしらえのため帰り道に何か食べるものを買おうということになった。
糸七は焼芋が良いと言った。
雪の降る寒い日だ。焼芋ならお腹はくちくなるし、暖かい。糸七に言わせると、「粮と温石と凍餓共に救ふ、万全の策だつた」(『鏡花全集』巻二十四、499頁)のに、弦光はその案を斥けて安い肉を買った。
弦光の家へ行くと、婆さんが味噌汁を出してくれる。ところが中味は芋殻ばかりなので、糸七はボヤく。
「それだから焼芋を主張したのに、ほぐして入れると直ぐに実になる。」
しかし、弦光は、
「仲之町の芸者の噂のあとへ、それだけは、その、焼芋、焼芋だけはあやまるよ。」
そう言って頭を下げた。
ここで作者が言う──
同感である。──糸七のおなじ話でも、紅玉、緑宝玉だと取次栄がするが、何分焼芋はあやまる。安つぽいばかりか、稚気が過ぎよう。近頃は作者夥間も、ひとりぎめに偉くなつて、割前の宴会の座敷でなく、我が家の大広間で、脇息と名づくる殿様道具の几に倚つて、近う……などと、若い人たちを頤で麾く剽軽者さえあると聞く。仄に聞くにつけても、それらの面々の面目に係ると悪い。むかし、八里半、僭称して十三里、一名、書生の羊羹、ともいつた、ポテト……どうも脇息向の饌でない。(同501頁)
作者の筆はここからしばらく物語を離れて、自分の身のまわりのことを書き始める。それも焼芋にからんだことだ。「ついこの間の事」、鏡花の家に「一大書店の支配人」がやって来た。
その人は苦労人で、田舎から十四歳で上京し、金物屋で小僧をしていたのだという。昔話を始めて言うには──小僧さんの頃、ある日、泥濘で五厘銅貨を拾った。交番へ届けると、巡査は「若、金鍔を食ふがよかツ。」という。中々優しいお巡りさんだ。
小僧は喜び勇んで菓子屋へ飛び込んだが、そこは立派な菓子屋すぎて、金鍔ひとつは売れないから帰れ、という。
「そこで焼芋ーー」
と支配人が言ったところで、鏡花がすかさず、
「三つ。」
と声をかけた。「金鍔の代わりに焼芋を三つ買ったんですね?」という意味である。
すると──
啊呍の呼吸で、支配人が指を三本。……恁うなると焼芋にも禅がある。(同501頁)
何と呑気な人々であろう。【註】
*1 夏目漱石『草枕』新潮文庫54-55頁。
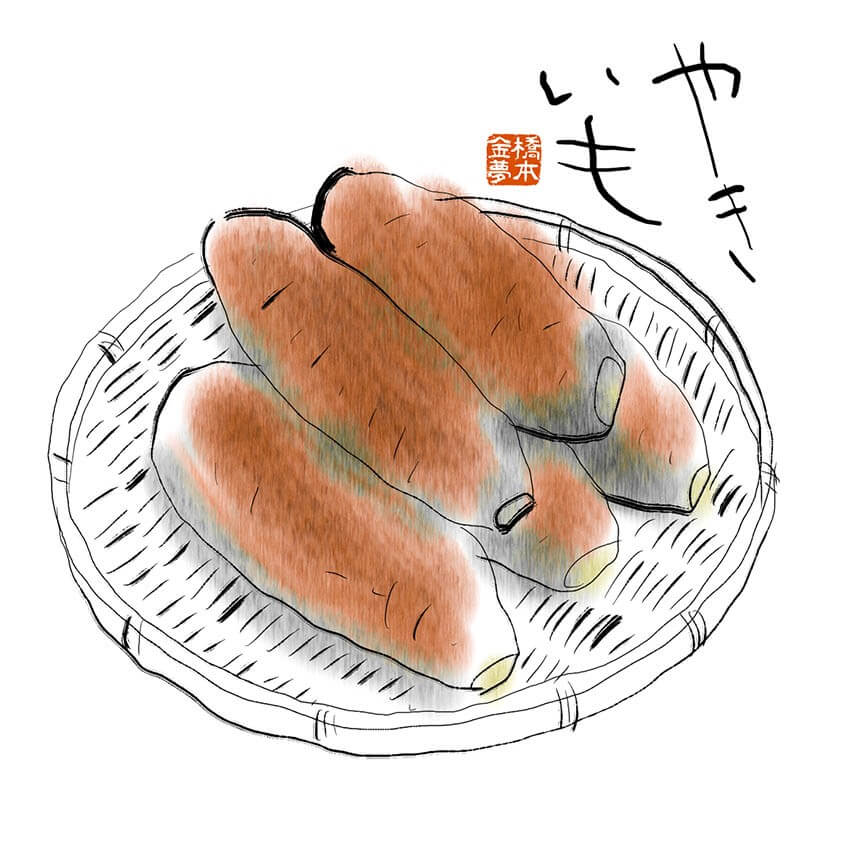
┃この記事を書いた人
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)