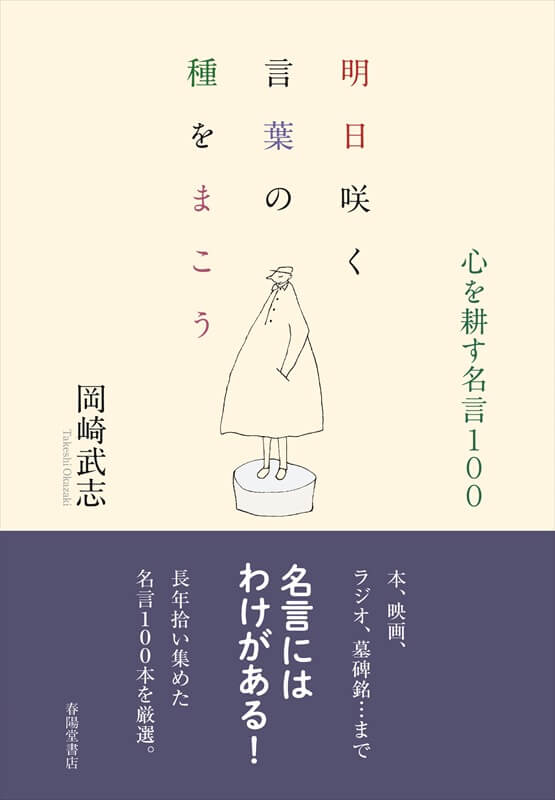【第45回】
『どくろ杯』の東京
金子光晴(1895~1975)といえば、日本を代表する詩人のひとり。代表詩集は『こがね蟲』、『落下傘』など。昭和初年、夫人の森三千代と日本を脱出し、中国、アジア、ヨーロッパの極貧の放浪旅行を続けた。その記録が自伝『どくろ杯』『ねむれ巴里』『西ひがし』にまとまるが、いずれも名作として世評は高い。
『どくろ杯』はその出発編。1923年に最初の詩集『こがね蟲』を出版し、詩壇に鮮烈な衝撃を与えたあたりから、1926年に上海へ渡り惨憺たる日々を送るあたりまでが描かれている。リアルタイムから40年近い月日を経ての回想なのだが、細部にいたるまで印象は曇らず、叙述は今目の前で起こったかのごとく鮮明である。
というわけで、金子の自伝といえば外国紀行になるのだが、じつは『どくろ杯』の前半は日本で暮らしていた時代の話である。とくに中央線沿線に住むあたり、私は関心をもって読んだし、少し調べてみた。つまり金子光晴の東京である。文学好きな女学生(森美三代)と恋仲になり結婚、子どもも生まれるが1926年上海へ。これは1928年から本格的に始まる地獄旅の前哨戦で、1カ月ほどして一旦日本へ帰る。
というわけで、金子の自伝といえば外国紀行になるのだが、じつは『どくろ杯』の前半は日本で暮らしていた時代の話である。とくに中央線沿線に住むあたり、私は関心をもって読んだし、少し調べてみた。つまり金子光晴の東京である。文学好きな女学生(森美三代)と恋仲になり結婚、子どもも生まれるが1926年上海へ。これは1928年から本格的に始まる地獄旅の前哨戦で、1カ月ほどして一旦日本へ帰る。

「先になんの成算もなしで、しあわせにしてくれるあてなどないことが一目でわかるような私に、いっさい任せたような顔をしてついてくる三千代も、浮世ばなれのした存在だった」と書くが、関東大震災以後に東京西側郊外へ移転してきた多くの貧乏文士は、いずれも似たような「先になんの成算もなし」の「浮世ばなれのした」者たちばかりだったのだ。そんなどん底の悲惨を、光晴は三千代の体を抱くことでなぐさめた。これはお金がかからない。
世はプロレタリア文学全盛、「高円寺、阿佐ヶ谷あたりは、右をみても、左をみても、なま半ちくで、口先の達者なにわかコムニストがうようよしていた」とある。一家が住む2階建て物件は、「震災後の物資不足とは言いながら壁紙の下が新聞紙だけというひどい家」で、痴話げんかをして光晴が三千代を突き飛ばすと、「からだの大きさにすっぽりと壁がぬけて隣の部屋にころがり出た」というから落語の世界だ。
しばらくして、もっと高円寺よりの「平屋建て三室の小家」へ引っ越す。家財道具は手押し車に積み込んで、自分たちで運んだ。現在は少しの余地もなく住宅やマンション、古アパートと店舗が建て込んだ高円寺周辺だが、昭和初年は「見渡す限り畑」だったという。これが中央線の北側か南側か判明しないのだが、私がかつて住んでいた環七の東側、高円寺南5丁目に近い場所ではないかと想像すると、ちょっとうれしくなるのである。
この時代の中央線文士による貧乏話は果てしもなくバリエーションが豊富で、話題が尽きることはない。何カ月か続いた高円寺暮らしで、金子一家も「近所の商人たち、米屋、雑貨屋、そば屋、豆腐屋と、店並みに借金ができ、豆腐屋などは、一丁五銭の豆腐が百丁、計五円也というためかたであった」。「五円」は現在の1万円ぐらいか。これは、まだ月末にまとめて代金を徴収する「掛け売り」という商法が残っていたことを示す。
もちろん、と言っては変だが、こうなると家賃も溜めに溜め込んでいる。しかし、上には上があるもので、友人の陶山篤太郎(詩集『銅牌』の詩人、政治家)は「放っておき給え。僕などは、家賃を二十六ヶ月ためている。おなじ長屋の連中がそれで気をつよくして、有難がっているので、いまさら払うわけにはゆかなくなったよ」と励ました。これまた落語みたいな世界だが、大家はたまったものじゃないだろう。
しかし光晴は再三の大家からの催促攻撃を気に病んでいた(それが普通である)。そしてとうとうある夜、夜逃げをしたのである。すべて長兄の計らいで、用意されたトラックに家財道具とともに乗りこみ、次に移り住むのが「京王線笹塚から右へ入って谷一つ越えてむこうの丘の、中野雑色という新開地」だった。「雑色」は今や消えた町名で、現在の中野区南台5丁目あたりを指すようだ。同地に「中野区立雑色子どものあそび場」という公園があり、「雑色」の名が残されている。京王線「笹塚」駅まで直線で1キロぐらいの距離か。
この頃、光晴は何をして稼いでいたか。『どくろ杯』によると、もっぱら講談社の雑誌の埋め草原稿を書いて、原稿料を得ていたようだ。しかし、当時団子坂にあった講談社までは歩いて電車賃を倹約していた。ちょっと話が長くなったが、ついでに当時の交遊関係のエピソードも拾っておく。興味をもたれたら、ぜひ現物『どくろ杯』を読んでいただきたい。私が今手にしているのは中公文庫の昭和51年5月刊の初版。ロングセラーとなり、現在でも新刊で入手可能である。
日本野鳥の会創始者の中西悟堂。「坊主あがりの野放図な男で、穀食を断って、松のみどりをちぎって常食にしていた」。田舎道を歩いていて、葉に止まる青蛙を見つけると「にぎりずしをつまむような手つきで」ぺろりと食べた。岡山出身の、こちらも坊主あがりの詩人・赤松月船は「食うものがないと、一家、断食をした」。それを坊主仲間では「釜を洗う」という。
まあ、きりがない。これぐらいにしておこう。金子光晴が住んだ「中野雑色」へは、いずれ訪ね、散策しようと思っている。

家呑みでバー「露口」ごっこ
NHKで『ドキュメント 露口~松山・伝説の老舗バー』を見た。「伝説のハイボール」とバー「露口」と聞いて、これは過去にも見聞きしたぞと気づく。それほど有名なバーなのである。カウンター13席(現在はコロナ対策で席数を減らし営業)だけの小さな店。マスター露口貴男と妻・朝子で切り盛りする。昭和33年の創業で、グラスも一枚板のカウンターも開店当初からのもの。
さて、著名人や地方からもわざわざ訪ねて飲みにくる「伝説のハイボール」とは? 番組で作られるところを見ていると、小さめのグラスに、まずサントリーの「角」を注ぎ込む。ツーフィンガーほどか。そのあと、大きめの氷を数個。ウィルキンソンの炭酸を3度ぐらいに分けて入れ、最後にバースプーンで静かにかきまわす。ただ、それだけのこと。何か秘伝や特別なものを入れるわけではないのだ。それでいて、「ここの濃いめのハイボールは違う。日本で一番うまい」なんて客が言う。そして、本当にうまそうだ。じつに不思議。
いろいろ検索してみると、訪問した客のコメントに「3杯のハイボールとチャージで3000円」とあったので、どうだろう、「角」のハイボールが1杯800円か900円なのか。高くもないがけっして安いとは言えない。チャージとは、チャームと呼ばれるおつまみの「ポップコーン」のことか。行きつけのバーのマスターに「露口」の話をし(もちろん彼は知っていた)、使っているものは市販で誰でも手に入るのにおいしいと客が言う「ハイボール」って何か違うのか聞いてみたが、「いや、変わらないと思いますよ。店の雰囲気じゃないですか」とのこと。
さらに、「露口」のハイボールをモデルに商品化したのが、缶の「角ハイボール 濃いめ」だと知る。露口さんが監修というからすごい。こうなると無性にそれが飲みたくなり、コンビニへ走って2缶購入。ついでにポップコーンも買って、家でバー「露口」の疑似体験をすることにした。それを写真に撮ってみたのがこれ。

ちょっとドキドキしながら、レシピと手順を踏まえてハイボールを作って飲んでみた。しかし、じつにありきたりな「角ハイボール 濃いめ」の味で、興奮も天に上る気持ちも顕在しなかった。それより、ポップコーンを食べるのが久しぶりで、「ああ、こういう味だったな」と確かめたことの方が印象に残った。映画館以外でポップコーンを食べた記憶がない。
アメリカの映画で映画を観ながら若者がバケツみたいな容器に入ったのを食べるシーンがよく出てくる。村上春樹『‘THE SCRAP’ 懐かしの一九八〇年代』(文藝春秋)に「映画とポップコーン」という一文があり、「映画といえば暗がりの中で食べるポップコーンとくるのがアメリカの常識」と書かれている。ちなみに村上は「映画を見ながら鰺の押し寿司を食べるのが好きだけど」という。
そして結論。やはり「露口」のハイボールは、松山の店へ出かけていって、目の前で露口さんが作ったのを飲まなければ、本当のところはわからないということだろう。
そして結論。やはり「露口」のハイボールは、松山の店へ出かけていって、目の前で露口さんが作ったのを飲まなければ、本当のところはわからないということだろう。
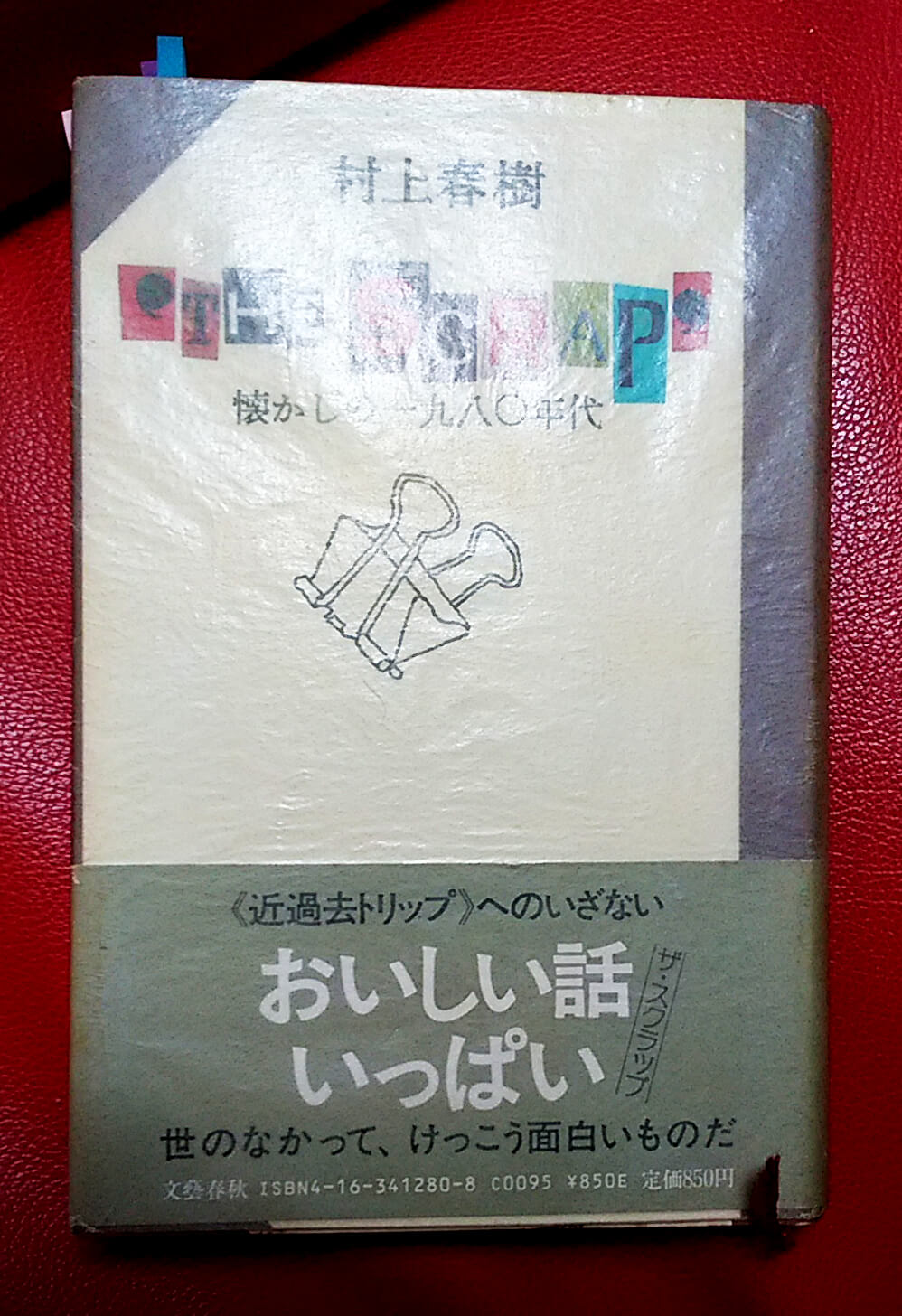
『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
┃この記事を書いた人
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。