
南條 竹則
第15回 林芙美子の食欲【後編】
ただそれだけが語られていたなら、『放浪記』もよほど悲しい作品になるだろう。だが、ここには食欲の充足の瞬間も描かれている。
それは願いそのままの実現とは限らないが、贅沢なものでなくても良いのだ。とにかく、「めし」にありつけた時、『放浪記』の主人公は一切を忘れて、生の恍惚境に浸る。
その描写は鮮烈だ。ちょっと御覧いただこう──
あぶないぞ! あぶないぞ! あぶない不精者故、バクレツダンを持たしたら、喜んでそこら辺へ投げつけるだろう。こんな女が一人うじうじ生きているよりも、いっそ早く、真二ツになって死んでしまいたい。熱い御飯の上に、昨夜の秋刀魚を伏兵線にして、ムシャリと頬ばると、生きている事もまんざらではない。(50頁)
洋食をとって、初めて肉の匂いをかぎ、ずるずるした油をなめていると、めまいがしそうに嬉しくなってくる。一口位は残しておかなくちゃ変よ。腹が少し豊かになると、生きかえったように私達は私達の思想に青い芽を萌やす。(91頁)
飲食店にはいって、ふっと、箸立ての汚ない箸のたばを見ると、私には卑しいものしかないのを感じる。人の舌に触れた、はげちょろけの箸を二本抜いて、それで丼飯を食べる。まるで犬のような姿だ。汚ないとも思わなくなってしまっている。人類も何もあったものではない。只、モウレツに美味いと云う感覚だけで鰯の焼いたのにかぶりつく。小皿のなかの水びたしの菜っぱの香々。(391頁)
まず朝食に、丼いっぱいの御飯にがんもどきの煮つけ一皿。ああ嬉しくて私は膝をつきそうにあわててしまう。
恋などとはたかのしれたものだ
散る思いまことにたやすく
一椀の飯に崩折れる乞食の愉楽
洟水をすすり心を捨てきる
この飯食うさまの安らかさ
これも我身なり真実の我身よ
哀れすべてを忘れ切る飢えの行
尾を振りて食う今日の飯なり。(423-24頁)
私は木の香のぷんと匂うべんとうを食べる。薄く切った紅いかまぼこ、梅干、きんぴらごぼう。糸ごんにゃくと肉の煮つけ、はりはり、じゅうおうむじんに味う。(440頁)
「じゅうおうむじんに味う」とは何と素晴らしい言葉だろう!洋食をとって、初めて肉の匂いをかぎ、ずるずるした油をなめていると、めまいがしそうに嬉しくなってくる。一口位は残しておかなくちゃ変よ。腹が少し豊かになると、生きかえったように私達は私達の思想に青い芽を萌やす。(91頁)
飲食店にはいって、ふっと、箸立ての汚ない箸のたばを見ると、私には卑しいものしかないのを感じる。人の舌に触れた、はげちょろけの箸を二本抜いて、それで丼飯を食べる。まるで犬のような姿だ。汚ないとも思わなくなってしまっている。人類も何もあったものではない。只、モウレツに美味いと云う感覚だけで鰯の焼いたのにかぶりつく。小皿のなかの水びたしの菜っぱの香々。(391頁)
まず朝食に、丼いっぱいの御飯にがんもどきの煮つけ一皿。ああ嬉しくて私は膝をつきそうにあわててしまう。
恋などとはたかのしれたものだ
散る思いまことにたやすく
一椀の飯に崩折れる乞食の愉楽
洟水をすすり心を捨てきる
この飯食うさまの安らかさ
これも我身なり真実の我身よ
哀れすべてを忘れ切る飢えの行
尾を振りて食う今日の飯なり。(423-24頁)
私は木の香のぷんと匂うべんとうを食べる。薄く切った紅いかまぼこ、梅干、きんぴらごぼう。糸ごんにゃくと肉の煮つけ、はりはり、じゅうおうむじんに味う。(440頁)
胃袋は一騎当千の武者。戦場を駆けめぐって、敵を片端から平らげる。こんな痛快な表現が一体、ほかの誰にできるだろう。
命をつなぐ「めし」からは、こういうクラクラするような忘我の喜びが生まれるが、語り手にもう少し余裕がある時、すなわちお菓子の類を食べる時は、詩ももっと温柔しいチャーミングなものになる。
たとえば、屋台の綿飴を描くくだりを御覧いただきたい。
湯島天神に行ってみた。お爺さんが車をぶんぶんまわして、桃色の綿菓子をつくっていた。あるかなきかの桃色の泡が真鍮の桶の中から湧いて出てくると、これが霧のような綿菓子になる。長い事草花を見ない私の眼には、まるでもう牡丹のように写ります。「おじいさん! 二銭頂戴。」子供の頭ぐらいの大きい綿菓子を私はそっと抱いた。誰もいない石のベンチでこれを食べよう。綿菓子を頬ばって、思うまじ見まじとすれど我家かな、漠然とこんな孤独を愛する事もいいではありませんか。(330頁)
こちらはたい焼きだ── あんまり寒いので、坂の途中の寺の前のたいやき屋で、たいやきを十銭買う。芳ちゃんと歩きながら食べる。のこりの二つを一つずつ分けて、二人ともあったかい奴を八ツ口の間から肌へじかにつけてみる。
「おおあついッ」
芳ちゃんが笑った。私はたいやきを胃のあたりへ置いてみる。きいんと肌が熱くていい気持ちだ。かいろを抱いているみたいだ。我慢のならない淋しさが胃のなかにこげつきそうになって来る。(420-1頁)
飢寒二つながら救うというのは、鏡花の焼芋を思い出させる。「おおあついッ」
芳ちゃんが笑った。私はたいやきを胃のあたりへ置いてみる。きいんと肌が熱くていい気持ちだ。かいろを抱いているみたいだ。我慢のならない淋しさが胃のなかにこげつきそうになって来る。(420-1頁)
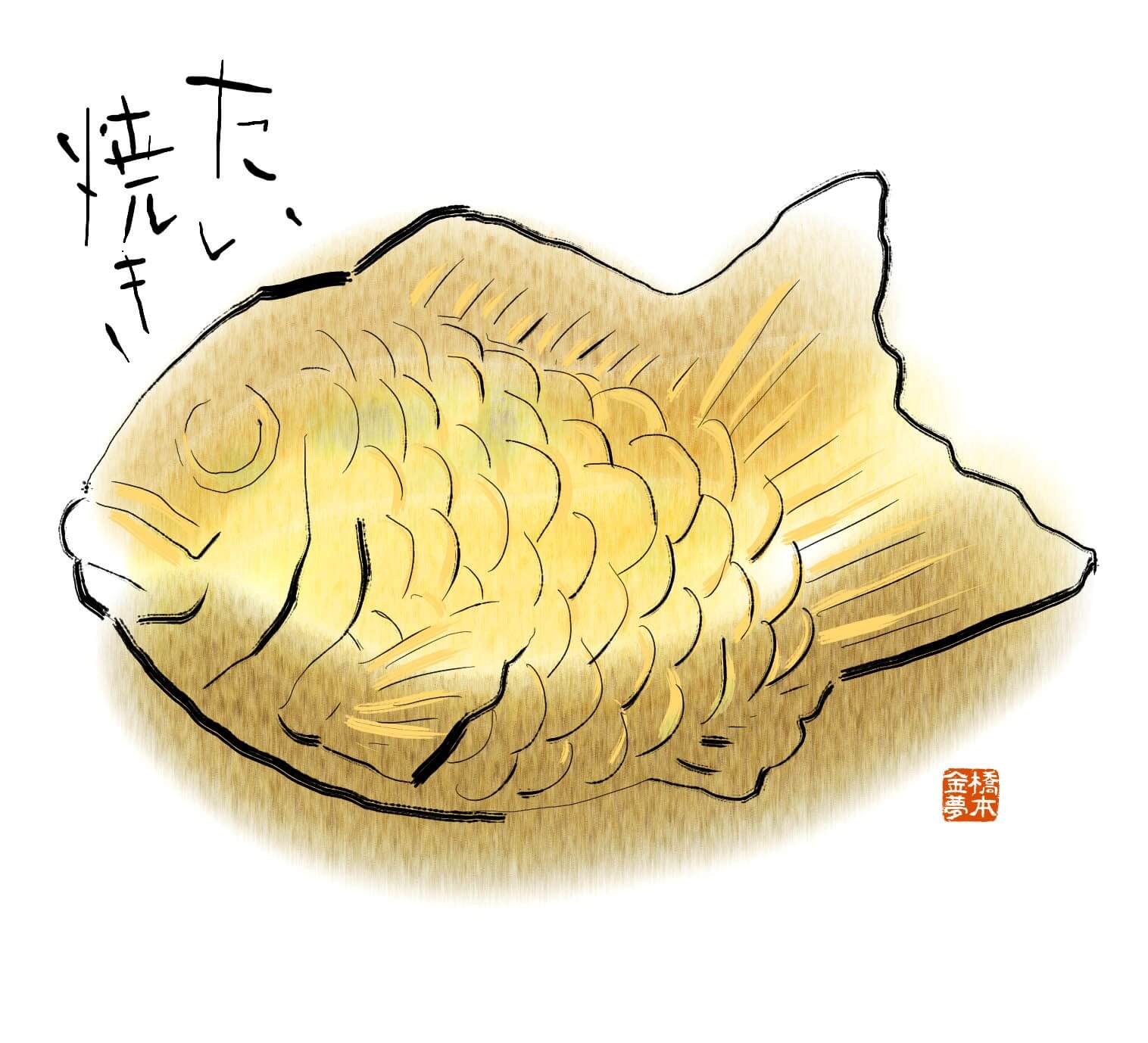
『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
┃この記事を書いた人
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
























