
南條 竹則
第16回 「支那そば」が食べたくて
「蓬莱軒のシナそば飛んで来い。」という詩は前に引用したが、ほかにも例はたくさんある──
朝の掃除がすんで、じっと鏡を見ていると、蒼くむくんだ顔は、生活に疲れ荒さんで、私はああと長い溜息をついた。(中略)支那そばでも食べたいなあと思う。(新潮文庫版116頁)
壁に積んである沢山の本を見ていると、なぜだか、舌に唾が湧いて来て、この書籍の堆積が妙に私を誘惑してしまう。どれを見ても、カクテール製法の本ばかりだった。一冊売ったらどの位になるのかしら、支那蕎麦に、てん丼に、ごもく寿司、盗んで、すいている腹を満たす事は、悪い事ではないように思えた。(315頁)
午前一時。二人で戸外へ出て支那そばを食べた。朝から何もたべていなかった私は、その支那そばがみんな火になってしまうようなおいしい気持ちがした。(319頁)
お金がほしく候。
ただの十円でもよろしく候。
マノンレスコオと、浴衣と、下駄と買いたく候。
シナそばが一杯たべたく候。(386頁)
どうにも空腹にたえられないので、私はまた冷い着物に手を通して、七輪に火を熾す。湯をわかして、竹の皮についたひとなめの味噌を湯にといて飲む。シナそばが食べたくて仕方がない。(438頁)
こうした「支那そば願望」は『放浪記』以外の作品にも顔を出す。壁に積んである沢山の本を見ていると、なぜだか、舌に唾が湧いて来て、この書籍の堆積が妙に私を誘惑してしまう。どれを見ても、カクテール製法の本ばかりだった。一冊売ったらどの位になるのかしら、支那蕎麦に、てん丼に、ごもく寿司、盗んで、すいている腹を満たす事は、悪い事ではないように思えた。(315頁)
午前一時。二人で戸外へ出て支那そばを食べた。朝から何もたべていなかった私は、その支那そばがみんな火になってしまうようなおいしい気持ちがした。(319頁)
お金がほしく候。
ただの十円でもよろしく候。
マノンレスコオと、浴衣と、下駄と買いたく候。
シナそばが一杯たべたく候。(386頁)
どうにも空腹にたえられないので、私はまた冷い着物に手を通して、七輪に火を熾す。湯をわかして、竹の皮についたひとなめの味噌を湯にといて飲む。シナそばが食べたくて仕方がない。(438頁)
「清貧の書」に曰く──
唾を吞み込もうとすると、舌の上が妙に熱っぽく荒れている。何か食べたい。──赤飯に支那蕎麦、大福餅にうどん、そんな拾銭で食べられそうなものを楽しみに空想して、私は二枚の拾銭白銅をチリンと耳もとで鳴らしてみた。(『林芙美子』ちくま日本文学020 111頁)
「泣虫小僧」の登場人物・勘三の台詞には、こうある──「あああだ、君の顔をみると、家賃の請求書に見えて仕方がないよ。ま、とにかく、俺の留守には、支那蕎麦の十杯も食べて吞気に待っていなさい。ええ?」(同175頁)
こんなにも「支那そば」を愛する人は、「そば」だけではない本式の「支那料理」に出会った時、一体どんな顔をしたろう?わたしはそう思わずにいられなかったが、林芙美子はこの問いに答えている。
『放浪記』がベストセラーになって金も文名も手に入れた彼女は、後年北京へ行き、滞在記「北京紀行」を書いた。
その一節に曰く──
私は二十日近くも北京の街ですごした。
北京はほんとうにいい処だ。一人で飯を食べに行くことも覚えて愉しかった。ホテルでは朝食だけにして、私は昼も晩も外へ出て支那料理へ這入った。私はいままで色々な処で支那料理も食べたが、北京で食べた支那料理の美味しさは舌が気絶しそうだと云っても過言ではないだろう。承華園と云う処を人に教わると、私はホテルから近いので、そこへたびたび一人で出かけて行った。私が行くとボーイはすぐ、雞糸胡瓜片と云うのを一番さきに出してくれる。鶏肉と胡瓜のなますのようなものでとても美味い。舌にも胸にも孤独に徹する豊かさである。(『下駄で歩いた巴里』岩波文庫16-17頁)
「雞糸胡瓜片」は、みなさん、料理名は御存知なくとも、目の前に出てくれば「ああ、これか」とお思いになるだろう。まさに鶏肉と胡瓜のなます(但し、鶏は蒸し鶏)で、北京料理屋ならたいていある平凡な冷菜だ。けれども、胡瓜がみずみずしく、鶏肉に味があって、蒸し加減が良く、作りたてなら、人を十分幸福にする。これを肴に老酒でも飲めば最高だ。北京はほんとうにいい処だ。一人で飯を食べに行くことも覚えて愉しかった。ホテルでは朝食だけにして、私は昼も晩も外へ出て支那料理へ這入った。私はいままで色々な処で支那料理も食べたが、北京で食べた支那料理の美味しさは舌が気絶しそうだと云っても過言ではないだろう。承華園と云う処を人に教わると、私はホテルから近いので、そこへたびたび一人で出かけて行った。私が行くとボーイはすぐ、雞糸胡瓜片と云うのを一番さきに出してくれる。鶏肉と胡瓜のなますのようなものでとても美味い。舌にも胸にも孤独に徹する豊かさである。(『下駄で歩いた巴里』岩波文庫16-17頁)
ボーイがすぐにこの料理を出して来たのは、林芙美子が何度も注文したからだろう。また、それ故に彼女は中国語の料理名をおぼえたのだろう。あるいは、初めて食べた時、誰かに書いてもらったのかもしれない。
さて、この冷菜をプレリュードにして、そのあと海参が出たか、フカヒレが出たか、それとも「油爆双脆」でも出てきたか知らない。
とにかく、「舌が気絶しそう」なくらいの美味が彼女の孤独を慰めたのだ。
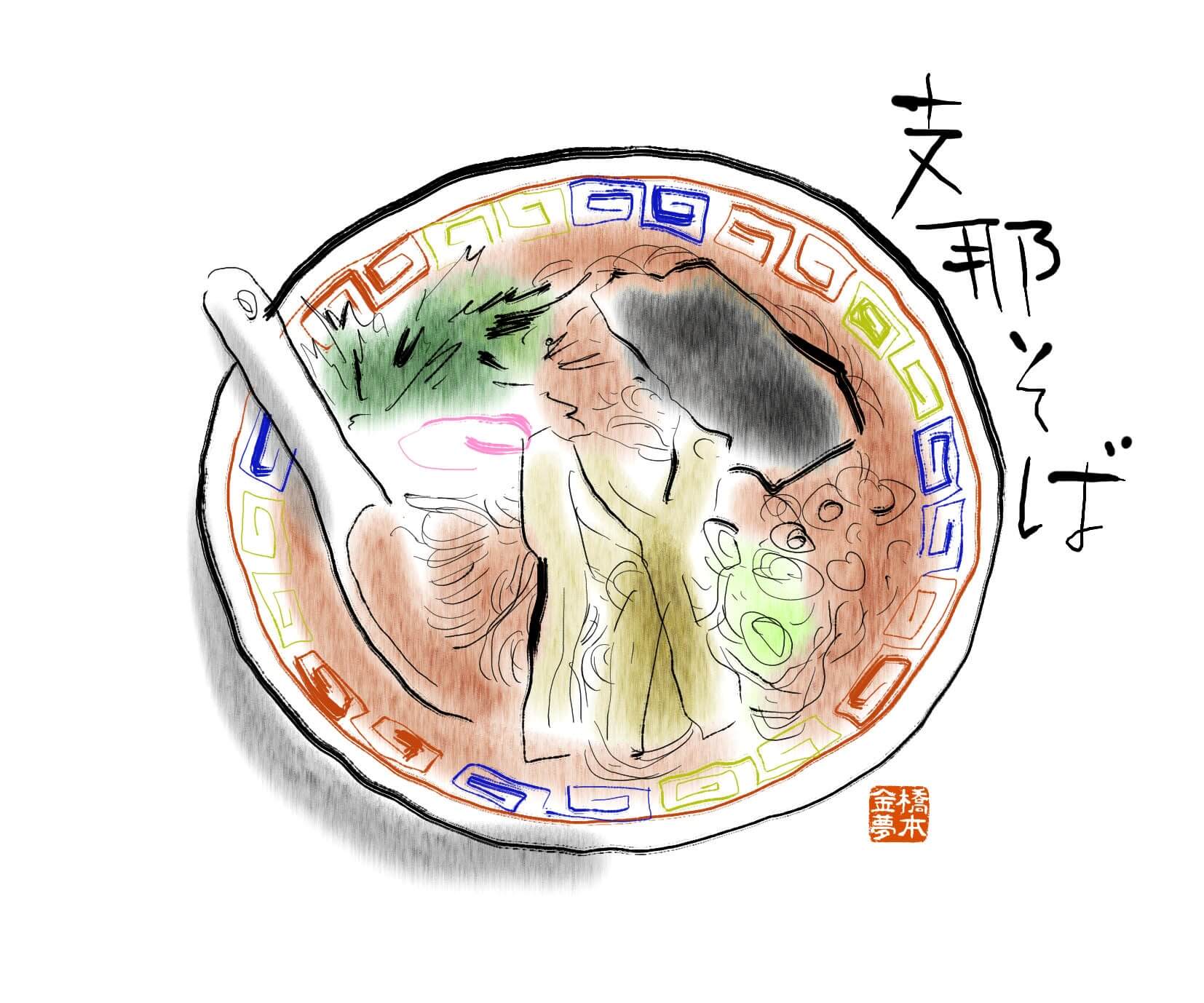
『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
┃この記事を書いた人
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
























