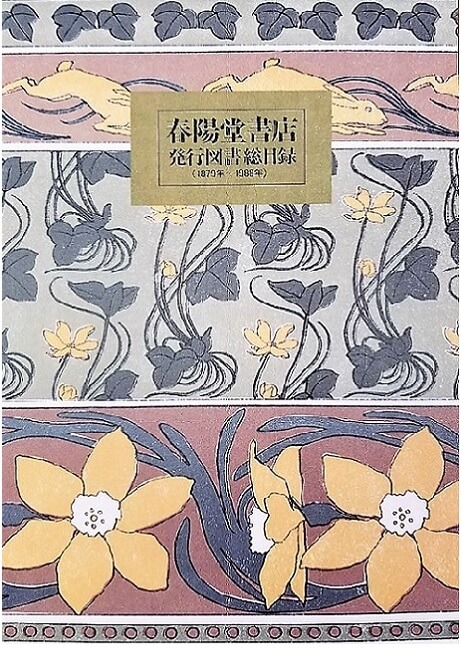第10回『二人女房』──銀と鉄、新所帯を切りまわすお金の話
東海大学教授 堀 啓子
感染症の猛威も少し落ち着き、人の集まる機会もわずかずつ増えてきました。秋の時候の良さも手伝い、週末にはご婚礼の招待客らしき方々も街中でお見かけします。今月は、姉妹二人の結婚をテーマとした作品を紹介します。明るい話題のうちにも結婚にまつわる様々なお金の騒動が描き出される、ユーモラスで微笑ましい一作です。
明治二十四年八月、『読売新聞』で連載を抱え、春陽堂から出版した単行本の売れ行きも好調だった尾崎紅葉は多忙を極めていた。その忙しい合間をぬって、金港堂の文芸誌『都の花』に連載したのが『二人女房』である。春陽堂の『小説萃錦』と同じく、近代文芸誌としては最初期に発刊された『都の花』は、同時期に活躍した多くの作家とゆかりが深かった。だがこの年の春、掲載された二編の小説が風俗壊乱にあたるとされて、『都の花』に発行停止が命ぜられる。三か月後にようやく解停となったとき、編集部が期待を寄せたのが華やかな紅葉作品だった。その意を受け、満を持して発表されたのが『二人女房』である。

『読売新聞』(明治二十四年八月一日)掲載の金港堂の広告。
『都の花』解停に当たって、『二人女房』を掲げることを大々的に宣伝し、その期待の高さを窺わせる。
某省の極卑いところを勤める丸橋新八郎といふ士族の娘にて、姉の名は銀、妹は銕、容貌は羽子板の裏表、肖てはゐねど同腹にて、姉は父親肖、妹は母親肖なり。
そう形容される二人は、姉が十九、妹が十七という仲良し姉妹で、両親と平和な暮らしを営んでいた。
人気作となった『二人女房』は、明治三十年六月には、もうひとつの大手出版社であった博文館の雑誌『太陽』の「創業十周年記念臨時増刊」に再掲された。左から、『二人女房』冒頭、結末と、『太陽』の奥付(著者蔵書)
嫁るに決めなさい。大した結構の口だ。まづ大磯の方に二千円ほどの地面があつて、さ、よしか、地坪が五十坪で建坪が二十五坪といふ居宅が自分の家作で、婢女が二人に書生が一人、お抱へ車で車夫が一人さ。奥には六十五になる姑が唯一人で、当人は奏任の百円といふ身分で、よしかへ、実意があつて優しいといふのだから、此上の望蜀はありやしない。年齢も二度目もいつた理のものぢやない。
奏任とは、当時の官吏の身分で高等官を指す。巡査や小学校教員の初任給が八円前後、もりかけ蕎麦が一杯一銭に値上がりしたと騒ぎになった年に、月給百円といえば高給取りに相違なく、相応の家産もある裕福な人物である。月給十八円の下級職の父親が、この好条件に色めき立つのも無理はない。近所衆のやっかみもあり、母親もお銀も色々悩みは尽きぬものの、最終的には輿入れすることに決まった。前日には例規の立振舞とて、赤飯は一升炊家内の盃事。父親は目出たい/\と口にはいへど、常に酒に対ふほどの元気は無くて萎れたる顔色。母は脆くも涙を浮べて、今日ばかり物懐かしげにお銀の顏のみ眺むれば、庭に柿の落葉する風も哀を誘ふ心地してお鉄もしみ/“\悲しく覚えぬ。
こうして秋の好日、お銀が嫁いでいくと、結構な暮らしが待っていた。夫には寵愛され、姑との折り合いも良く、使用人たちにも「奥様」と奉られる。娘時代とは雲泥の差で、お銀自身にも「これが玉の輿かと乗て見れば異なもの」に感じられる。
宮川春俤『美人十二カ月 其十一 嫁』口絵(国会デジタルコレクション)。華やかな当時の若い既婚婦人の身支度の様子が描かれる
さらにお銀の心痛に追い打ちをかけたのは、夫、周三の失職である。
時に不運なるかな、官海の風波穏かならず、鯰鰌大いに恐慌の折から、渋谷周三も非の字となつて、官制改革後であるから、三年間の涙金は下らぬ始末。
「鯰鰌」は、鯰や鰌のような形のひげを蓄えた男性、ここでは当時の上級官吏を指し、「非の字」とは非職すなわちリストラである。だが厳密に言えば「官吏が身分・地位はそのままで職務だけ免ぜられること」で、自己都合も含め、要因はケースバイケースで、条例によると「廃庁廃官」「疾病」「事故」などがある。俸給は三分の一となるが、明治二十四年の非職条例改正までであれば、三年間は保証されるはずだった。だがこの作品が発表されたのも明治二十四年で、登場人物の動きは、恐らく時期を合わせて想定されているであろう。そのため、渋谷の場合も、もはやそうした救済措置もなく、経済的な余裕を失ってしまう。小さな貸家住まいになった息子夫婦の苦境に姑も我を折って戻り、何とか家内和合に落ち着いた。
当時は、多くの紳士が髯をたくわえていた。規則正しいまっすぐな髯を生やしている人は自制心が強い、など口髭でその人物の性格がわかるとする興味深い説も発表されている。左は松尾久太郎『紳士淑女談話の種草』(明治二十一年 国会デジタルコレクション)
右は「美髯の紳士」という記事(『読売新聞』明治三十五年五月十一日)
容色を買われて玉の輿に乗ったが気苦労の多い姉と、背伸びをせず近所の昔馴染に嫁いで「成人したお坊様と飯事をするやうな楽世帯」の妹。ともにごく平均的な気質性格で、どこにでもいるような娘たちゆえに、その日常にはリアリティーがある。
結末は紅葉らしく、「皆々様御推もじ被下度候。」と結ばれるが、お鉄の懐妊に続き、どうやら渋谷家からも吉報がもたらされる予感である。
人生の曲がり角ごとに突きつけられる大きな選択。それを自身で選び取り、その道をまっすぐ進むのが一番。そんな紅葉のメッセージは、今も昔も変わらず読者に響いてくる。
【今月のワンポイント:官吏の非職】
作品中、お鉄は夫の収入に見合うかたちで堅実に家計をやりくりし、お銀は裕福だった夫の失職に伴って経済的な苦労をする。『二人女房』の少し前に、同じく言文一致体で話題を呼んだ二葉亭四迷の『浮雲』にも、職を解かれた人物が登場する。じつは当時、官吏の非職・免職はさほど珍しいことではなかった。
この問題に関して比較的知られているのは、伊藤博文による、官僚制整備のための官吏非職条例の公布(太政官布告第三号・明治十七年一月四日)であろう。だが、実際にはその前からこうした事態は起きており、新聞でもしばしば報じられていた。
そのため、シリアスな問題であるいっぽう、巷では「非職」「免職」は流行語になった。酒宴などでは、猪口のまわりが悪い場合には「非職らしいからお一つ」と言って勧め、酒を切り上げて食事にする場合はお猪口を「免職」にしたといい、芸者がお茶を挽いているときも「当時非職」、客が離れたのを「免職」、座が休業中の役者は「非職でござります」などと言いつつ騒いだという。

「官吏と小使」(池辺義象[他]『当世風俗五十番歌合』明治四十年)(著者蔵書)自慢の口ひげに触れる癖のある官吏が多かった
『春陽堂書店 発行図書総目録(1879年~1988年)』春陽堂編集部(編)
春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。
書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。
表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。
春陽堂が1879年~1988年に発行した図書の総目録です。
書名索引付き、747ページ。序文は春陽堂書店5代目社長・和田欣之介。
表紙画は春陽堂から刊行された夏目漱石『四篇』のものをそのまま採用しました。
┃この記事を書いた人
堀 啓子(ほり・けいこ)
1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。
堀 啓子(ほり・けいこ)
1970年生まれ。東海大学教授。慶應義塾大学文学部卒業。慶應義塾大学大学院文学研究科博士課程単位取得、博士(文学)。日本学術振興会特別研究員(PD)を経て、現職。国際児童文学館 令和3年度特別研究者。専門は日本近代文学、比較文学。2000年に尾崎紅葉の『金色夜叉』にアメリカの種本があることを発見、その翻訳『女より弱き者』(バーサ・クレー著、南雲堂フェニックス、2002年)も手がけた。主な著書に、『日本近代文学入門』(中公新書、2019年)、『日本ミステリー小説史』(中公新書、2014年)、『和装のヴィクトリア文学』(東海大学出版会、2012年)、共著に『21世紀における語ることの倫理』(ひつじ書房、2011年)などがある。