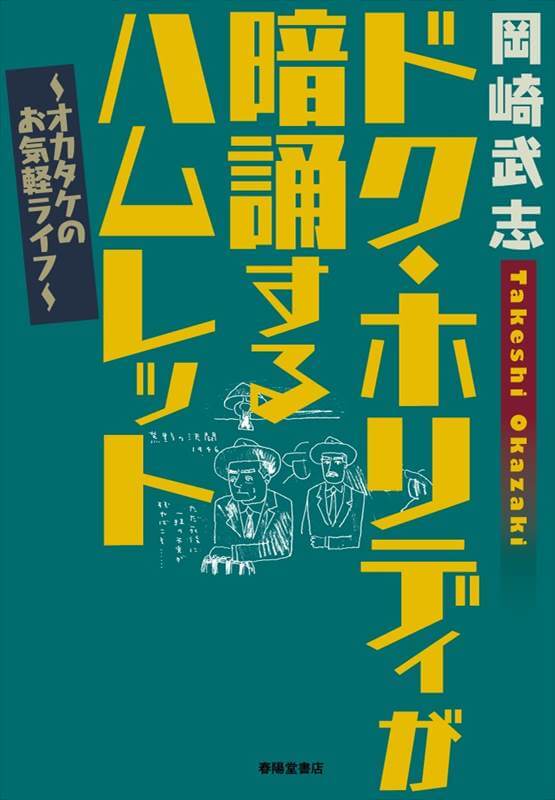【第79回】
もくじ
記憶の不思議
時々、不意にあることを思い出して、なんでそんなことをいつまでも覚えているのだろうと不思議に思うことがある。高校の同窓会が開かれて、思い出を語り合う時、同じ体験を共時した者たちでも、覚えている場面やポイントがずいぶん違う。こちらの記憶の間違いを訂正されることもある。「ええ、そうだったのか!」と大げさに言えば驚愕するような事実を知るケースに出くわすと、つくづく記憶というもののメカニズムを謎だと思うのである。
たとえば、今でも写真に撮ったように場面をはっきり頭に刻み付けられた記憶がある。私は小学3年までに出生地から3度転居をしている。2度目の転居が同じ大阪市北区内でなされた。小学1年の途中で、樋之口町から北へ1キロほど離れた長柄東へ移った。どちらも父親が勤務していた紡績会社の社宅で、樋之口町が木造平屋の長屋方式、長柄東が鉄筋コンクリートのいわゆる団地であった。最新の地図で確かめたら、この一帯は現在「URリバーサイド ながら」という都市公団の団地になっているようだ。
この記憶は後者の長柄東時代。ここも小学3年の途中で枚方市へ引っ越すことになる(父親は会社を辞めた)から、せいぜい1年半か2年という短い期間である。我々一家が住む棟のすぐ目の前が小学校の運動場ぐらいの規模の広場になっていて、私はここで自転車の練習をして乗れるようになったのである。同級生にくらべてずいぶん習熟は遅かったが、本を読むこと以外はすべてのことにおいてそうであった。
社宅のすぐ東を淀川の支流である大川が南北に流れていて、七夕の時など、この川で七夕飾りを橋の上から流したのだった。当時は幼くて、地理的関係や地名などに関心はなかったが、のち、七夕飾りを川へ流した橋が毛馬橋だと知る。対岸は毛馬町。江戸時代は毛馬村で蕪村の出生地であった。現在、公園にはそのことを示す碑が建っている。
繰り返しになるが、私たちが住んだのは紡績工場の社宅で、広い敷地内に工場もあり、また木造平屋の社宅もあった。一つの町に相当する広い地所だった。ここで会社の運動会やレクリエーションなどが子どもも交えて行われたのである。社員の子どもたち向けの遠足もあった。「はっきり頭に刻み付けられた記憶」とは、この遠足での一場面である。広場を挟んで向かい側に木造平屋の長屋式社宅があって、そこに住む一家の兄妹と淡い交流があった。妹が私と同学年で、ただし先述したように私が入学した小学校(菅北小学校)は1キロ先にあり、私はそのまま転校せずに通っていたから、この兄妹とは学校が違う。おそらく2人はすぐ近くの豊仁小学校の生徒だったはず。
親同士があるいは知り合いだったのか、私は兄妹の家に遊びに行ったこともある。印象的だったのは2人の顔立ちで、鹿児島や沖縄などの南方系のはっきりした目鼻立ちを持っていて、子ども向けの小説の挿絵に描かれるようなマスクであった。10代後半まで成長すれば、おそらく互いに美男美女になっただろうと思われる。たとえば歌手の西郷輝彦を見るとき、この兄の面影が重なる。
どれぐらいの人数で、どこを巡った遠足かはまったく記憶にないが、顔なじみであったこの兄妹と行動をともにしていた。兄の方が花柄の魔法瓶タイプの水筒を肩からぶら下げていたが、何の拍子か、これをどこかにぶつけて中のガラス(鏡になっているタイプ)が割れてしまった。音ではっきりわかったのである。
これが私なら「しもた(しまった)! お母ちゃんに怒られる」などと騒ぎたてるところを、兄は一言も発せず(少し顔をしかめたか)、近くにあった噴水にゆっくり近づいて行って、水筒のふたを取って割れたガラスを水中に捨てたのだった。妹の方もそれを黙って見ていた。
記憶というのはこれだけである。引率した大人たちが近寄って何か慰めを言ったり、そのことで子どもたちが騒いだわけではなかったと思う。非常に静かな一場面である。しかも、いわば他人事だ。それでもこの出来事と映像は深く胸の底に刻まれ、何かの拍子にふと思い出されるのであった。おそらく強い衝撃を受けたのだろうと思う。
そのほか、蕪村生地の対岸で暮らした少年時代での記憶は、じつによく「たこ焼き」を食べたなあ、ということ。コンクリートの塀で囲まれた社宅の西側に出入り口があり、そこからすぐのところにたこ焼き屋があった。店内に食べるスペースはなくテイクアウト専門である。5個10円ぐらいだったか。小さく切った新聞紙の上に乗せて渡された。がまんできずに家に帰るまでに食べてしまうのが常だった。このたこ焼き店はどこにあったか。50年以上の懸隔はあるが、地図を記憶でたどると現在「本家かまどや」という弁当チェーン店の「長柄店」のある角地がそうだった気がしてきた。一度、確かめに訪れたい。
とにかく、大川を挟んで隣接するエリアで与謝蕪村が幼少期を送ったこと。それが蕪村の名を私に近しくさせる。蕪村を読もう。安東次男、藤田真一、大谷晃一の蕪村についての著作をとりあえず手元へ引き寄せる。自分から蕪村に近づいていくのだ。
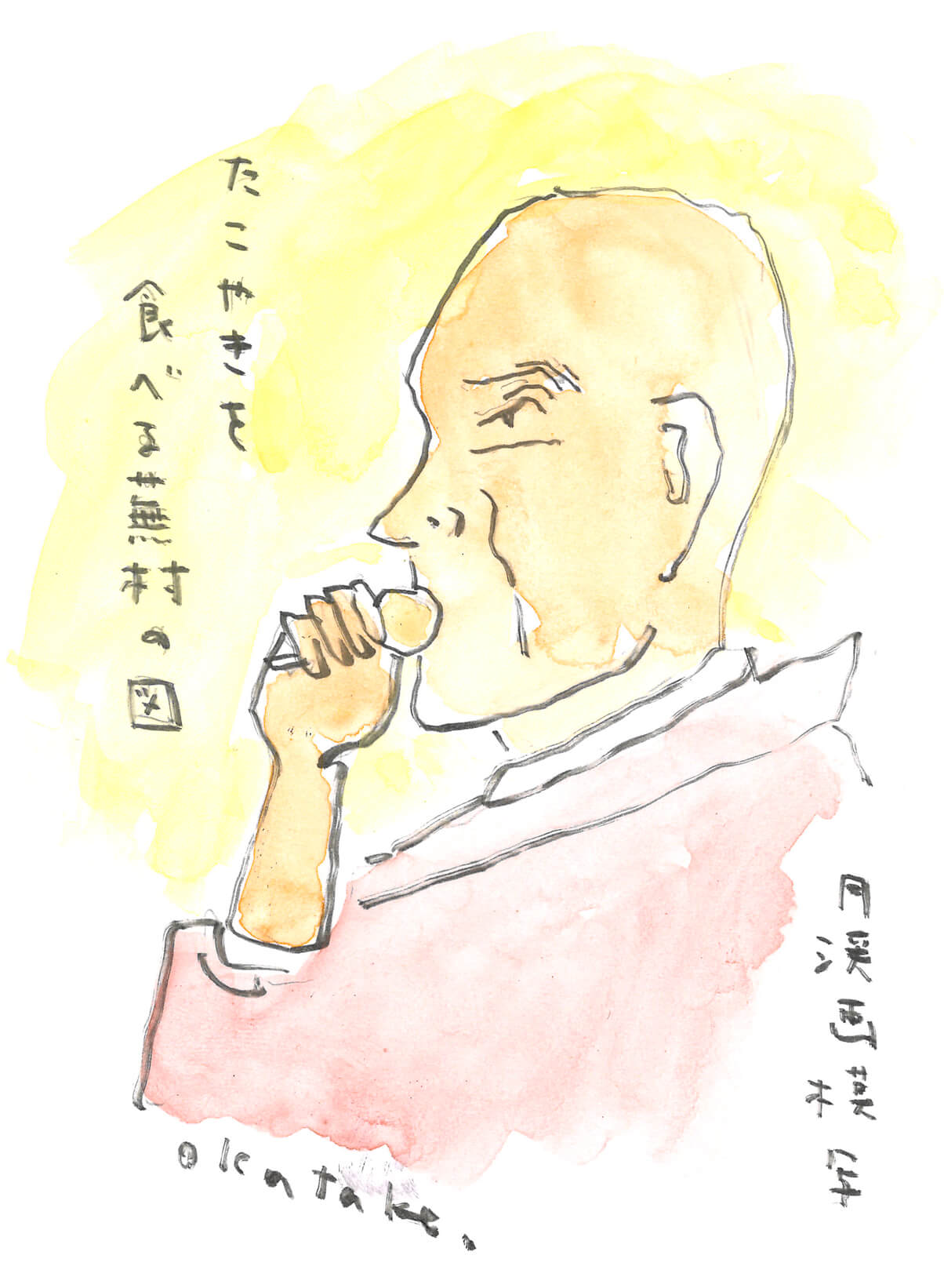
喫煙可の喫茶店「リオ」
 国分寺駅北口では、「ジョルジュサンク」とともに私が喫煙するために立ち寄る喫茶店がもう一軒あって、それが「リオ(RIO)」である。北口は平成の終わりごろから大規模な駅前開発が進み、駅直結のツインタワーと駅前ロータローの整備で風景がまったく変わってしまった。この10年ほど、国分寺を離れて暮らしてきた人が、今戻ったらあまりの変貌ぶりに驚くだろうと思う。
国分寺駅北口では、「ジョルジュサンク」とともに私が喫煙するために立ち寄る喫茶店がもう一軒あって、それが「リオ(RIO)」である。北口は平成の終わりごろから大規模な駅前開発が進み、駅直結のツインタワーと駅前ロータローの整備で風景がまったく変わってしまった。この10年ほど、国分寺を離れて暮らしてきた人が、今戻ったらあまりの変貌ぶりに驚くだろうと思う。それでも新風が吹くのは駅前半径150メートルぐらいで、少し離れるとまだまだ旧市街の風景が残っている。今回紹介する「リオ」もその一つ。「西友」のある駅前の商店街を東へずっと進んでいくと、駅近く周辺の店はほとんど装替えになったが、奥へ進むと昔ながらの店がまだ残っている。路地を入った名曲喫茶「でんえん」はその代表。路地へ入らず、そのまま歩くと正面に「ビジネスホテル 千成」の看板が見える。かなり老朽化したビルで、一階が飲食店街になっている。しかし、いつも人の気配はない。
いつも気になっていて廃業したかと検索したら、現役で営業中だった。失礼しました。なぜこんな場所にビジネスホテルがあるのだろう。駅の至近にメッツホテルがある。「千成」は少し離れていて目立たない。そうか、と気づいたのは、国分寺には東京経済大学をはじめ、東京学芸大学といくつか大学がある。大学入試のシーズンになれば、地方の受験生たちの宿泊需要があるかもしれない。隣の町である国立にも一橋大学があり、こちらは駅周辺に私の知る限り恰好のホテルはなく、立川、あるいは国分寺に流れるのかもしれない。
今回、初めて知ったが、「千成」は朝食付きの宿泊プランが取られていて、その朝食を供するのがすぐ近くの「リオ」であった。1977年の開業と店頭に出された看板でわかる。かなり年季の入った店舗だが、店内は掃除が行き届き清潔。奥にカウンター、ほかテーブル席が6つぐらいある。テーブルにはすでに灰皿がおかれていて、ランチタイムを避ければ満席ということもない。コーヒーも一杯ずつ淹れてくれて申し分ない。

ここで30分くらい、タバコに火をつけ、たいていは「七七舎」という古本屋で買った本を広げるのが常である。奥のカウンター前の席は、すぐ目の前に大型テレビがあり、少し音がうるさい。ふだん見ない春の高校野球やNHKの「のど自慢」も音だけ、あるいはちらりと画面を眺めた。おそらく「のど自慢」は少しだけだが初めて聞いた(見た)。そこで分かったのは、歌唱力のトップクラスのみが選抜されるわけではないらしい、ということ。鐘一つレベルの、標準あるいはやや劣るような人も舞台に立つ。そうか、ただ歌のうまい人ばかり並べて競わせても、番組としては単調で面白くない。むしろ人柄というか、キャラクターとして愉快な人も混ぜて出場者が決まるようなのだ。長寿番組の秘訣はそこにありそうだ。
しばらく音のみぼんやり聞いていて、そんなことを考えていたら、いきなりハイレベルの女性が登場してきた。「これはうまいわ、鐘三つだわ、プロになれるわ」と瞬時に思い画面を見たら、歌手の坂本冬美であった。毎回、プロの歌手がゲストで呼ばれるのだが、この回は彼女だったのである。「プロになれるわ」なんて思ったことを恥じるとともに、プロと素人の越えられぬ壁を見た。
カラオケの普及で一般人の歌唱力は飛躍的に底上げされたが、単に歌がうまいというだけではプロにはなれない。うまい人はたくさんいるのだ。そこにプラス、物語を盛り込める別の力が備わっていないといけない。歌自慢の素人たちを前に、軽々と歌い上げる坂本冬美を見て、そんなこと(あたりまえのこと)を思った。
(写真とイラストは全て筆者撮影、作)
『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著
書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。
書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。
┃この記事を書いた人
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。