太台本屋tai-tai books:黄碧君(エリー)さん、三浦裕子さんインタビュー
台湾文学の誘い(後半)
対話:倉本さおり、長瀬海
『歩道橋の魔術師』が広く読まれた結果、台湾文学にも改めて注目が集まりました。日本でも人気作家となった呉明益はその後も多くの翻訳が刊行され、ほかにも、徐嘉澤『次の夜明けに』(三須祐介訳、書肆侃侃房、2020年)、紀蔚然『台北プライベートアイ』(舩山むつみ訳、文藝春秋、2021年)、そして日本人プロレスラーも登場する林育徳『リングサイド』(三浦裕子訳、小学館、2021年)など、次々と翻訳がなされています。後半では、呉明益をはじめとした台湾文学の魅力について、また翻訳された各作品の魅力にについて、お話しいただきました。呉明益とは、はたして何者か?
── 私たちは『歩道橋の魔術師』で初めて呉明益という作家を知ることになったんですが、当時の衝撃は今でも忘れられません。時代の風景や、そこに幾重にも折り畳まれた哀愁が驚くほど鮮明に表現されていて……。非常にこまやかな観察眼を持っている作家だと思うんですが、同時に途方もない視野の広さもまた感じさせるというか。呉明益は台湾の文壇でどのような存在なんですか?

呉明益『歩道橋の魔術師』(天野健太郎訳、白水社、2015年)
エリー そうですね。呉さんはいまの台湾において、代表的な人気作家と言ってもいいです。彼の作品には台湾ならではの要素が随所に感じられますが、同時に世界にも通じる、国境を超えるものだと思います。彼は初期のころは、台湾の自然と生態を繊細な目で観察して、文学的に表現したエッセイを発表していました。それらの作品は、それまで台湾で書かれた自然に関する書物とは一線を画する、台湾ネイチャーライティングの新境地を拓いたということで、高く評価された。そういう視点を持って書かれた呉さんの小説は、台湾読者に、台湾にもこんなに豊かな世界があるんだって気づかせてくれるようなものばかりです。
一方で、台湾の歴史を掘り起こすことにも長けていて、社会のあちこちに刻まれている戦争などの記憶を物語にすることで、台湾という土壌に根ざしているもの、心のなかに埋もれていたものを文章のなかに映し出すことができるんですね。『歩道橋の魔術師』では中華商場という社会の記憶を描いたわけですが、『自転車泥棒』では現在と日本の台湾統治時代といった過去の記憶が見事に絡まり合って表現されている。彼は自分の部屋に閉じこもって作品を書くタイプじゃなくて、自分の田んぼを自分で耕したりしていて、自然のなかで物語を編む小説家でもあります。

呉明益『自転車泥棒』(天野健太郎訳、文藝春秋、2018年)
── 呉明益は土地の記憶と郷愁を象った物語で、まず日本の読者の心を掴みました。2021年には日本では三作品、続けて翻訳されて話題となりましたね。『眠りの航路』(倉本知明訳、白水社)は『自転車泥棒』の前日譚のような物語。それから、近未来の台湾と神話的世界を絡ませながら、壮大なスケールで独自の環境思想を紡ぎあげた『複眼人』(小栗山智訳、KADOKAWA)と、動物や自然と共生することとは何かを深く静かに問い、そこで生きる人間の姿を微に入り細を穿ちながら捉えた6つの物語が収録されている『雨の島』(及川茜訳、河出書房新社)。この『複眼人』と『雨の島』は自然と人間の普遍的な関わりを主題にしている点で共通しています。
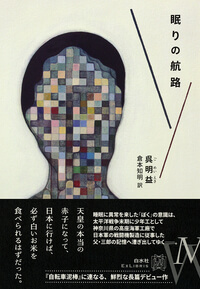
呉明益『眠りの航路』(倉本知明訳、白水社、2021年)

呉明益『複眼人』(小栗山智訳、KADOKAWA、2021年)

呉明益『雨の島』(及川茜訳、河出書房、2021年)
エリー 『眠りの航路』は眠りや夢をモチーフとしながら、主人公の意識が少年時代に日本の海軍工廠で働いていた父の記憶と繋がっていく物語で、言ってみれば、ノスタルジー路線です。でも、呉さんの他の作品と緩やかに繋がっていく。呉さんの長編デビュー作ですが、その後の作品とのテーマの連続性や、その原型のようなものが含まれています。
三浦 私、個人的には『雨の島』は呉さんの作品のなかでも最高傑作なんじゃないかなって思ってて。6つの作品、どれもそれぞれ映画一本撮れるくらいの密度になっているんですよね。こんな濃い物語が6つも揃ってて、1冊の本として重みがすごい。
── ちなみに呉さんは大学でも創作について教えていらっしゃいますね。三浦さんが初めて翻訳を手掛けられた『リングサイド』(小学館)の著者、林育徳も呉明益の元学生だったとか。
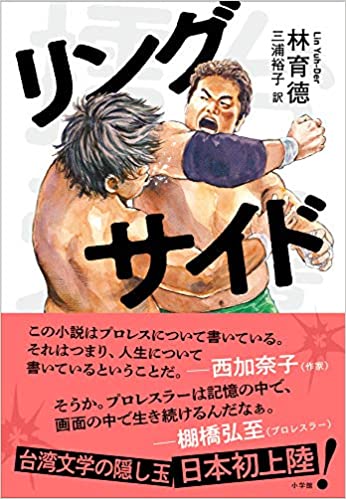
林育徳『リングサイド』(三浦裕子訳、小学館、2021年)
エリー あるいは、最近読んだ小説の話、とかね。
三浦 これは『リングサイド』の原書の前書きに書いてあるんですが、呉さんは指導をするときに、日常のなかで「小説感」のある物事に出逢ったら、それを収集しなさいって教えているらしいんです。例えば、ニュース番組で見聞きした事件だったり、資料で読んだりしたもののなかから「小説感」のあるものを見つける。でも、「小説感」って言われても学生からしたらよくわかんないじゃないですか。そこでまずは呉さんが最近見つけた「小説感」のあるものについてのエピソードを披露する。学生はそれを参考に自分が「小説感」があると感じたものを集めて、発表するってことをしているみたいです。
── やばい。「小説感」のあるものを集めて発表する授業……受けたい。
三浦 でしょ(笑)。林さんはプロレスをテーマに小説を書こうと思ってたから、プロレスに関する「小説感」のあるエピソードを発表していたら、いくつか報告したところで呉さんに「これで君の小説は書き始められるね」って言われて、そこから書き始めたらしい。
── もともとプロレスに関心のある方なんですか?
三浦 そうですね。林さんは東華大学のある花蓮という台湾東部の小さな街の出身なんですね。十八歳までずっとそこで育ったので、本人としてはそこから出たくて仕方なかった。田舎だし、人間関係も濃いし、とにかく外の世界に憧れてた、と言います。それで大学に進学して街を出るんですが、そこは想像と違っていた。それで鬱々と、人生これでいいのだろうか、念願だった外の世界に出てこられたのに、イメージ通りじゃなかった……と悩んでしまった。そんな折に、深夜テレビを見ていたらプロレスがやっていた。その瞬間、暗い喜びが胸に湧き上がってきたらしいんです。みんな寝静まったこんな真夜中に、台湾で超マイナーなプロレスがやっている。俺は、それを見ているんだ。負け犬の極みじゃないかって。そこから、人が注目していないものにのめり込んでいく、いわばオタク心に火がついた。
── まさにサブカルの基本ですね(笑)。
三浦 ええ。マイナーなものに惹かれるという人間の不思議な心理によって、プロレスを発見したんですね。
── 日本のプロレスをテーマとしたこの作品集は、タイムカプセルみたいだなって思います。このなかに、三沢光晴が好きなおばあちゃんが登場する「ばあちゃんのエメラルド」という作品がありますよね。作中の台湾では、まだ三沢が生きていた頃の試合がテレビで放映されている。語り手の孫は、インターネットを通じて三沢が既に死んでいるということに気づいてしまい、三沢に夢中になっているおばあちゃんを前にしてとても複雑な気持ちを抱く。伝えた方いいのだろうか、いや、言えない……って。だって、おばあちゃんは三沢の戦う姿にめちゃくちゃ猛ってるんですよ。輝かしい緑色のパンツでステージにあがる三沢に興奮するおばあちゃんがとても愛おしい。「ばあちゃんのエメラルド」ってタイトルを目にしただけで泣きそうになります(笑)。
エリー わかります。私もとても良いタイトルだと思います。
── もう亡くなっていて画面のなかにしかいない、三沢光晴というヒーローがフィクションとして駆動し続けてる感じが、ほんとうに素晴らしく描けていると思いました。三沢は、いつまでもおばあちゃんの人生にとってエネルギーになり続けてる。それって、プロレス好きの日本人の読者はもちろん共感できるし、プロレスに詳しくない人でも、なぜか不思議と懐かしい気持ちになる。そういう意味で、ここに描かれている人情は私たちもよく知っているものだって感じるんだと思います。
三浦 私はこの作品を最初読んだとき、とにかくリアルだなって思ったんです。キャラクターや一つひとつの会話から、今まで私が台湾で会ったり、街で見かけたりした人たちの姿が目に浮かぶというか。
── リアルっていうのはよくわかります。例えば、小さな村に住む主人公のお母さんが、お父さんに愛想を尽かして出て行ってしまった。お父さんはお父さんで、漁業でうまくいかなくて、犬に暴力をふるってたりする。つまり、ろくでなしなんですよね。そんな鬱屈した漁村で暮らしているなかで、主人公がマイナースポーツのプロレスという趣味を見つける。この感覚、すごいリアルだと思います。
三浦 『リングサイド』も『歩道橋の魔術師』も特別じゃない存在の、現代に生きる人々がいきいきと描かれている。『歩道橋の魔術師』がなぜ日本の人たちにこれほど喜んでもらえたかっていうと、やはり、それ以前に日本で翻訳されてきた台湾作品にはあまり感じられなかった、同時代性が多分に含まれているということも大きいのではないかと思います。初期の村上春樹のような物語のテイストを感じる部分があったり、「スター・ウォーズ」が登場したりする。読者は、自分がいるのと同じ時代に書かれた物語なんだと親しみが持てる。『リングサイド』も、私たちと同じ、普通の人の普通の日常がそこに描かれていて、だからこそ日本の読者も共感したり面白がったりしてくれたりするんじゃないか、そう考えたので、紹介しようと思いました。
── そうですね。『リングサイド』が私たち日本人にとってもリアルな物語だっていうのはとてもよくわかります。例えば、あの作品では、日本のプロレスが全ての短編のキーとなるんですが、けっして日本のプロレスの最前線を物語の背景に置いているわけじゃない。タイガー・マスクや獣神サンダー・ライガーといった、私たちにとってもどこか懐かしい存在を、その懐かしさそのままに物語のなかに登場させる。そこに漂うノスタルジー、作中の人びとの胸に去来する感情が日本人にとってとてもリアルだからこそ、共感できるんですね。『リングサイド』は台湾で生きる若者たちのアイデンティティをめぐる物語ですけど、そこにある戸惑いや哀愁は私たち日本人の物語とつながっている。広く日本の読者に読まれてほしい作品ですね。
三浦 ありがとうございます。お二人の熱が伝わってくる(笑)
── この小説、大好きなんです(笑)
(2021年4月8日、春陽堂書店にて収録、その後一部加筆修正を行った)
┃プロフィール
黄碧君(ふぁん・びじゅん、通称エリー)
文芸翻訳者。呉明益、紀蔚然、林育徳、リン・シャオペイなど台湾作家の日本におけるエージェントや、台湾の本まわりの情報発信などを行うユニット「太台本屋 tai-tai books」代表。台北出身、現在日本在住。中国語繁体字版訳書は、三浦しをん『舟を編む』、柴崎友香『春の庭』、乃南アサ『水曜日の凱歌』、川本三郎『いまむかし東京町歩き』、つげ義春『ねじ式』など70作品以上。 三浦裕子(みうら・ゆうこ)
仙台生まれ。版権コーディネーター、翻訳者、編集者、ライター。出版社で雑誌編集、国際版権業務に従事した後、太台本屋 tai-tai booksに参加。台湾や香港の「ふつうにおもしろい」作品を日本の出版社と読者に紹介する活動や、本まわり、映画まわりの翻訳や記事執筆などを行う。訳に林育徳『リングサイド』(小学館)、呉明益「沖積層になる」(短篇、河出書房新社『文芸』2022年春季号掲載)など。
千葉県出身。インタビュアー、ライター、書評家、桜美林大学非常勤講師。文芸誌、カルチャー誌にて書評、インタビュー記事を執筆。「週刊読書人」文芸時評担当(2019年)。「週刊金曜日」書評委員。翻訳にマイケル・エメリック「日本文学の発見」(『日本文学の翻訳と流通』所収、勉誠社)共著に『世界の中のポスト3.11』(新曜社)がある。
黄碧君(ふぁん・びじゅん、通称エリー)
文芸翻訳者。呉明益、紀蔚然、林育徳、リン・シャオペイなど台湾作家の日本におけるエージェントや、台湾の本まわりの情報発信などを行うユニット「太台本屋 tai-tai books」代表。台北出身、現在日本在住。中国語繁体字版訳書は、三浦しをん『舟を編む』、柴崎友香『春の庭』、乃南アサ『水曜日の凱歌』、川本三郎『いまむかし東京町歩き』、つげ義春『ねじ式』など70作品以上。 三浦裕子(みうら・ゆうこ)
仙台生まれ。版権コーディネーター、翻訳者、編集者、ライター。出版社で雑誌編集、国際版権業務に従事した後、太台本屋 tai-tai booksに参加。台湾や香港の「ふつうにおもしろい」作品を日本の出版社と読者に紹介する活動や、本まわり、映画まわりの翻訳や記事執筆などを行う。訳に林育徳『リングサイド』(小学館)、呉明益「沖積層になる」(短篇、河出書房新社『文芸』2022年春季号掲載)など。
倉本さおり(くらもと・さおり)
東京生まれ。書評家、法政大学兼任講師。共同通信文芸時評「デザインする文学」、週刊新潮「ベストセラー街道をゆく!」連載中のほか、文芸誌、週刊誌、新聞各紙で書評やコラムを中心に執筆。TBS「文化系トークラジオLife」サブパーソナリティ。共著に『世界の8大文学賞 受賞作から読み解く現代小説の今』(立東舎)、『韓国文学ガイドブック』(Pヴァイン)などがある。
千葉県出身。インタビュアー、ライター、書評家、桜美林大学非常勤講師。文芸誌、カルチャー誌にて書評、インタビュー記事を執筆。「週刊読書人」文芸時評担当(2019年)。「週刊金曜日」書評委員。翻訳にマイケル・エメリック「日本文学の発見」(『日本文学の翻訳と流通』所収、勉誠社)共著に『世界の中のポスト3.11』(新曜社)がある。






















