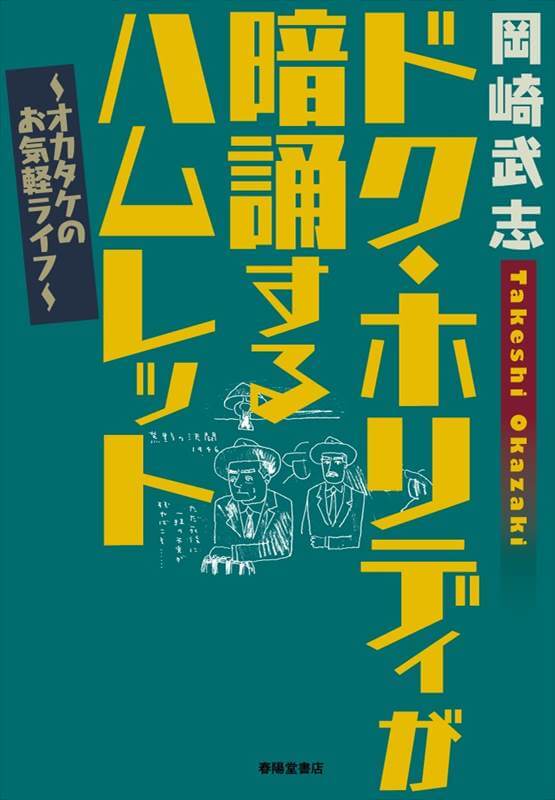【第70回】
もくじ
小川駅前「戸隠そば」
ときどき、自宅から自転車で行ける5キロ圏内の駅前にある立ち食いソバ店をチェックし、思いついたら訪れている。西武国分寺線「小川」駅前の「戸隠そば」(小平市小川西町)は気になりながら未踏であった。というのは、小川へ行くなら隣の市になるが同じ西武国分寺線沿いでわりあい近い町中華の名店「宝来屋」(東村山市美住町1丁目)でタンメンを食べたい。そんなにひんぱんに訪れる地域でもないので、「宝来屋」タンメンは逃したくない大きな魚だった(言い過ぎてないかな)。
今回はへそに力を溜め、「よし、戸隠そばへ行くぞ!」とワンテーマを固く誓ってペダルをこぎだした。すでに11月下旬で、もうすぐ街にクリスマスソングが流れ始める初冬であるが、穏やかな日差しに包まれ風はまだ冷たくない。どうかするとコートを脱ぎたいくらいだ。ところが、北海道では記録的な大雪だという。どうなっているのか。
いつも通るコースではなく、適当に方角を決めて知らない道を入っていったら、住宅街と畑に囲まれた袋小路に入ってしまい難渋する。しばらく自転車を停めて、あたりをうかがっていると、中年女性が乗る自転車が畑の脇にすっと姿を消していった。近づいてみると、自転車が1台ようやく通れるぐらいの細い道があった。下は土の道である。地図にはない。知る人ぞ知る、であろう。もと来た道を戻るしかないと思いかけたので助かった。
 なんとか袋小路を脱出し、自宅から20分ほどで「戸隠そば」へ到着。自転車はすぐ近くの地方銀行の駐輪場に停めさせてもらった。すいません。「戸隠そば」は小川駅から徒歩2分ぐらい。小川駅は西武拝島線も乗り入れる地上ホームの橋上駅。小さな駅前西口はT字になっていて、目の前の道を西に進むしかない。交番がすぐ角にある。なんだか、松本清張の小説で殺人を犯してしまうサラリーマンが夜に降り立ちそうな駅前だ。私は、こういう雰囲気、好きである。
なんとか袋小路を脱出し、自宅から20分ほどで「戸隠そば」へ到着。自転車はすぐ近くの地方銀行の駐輪場に停めさせてもらった。すいません。「戸隠そば」は小川駅から徒歩2分ぐらい。小川駅は西武拝島線も乗り入れる地上ホームの橋上駅。小さな駅前西口はT字になっていて、目の前の道を西に進むしかない。交番がすぐ角にある。なんだか、松本清張の小説で殺人を犯してしまうサラリーマンが夜に降り立ちそうな駅前だ。私は、こういう雰囲気、好きである。「戸隠そば」はすぐ目の前。かなりの年季が入った店舗だ。2階建てのようだが、3階建て分はある大きな緑の幌に「自動車教習所」の広告の文字が目立つ。広告看板のスペースらしい。手動の入口ドアを開くとすぐ鍵の手となるカウンターに椅子席。壁に書き文字のメニューが並んでいる。かけそば300円は、まあ普通だが、さまざまなご飯もののセットが500円からとこれはサービス価格。珍しいのは看板にも「そば・うどん・焼きそば」と「焼きそば」があるが、ほかにラーメンもあること。無敵の炭水化物王国である。
カウンターに座ろうとしたら、厨房のマスク老人店主が、なにかごしょごしょと言った。何と言ったのか不明だ。しかし「支持する政党は?」とか、「初恋の女性はいま何をしている?」などと聞くわけはない。事前の調査で「たぬきそば+カレー小セット」500円と注文は決めていたので、それを告げる。また、ごしょごしょと何か言ったが、こちらは「水」と聞こえたので、後ろに給水機があるから勝手にどうぞ、という意味のことを言ったと分かった。いやあ、大変です。
少し待って、カウンター上にカレー、そばの順に出された。黒く重い丼にたっぷりの汁に沈んでそば、ネギ、大きめの天かすが散らしてある。汁は真っ黒系ではなく赤みがかった好みのタイプ。カレーは「小」ということであったが、量は「並」で、小食の人ならこれで満腹になるだろう。黄色味がかったスパイスの効いたカレーは、小麦粉多めのドロリとしたタイプ。少し食べてみたが、これは新潟「万代バスセンター」の立ち食い店の名物カレーとそっくり。いやあ、うまいうまい。新潟まで行く必要はなくなった。

そばの麺はゆで麺の柔らかめ。汁が最後まで熱くて、量も多いのがうれしい。特筆すべきことはないにしても、立ち食いそばの必要条件を満たした合格品だ。「戸隠そば」と言えば、一般的にはそばの国・長野を代表するそばのことで、そばの甘皮を剥かずに挽く製法を使う。まさか、ここがそうだとは思わない。しかし何の文句もございません。おいしゅういただきました。
私の次にガテン系の男性の入ってきた時、ふたたび店主がごしょごしょ言った。それで分かったが、「セットの時は、先にセットと言ってね」と言っていたのだ。セットの時と、単品の場合とでは、調理の手順が違ってくるのか。常連ならすぐにわかること。以後、気をつけます。
小川駅は東側にブリヂストンの工場、西側に団地を持つ、それなりに人口の多い町だが、駅前は謙虚につつましい。「戸隠そば」のある商店街も昭和の匂いを色濃く残す。しかし現在、この西口一帯が再開発計画の途上にあると聞く。いずれ「戸隠そば」も姿を消すのであろうか。それまでにあと何回かは「セット」と先に告げて、小川駅周辺の空気を含め「戸隠そば」を味わいたい。
野口五郎と岩崎宏美
NHKの深夜音楽番組『SONGS』(11月18日放送)を見て、大いに感銘を受けた。大泉洋の司会。この回のゲストが野口五郎と岩崎宏美。昭和の歌謡曲全盛時代を、トップランナーとして駆け抜けてきた2人だ。私は1956年生まれの野口と、1958年生まれの岩崎に挟まれて、ちょうど真ん中の1957年生まれだから、2人にはデビュー以来、シンパシーがある。浮き沈みの激しいこと尋常ではない芸能界で、よくぞ40年以上(野口はデビュー50年)も生き残ってきたものだ。
しかし、このツーショットはなかなか見られなかったのではないか。2021年の今年、「好きだなんて言えなかった」という初のデュオ曲を発表、一緒に活動する機会を得ての出演で実現した。番組では過去の懐かしい映像を交えて、互いの芸能生活を振り返る。岩崎の野口との初対面の印象は悪く、岩崎が足を組んで座っていると、それを野口が注意したというのだ。デビューで言えば、野口は4年先輩だった。
2人は筒美京平の楽曲を多く歌ったという共通点がある。岩崎のデビュー曲「二重奏(デュエット)」も、野口の最初のヒット曲「青いリンゴ」もともに筒美京平作曲。音楽オタクらしい野口の発言。岩崎の「二重奏」を、一小節ごとに「タンタタンタタン」と歌詞なしのブレイクが入ることを指摘、それは筒美の狙いで、聞く側がそこで歌詞を頭の中に繰り返すサブミナル効果がある、なんて解説していた(聞き覚えで正確ではありませんよ)。
2人は歌以外のバラエティやドラマにも進出。野口が『カックラキン大放送‼』で「ゴロンボ刑事」に扮したコントをした映像が流される。野口は最初断ったが、プロデューサーに「明日はない」みたいな脅しを受け、ハイハイと受託したと笑わせる。「ずっこけ」を教わったのは加藤茶、というのも意外であった。歩いていて、途中で足を引っかけ「ずっこけ」るなどいくつかの加藤茶直伝のパターンをうれし気に披露していた。大泉も岩崎も大笑い。これは、芸能界らしい、いい空気だったなあ。
2人のもう一つの共通点。ミュージカル『レ・ミゼラブル』の日本版初演(1987年)で共演している。岩崎がファンテーヌ、野口がマリウス。ところが、緊張とプレッシャーで野口はつぶれそうになる。「大量に汗をかいていたのを覚えている」と岩崎。この初演に子役で出演していた山本耕史(のち「マリウス」役)が、インタビューに答える。野口の緊張ぶりを「舌が真っ白でした」と証言。よく覚えているものだと感心する。
野口は結局、一幕が終わったところで倒れ病院へ。「2幕目からマリウス役が別の人になっていた」と岩崎が当時を思い出す。そんな中でも2人はミュージカルを務めあげる。歌謡界では歌唱力のある実力派と目された2人だが、生の舞台、しかもミュージカルとなれば発声法から何から、違っていたようだ。このあたりの話には凄みがある。
時代は平成、令和と進み、歌謡界という言葉が有名無実となり、芸能界そのものも大きく変質した。私などは昭和が終わった段階で、日本の芸能界から気持ちは離れた。
そういえば、野口五郎の本をたしか持っているぞと気づき、芸能関連の本を並べた棚へ向かうとすぐ見つかった。こんなこと(探していた本がすぐ見つかる)は大変珍しい。『哀しみの終るときに』(立風書房・1975)というフォトエッセイで、この時代、アイドル歌手はこぞって同種の本を出していた。「あとがき」にはこうある。
「とっても恥ずかしい。未熟そのものの僕が、つまらないこと書いて、いったいこれはなんだなんていわれることがこわいのです。/僕は、ほんとうは、とっても臆病な男だから」(ソンナコトナイ、ゴロウハトッテモカッコイイ。ズットオウエンシテイルヨ)。
と、カッコ内のカタカタ文は、当時の女性ファンの気持ちを忖度し書いてみました。続けてこうも野口は書いている。
「五郎にはこんなバカなところがあったのかって思ってくださっていいのです」(ウウン、バカナンカジャナイ。ゴロウハステキ!)
ちょっとバカバカしくなってきましたが、わかるのは二十歳目前で人気歌手となった若者のとまどいや不安がよく表れていることだ。この弱音や自制は、同年代の女性ファンにとってたまらなく母性本能をかりたてただろうと思う。岐阜県美濃市で育った歌好きの少年が、歌手をめざして母親と上京。デビューまで、母が働いて息子の夢をサポートしたことも、この本でわかる。父と兄は実家に残って、佐藤(本名の姓)家が一丸となって息子の夢に賭けた。こんな塩っぱい苦労譚が、令和の今でもあるのだろうか。
15歳のとき、「博多みれん」でレコードデビュー。これは演歌だった。芸名・野口五郎は北アルプスの野口五郎岳から取った。その事情を知らない人は、野口五郎岳の名前を見て、「あら、歌手の野口五郎にちなんでつけられたのね」なんて思うかも。
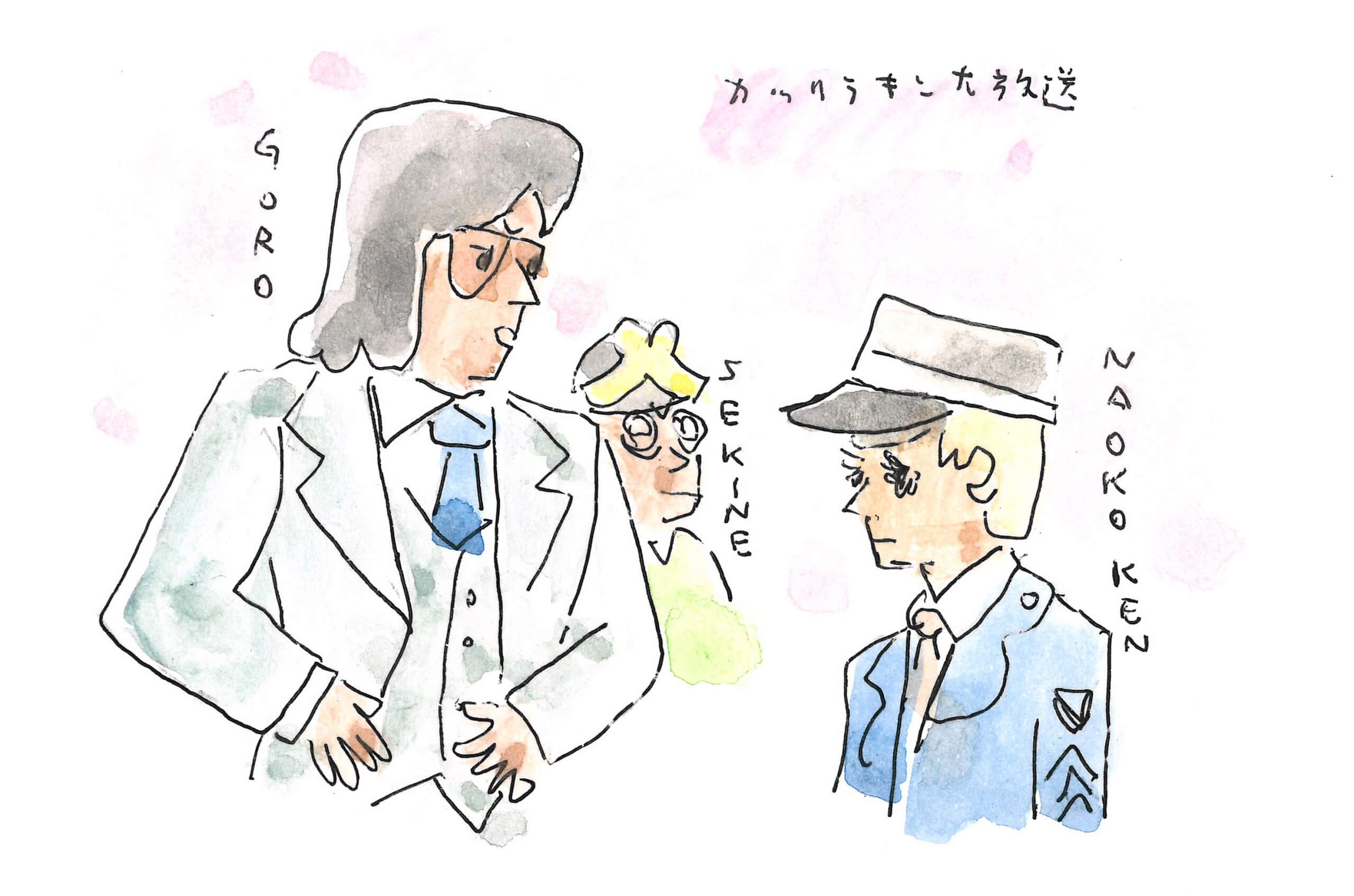
(写真とイラストは全て筆者撮影、作)
『ドク・ホリディが暗誦するハムレット オカタケのお気軽ライフ』(春陽堂書店)岡崎武志・著
書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。
書評家・古本ライターの岡崎武志さん新作エッセイ! 古本屋めぐりや散歩、古い映画の鑑賞、ライターの仕事……さまざまな出来事を通じて感じた書評家・古本ライターのオカタケさんの日々がエッセイになりました。
┃この記事を書いた人
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。Blog「はてなダイアリー」の「オカタケの日記」はほぼ毎日更新中。