
南條 竹則
第34回前編 ドリアンとオチャホイ金子光晴が南方で食べた物の話をもう少しさせてもらおう。
ビーフンと原料は違うけれど、同じヌードルの仲間で一つ気になるものが『西ひがし』に出て来る。
語り手の「僕」はシンガポールでシャオという男に裏通りの小屋へ案内され、シャオが勧める「シャム女」──じつは彼の女房なのだが──に会う。
暑いので、シャオは近所に行ってアエ・バト(氷水)を買って来る。それを飲んでいると、「オチャホイ」という麺を売りに来る呼声がした。
オチャホイは、支那人の呼びうりの声で、平打うどんを、麻油と唐辛子で炒めたもので、舌のちぎれるほどの辛さが、暑気払いに快かった。銀貨一枚出すと、女がじぶんで買いに行った。(『西ひがし』中公文庫 163-164頁)
シャオは女を囲い者にしろとさかんに勧めるが、「僕」はためらっている。 返事を待っているシャオのことを忘れて黙っているうちに、オチャホイを西洋皿にのせたシャムの女がかえってきた。
女は立居に余情があり、ながく傍にいるほどいとおしさが益してゆきそうであった。彼女は、買ってきたオチャホイを小皿三枚に盛りわけた。僕は、すすめられるがままに、そえてある不似合いな大きなフォークですくってそれを唇にもってゆくと、下唇のうすい皮膚が、ぴくぴくと痙攣した。唐辛子といっしょにカレーも、胡椒も多量にいれてあるらしかった。(同167-168頁)
辛くて美味そうな「平打うどん」を食べているうち、「僕」はだんだん女に欲情を催して来る。けれども、結局何事もなくてその場を脱した。女は立居に余情があり、ながく傍にいるほどいとおしさが益してゆきそうであった。彼女は、買ってきたオチャホイを小皿三枚に盛りわけた。僕は、すすめられるがままに、そえてある不似合いな大きなフォークですくってそれを唇にもってゆくと、下唇のうすい皮膚が、ぴくぴくと痙攣した。唐辛子といっしょにカレーも、胡椒も多量にいれてあるらしかった。(同167-168頁)
わたしにはこの麺の名称がちょっと気になる。
昔、河南省の開封の屋台で「燴麺」という麺を食べたからだ。平たいきしめん風のもので、羊のスープに入っていた。しかし、それを炒めたものもあって、「炒燴麺」という。
「オチャホイ」はこの「炒燴」から来たのではないかと思うが、果たして当たっているかどうか──。
南方へ行って、詩人はもちろん色々な果物を食べた。
昭和十六年の雑誌に発表した「蘭印紀行」という文章の中で、マンゴスチンやマンゴーなど、ジャバ(ジャワ)の果物を紹介している。
その中にドリアンも出て来るが、「棘の生えた鉄兜のようなドリヤン、これは、悪臭芬々としていますが、一度食べたら、味を忘れることの出来ないというものです。」(『マレーの感傷』中公文庫 182頁)という書きぶりは、何だか又聞きのようで、実際に味わった人の言葉らしくない。
彼の初めてのドリアン体験は、『西ひがし』に詳しく記してある。
この本の終わりの方で、新しい恋人ができてしまった「彼女」を、「僕」は先にシンガポールから日本へ帰す。出船の直前、珍しいものを食べさせてやろうと、滞在していたホテルの主人にドリアンを買いに行かせる。
ドリアンの臭いは、糞臭に似ていて、その臭いがあたりにしみこむと何日でもとれないというので、船にもってゆくことは、船の人が迷惑して、歓迎しないというが、慢性肥厚性鼻炎の僕は臭気だけはどんなに激しくても平気であるから、どんなものであるか、興味があった。主人は、十分ばかりでかえってきて、鋭い太針でよろった、フットボール位のドリアンを新聞紙のうえにひろげ、釘でも、金槌でも割れない表皮のつるに近い急所から、三つに割って、どんな意地にも代えられないといった様子で、一つずつにそれぞれ三つ四つずつある、その種子にむしゃぶりついた。それぞれの種子には、卵いろの果肉がからまりついていてそれが甘くもすっぱくもなく、キャモンベールに似た一種独特な味をもっていたが、その香が強烈らしいとわかっても、僕の鼻はあいかわらず無感動であった。彼女のほうを見ると、彼女は、その臭気に辟易しながら、できるだけうしろに身を反らしながら一粒の種子にからまる肉をなめてみて、
「味は皮肉な味で、うまくないというわけじゃないけれど……」
と言った。(『西ひがし』中公文庫 208-209頁)
「僕もそうおもうけれども、マライ人が家産をつぶし、女房をカタにしても、これが食べたいという話は、理解できない」と詩人が言うと、ホテルの主人が答えるには──「味は皮肉な味で、うまくないというわけじゃないけれど……」
と言った。(『西ひがし』中公文庫 208-209頁)
「いや、そんなことはありませんよ。私だって、暑い南洋になにがたのしみで辛抱しているかと言えば、これが忘れられないからです」
と、主人は、ドリアンにみこまれたように、僕らが一粒だけでもてあましたあとを、血相変えて、すっかり貪り食べた。あとで、五十叩き、百叩きの刑にあっても、ドリアンのあるところからうごくことはできないといった、あさましさも、恥も丸出しにした主人が種子をしゃぶり終るのを、呆気にとられ、声一つ立てず僕らはながめていた。(同209-210頁)
ドリアンに魅せられた人の話は、日本でも戦前から伝説のように語られている。この主人の描写は写実か、そういう話に基づくフィクションかわからないが、果物自体が正確に描かれているので説得力がある。噓だとすれば、巧い噓だ。と、主人は、ドリアンにみこまれたように、僕らが一粒だけでもてあましたあとを、血相変えて、すっかり貪り食べた。あとで、五十叩き、百叩きの刑にあっても、ドリアンのあるところからうごくことはできないといった、あさましさも、恥も丸出しにした主人が種子をしゃぶり終るのを、呆気にとられ、声一つ立てず僕らはながめていた。(同209-210頁)
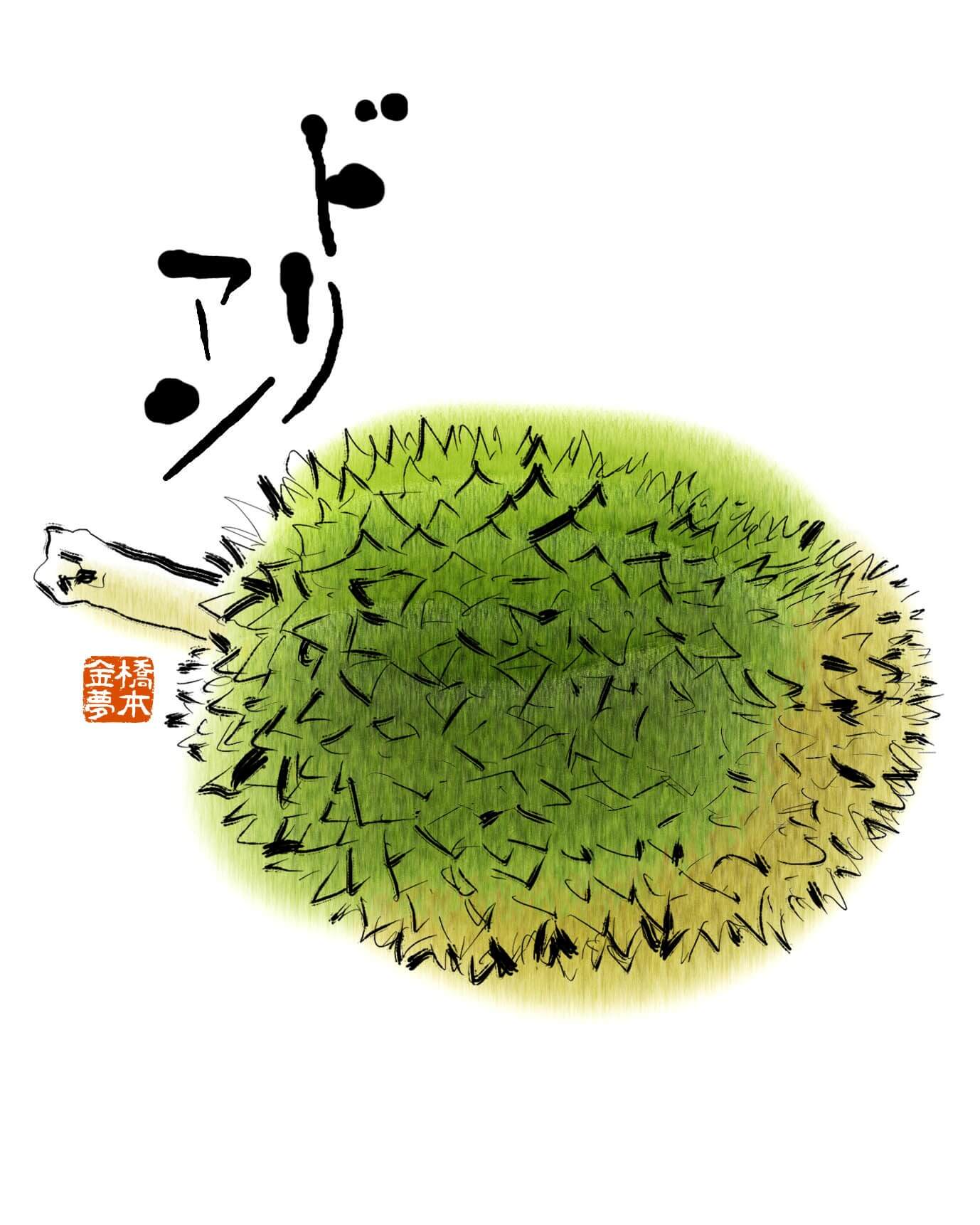
『酒と酒場の博物誌』(春陽堂書店)南條竹則・著
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
『銀座百点』(タウン誌)の人気連載「酒の博物誌」を書籍化!
酒の中に真理あり⁈ 古今東西親しまれてきたさまざまなお酒を飲みつくす著者による至高のエッセイ。
お酒を飲むも飲まざるも、読むとおなかがすく、何かじっくり飲みたくなる一書です!
┃この記事を書いた人
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に、小説『魔法探偵』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
























