
吉田 篤弘
第一話 塔のある街[其の一]ふたつの道が、直角もしくは、ほぼ直角に交わるところを十字路と云う。
ことさら冷たい風ではないとしても、北から吹きつのる風を、これすべて北風と云う。
大して仕事をしていないのに、毎月の給与を平然と受領する者を、給料泥棒と云う。
アスファルトの路上に、いたずら描きを施すために用いられる筆記用具を、臘石と云う。
この中に入ってはなりません、と侵入者を禍々しい鉄の刺で威嚇するものを、バラ線と云う。
一塁および二塁および三塁にいる走者を、ひとつ以上先の塁に走らせるために、あえて凡庸なフライを打つことを、犠牲フライと云う。
まず間違いなくほとんどそうであろうことを、十中八九と云う。
目を病んだ際に、疾患部を保護および湿布するために用いる留紐のついたあて布を、眼帯と云う。
他人と歩みを共にすることを厭い、独自な行動に終始する者を、一匹狼と云う。
そして、数々の難事件の謎を解き、その見事な推理が庶民に伝えられて名声を得た者を、名探偵と云う。
*
いまここに、灰白色の眼帯をつけた一人の男がいて、彼が一匹狼の名探偵であることを誰が知ろう。否──。
いやしくも、名探偵と呼ばれている以上、多くの者が知り得ているはず。
名探偵とは、これ「不吉な者」にほかならず、この世の難事件の多くは、名探偵さえ現れなければ、誰ひとり、事件の発生に気づかなかった。
彼の独眼は平穏無事な日々を揺るがす不吉な発見──すなわち、隠匿された事件の尻尾を見出すためにあり、バラ線にこびりついた一片の布きれから、連続殺人事件の予感をもあぶり出す。
彼はそうした自分に倦んでいた。
自らに着せられた「名探偵」という名の外套を脱ぎ捨て、単なる一市民として暮らしていきたい──そう望んでいた。
否──。
市民らと立話をしただけで、事件の輪郭が浮上してしまうことが多々あるゆえ、やはりここは、一匹狼となって生きていくべきか──。
悩ましい限りだが、いずれにしても、これより自分は「独眼の名探偵」にあらず、本来の名であるところの、除夜一郎に戻ろうと思い決めた。
「除夜」は無論のこと、「じょや」と読み、一市民の苗字としては稀なものだが、一匹狼に冠せられる二文字としては申し分ない。
一年の仕舞いに設けられた大晦日の夜を、除夜と云う。
ジョヤと片仮名で表記すれば、どこかしら異国の響きにも感じられる。
もとより彼の片方の目は、じつのところ碧眼で、生まれながらの日本人ではあるが、生まれながらのオッドアイである。
左右の眼の虹彩の色が異なることを、オッドアイ、もしくは虹彩異色症と云う。
彼が名探偵として世に認められ、誰もが知るところとなった難事件──のちに彼を主人公にして著された小説の題名を拝借すれば、『臘石の絵の女』と呼ばれる事件において、彼はその小説を書いた作者の企みによって、あらかじめ、オッドアイを封印されていた。
ダテ眼鏡ならぬ、ダテ眼帯によって──。
作者の云い分によると、
「除夜一郎という男は現実に存在する探偵であるのに、その奇異なる名前のみならず、オッドアイであるという事実が、作者による創作ではないかと疑われてしまう。よって、彼の左目に宿った青い海の色を灰白色の眼帯で覆い、読者の皆様には、その青い目をお見せすることなく、詳らかにしない。
そうすることで、連続活劇小説《除夜一郎の冒険》は、安易に二次元世界に閉じ込められることなく、われらが主人公は、現実の除夜氏そのものであると正しく理解されよう。
ただし、小説がそのような設定を選択した以上、現実の除夜氏にも、ダテ眼帯の着用をもとめるよりほかない。
はなはだ恐縮ではあるが、氏には生涯にわたって、この設定を受け入れていただくよう、お願い申し上げた次第である」
*
「つまり、おやすみをされるということでしょうか」時計屋の主人は二階からおりてきた除夜に気づき、トレードマークの黒い外套と灰白色の眼帯の不在を問い質した。
「時計屋の主人」とは、除夜がその二階に下宿している老舗時計商〈雲行時計店〉を営む雲行仰太郎氏のことを云う。
ちなみに、雲行はクモユキと読み、仰太郎はギョウタロウと読む。
下宿人が「除夜」で、大家が「雲行」とは、これまたいかにも作りごとめいているが、この世には間違いなく、こうしためぐり合わせがある。現にいま、ここにこうしてある。
ここ、というのは、〈雲行時計店〉が五十二年間、店を構えてきた〈塔ノ下〉と呼ばれる街を指す。
この街の只中には、ゆるやかに蛇行した目抜き通りがあり、地図にうつしとられたその姿は、まさしく蛇の如し。蛇の胴回りがいささか心細くなってきた尾のあたりに時計屋は位置している。
除夜はこの街にひどく馴染んでいた。この感慨は彼ひとりのものではなく、街の住人のことごとくが街と同化した彼を特別視しなかった。
常に眼帯をしている彼の容貌は、「現代の名探偵」と称せられ、すでに新聞等々で広く人の目に晒されている。したがって、街の人々もその顔を知らぬはずがない。
が、彼らにとって除夜という男は、時計屋の二階をねぐらにした、いささか風采の上がらない万年青年として映った。じつに、六件もの難事件を解決して世をにぎわした男という認識がない。その徹底した無関心が、除夜をこの街に留めていた。
「外套はともかく、夜中でもないのに眼帯を外されたのは初めて拝見しました」
修理中の懐中時計を作業台に置き、仰太郎は振り向いた姿勢のまま、除夜の左右の目を無遠慮に見くらべた。
「かえって、人目につくのではないですか──」
「そうでしょうか。とにかく、僕はしばらく事件というものから遠ざかって、ひとりの人間に戻りたいのです」
除夜はいさぎよく外套を脱いでしまったので、いつもならポケットに入れているであろう両手を持てあましていた。
「どうぞ、お好きなようにしたらいいでしょう」
仰太郎は眼鏡を掛けなおして作業に戻った。
「この街にいる限り、何も変わらないと思いますが」
「いえ、これは自分自身の意識の問題なので──」
「そうはおっしゃられても、世間が放っておかんでしょう。じきにまた事件が起きて、さっそく依頼がありますよ」
「いや、それならいいんです。依頼は断れますから。問題は自分が──」
問題は自分が事件を見つけてしまうケースである。
たとえば、以前にも事件から遠ざかりたいと思い立ち、行くあてもなく旅に出たことがあった。
このとき除夜は、のちに『諦念亭緑青夫人の沈黙』として知られる事件の舞台となったT市の古びた旅館に滞在したのだが、彼がその宿を自ら選んだわけではない。旅の途上で、たまたま彼を駅から乗せたタクシーの運転手が、「古い宿ですが、清潔で、料理もいいです」と勧めるのに従ったまでだ。しかし、投宿したその夜に、彼は宿屋の女将の言動に不穏な気配を読み取り、そればかりか、市内の各地で連続して起きている「謎の死」に彼女が関わっていると即座に見抜いた。
ニワトリが先か、卵が先か。
事件が発生するから探偵が登場するのか、それとも、探偵が現れるから事件に輪郭が与えられてしまうのか。
除夜には解けぬ謎などないはずだったが、この問いばかりは未だに解けていない。そのもどかしさが、名声とは裏腹に、彼を歪んだ罪悪感に追い込んでいた。
裏腹とは、背中と腹部の同居、表と裏がひとつになったさまを云う。
ニワトリと卵もまた同じようなもの。これすなわち、矛盾である。
「いずれにしましても──」
仰太郎は修理の手を休めることなく、やんわりと警告した。
「眼帯は外さない方がよいのではないですか」
✻
目抜き通りの蛇の尾にしがみついて夜の路上にあかりを落とすバー──その名も〈パンドラ〉のカウンターで、除夜は常連の皆から「角丸──カドマル」と呼ばれている電気修理屋と語らっていた。外套は脱いできたが、仰太郎の言に従って、眼帯はつけている。
「はたして、矛盾とは何でしょうか?」
除夜の問いに、角丸は「さぁ、知りません」と首を振る。
この人は、「知りません」が口癖で、ああ、自分もこうありたいと除夜はひそかに羨んでいる。
なぜ、探偵は──それも、とりわけ名探偵と呼ばれる者は、「知りません」では済まされないのか。ともすれば、強迫観念とでも云うべきものに責め立てられ、本来であれば、「知らない」「判らない」と答えるところを、無理にでも頭を働かせて、ああでもないこうでもないと、考察、推察の限りを尽くしてしまう。
探偵とは、人一倍、あることないことを云う者である。
人一倍、あることないことと戯れる時間と権利が与えられ、思いつく限りの御託を並べていれば、突出した推理の才などなくても、いずれ、真相を云い当ててしまうこともあるだろう。
「もしかして、そういうことなんでしょうか」
「そうですねぇ──」
角丸は飲みかけた真紅の酒が充たされたグラスをカウンターに戻した。
「あなたが本当に優れた探偵であるならば、誰かが殺される前に事件の謎を解くべきではないですか? 殺されてからでは、手遅れというものです」
カウンターの中でグラスを磨いていたマダムが顔を上げた。
「そうね、大事なのは人の命であって、優れた推理ではないもの」
除夜は言葉を失った。
それがおそらくは、自分を苛んできた矛盾への答えである。
誰かが殺される前に、その殺人事件の謎を解くこと──。
すっかり酔いが覚め、バーを出た彼は十字路に佇んで外套の襟をたぐり寄せようとした。
が、外套は脱いできたのだから、手はただ宙を泳ぐばかり。
ことさら冷たい風ではないとしても、北から吹きつのる風を、これすべて北風と云う。
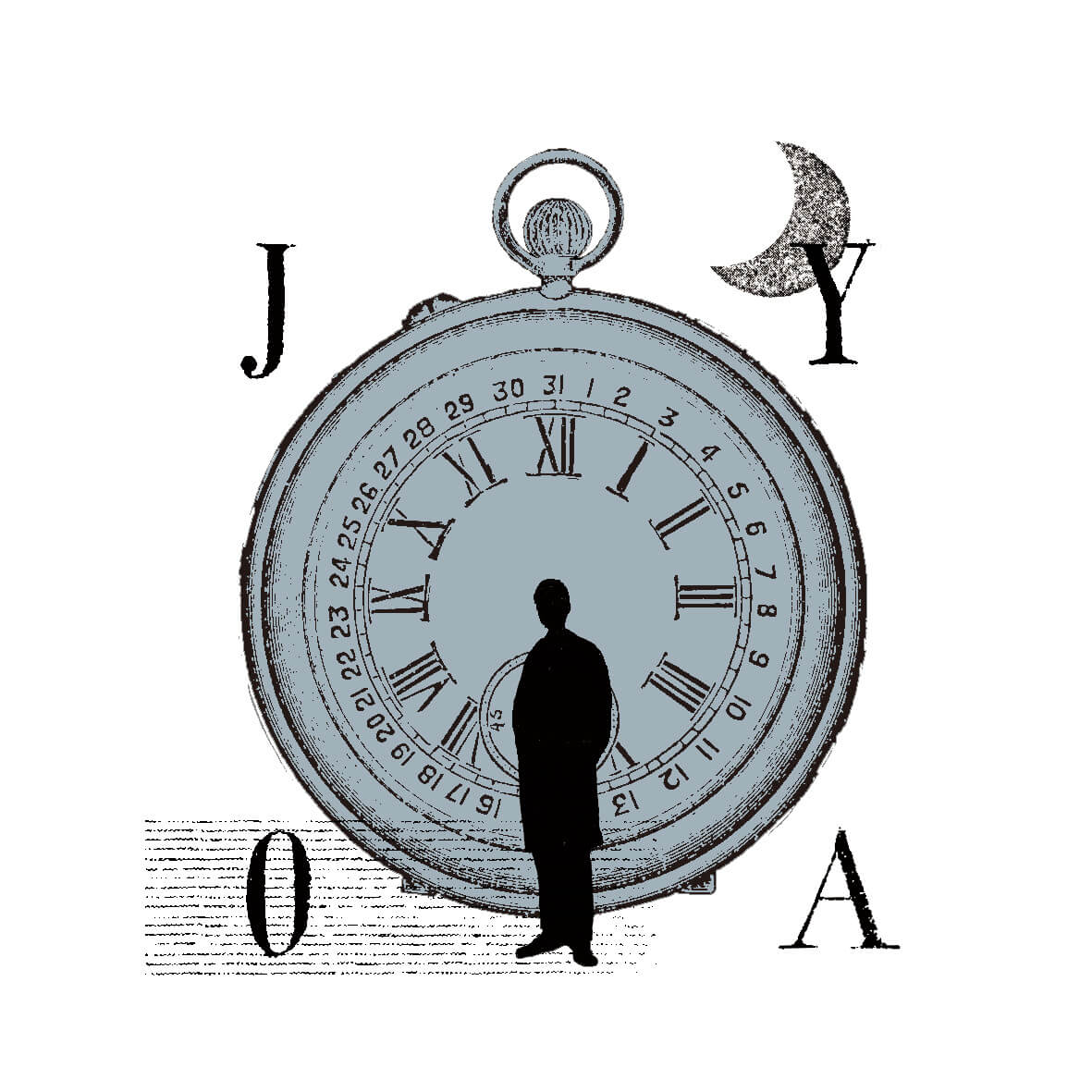
Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida
(「第一話 塔のある街[其の二]」へつづく)
┃著者紹介
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。






















