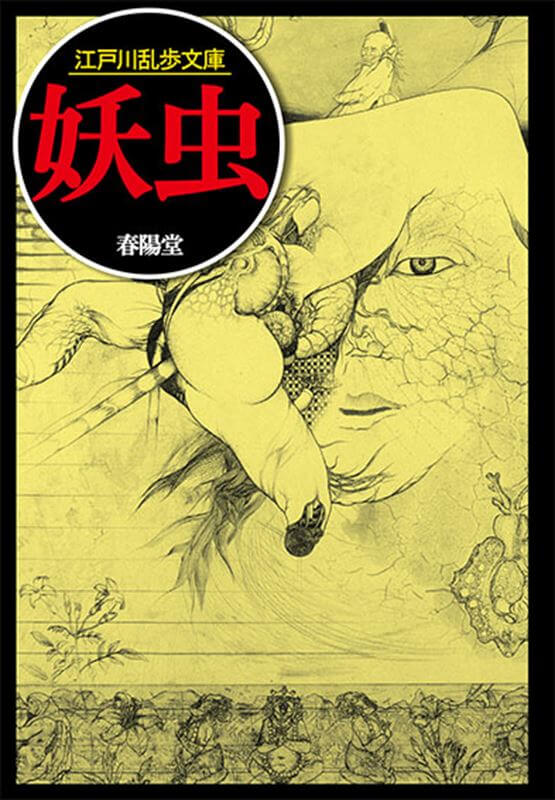名探偵は明智小五郎だけじゃない? 老探偵大活躍の『妖虫』

読唇術が暴く殺人予告。空き家で起こる女優の惨殺事件。現場に残されるサソリの紋章。次々と狙われる美女達を、老探偵・三笠竜介は、兇賊「赤いサソリ」の魔手から守れるのか──。
「妖虫」(1933・12~1934・10)は、1932年5月に「恐怖王」が完結してからほぼ休筆状態だった乱歩が、通俗探偵長編小説に復帰した作品である。劇場型の異常犯罪、幽霊屋敷、迷宮、地下室、見世物小屋……と、乱歩的要素が詰め込まれ、1年半以上のブランクを感じさせない快作となっている。この時期の乱歩が描く犯罪者は「怪人」性をエスカレートさせており、本作では人間大のサソリが大都会に出現する。桃源社版『江戸川乱歩全集』の「あとがき」で乱歩は「相変らずの荒唐無稽小説だが、真犯人とその動機はちょっと珍しい着想であった」と述べるが、フーダニット・ハウダニットを主眼とした推理劇というよりも、探偵と犯人グループの裏のかき合い・騙し合いが物語の推進力となる、クリフ・ハンガー型のスリラー活劇として楽しむべきだろう。
兇賊に戦いを挑むのは、「日本のシャーロック・ホームズ」と呼ばれる老探偵・三笠竜介である。「まるで猿に洋服を着せたような」冴えない外見は、既にダンディなイメージを確立していた明智小五郎とは対照的で、新たな探偵キャラクターの出現を期待させる。
ただしこの老探偵、「希代の名探偵」と持ち上げられているわりに、どうにも不手際が目立つ。自身が設計した地下室に閉じ込められたり、不意を突かれて後ろから刺されたり、肝心な時に入院していたりと、意外に頼りにならない。それどころか、一度は犯人グループを追い詰めておきながらも、逃亡された上に被害者をむざむざ殺されてしまう。被害者の救出よりも、芝居がかった大捕物を優先した結果の失態である。最終的には真犯人を暴くのだが、その過程で仕掛けた非情の罠は、後味が悪すぎる。結局、明智に代わる「名探偵」としての魅力を発揮できないまま、「妖虫」のみで退場となってしまったのは残念である。
余談だが、「妖虫」は氷川瓏の代筆で児童向けの「赤い妖虫」にリライトされており、三笠役が明智にスライドしている。そのため、明智が他作品に比べて迂闊な上に非情な人物に見えるという弊害が生じている。
三笠竜介の探偵としての特徴は、自らが考案した「探偵の七つ道具」(実際には20種類以上収納されている)をポケットサイズのケースに収容して常に携帯していることである。これはオースチン・フリーマンの創造した名探偵・ソーンダイク博士が携帯している、科学捜査用の器具が詰まった「緑の小箱」から着想を得たのかもしれない。惜しむらくは、三笠が「七つ道具」を活用するのが、地下室からの脱出シーンに留まることである。巧みな変装術も披露するが、明智の二番煎じの感は拭えない。むしろ秘密道具を駆使する科学者風の名探偵という要素を全面的に展開させていれば、明智とは違ったタイプのヒーローになり得たのではないか。
「妖虫」は探偵役がもう一人いる。それが相川守青年である。好奇心と冒険心が旺盛な「猟奇の徒」である彼は、妹・珠子から「探偵さん」というあだ名で呼ばれている。
探偵小説の猟奇的世界に耽溺する富裕層の御曹司が、偶然に殺人計画の密談を察知し、現場と思しき空き家の内部を節穴から覗くと、そこには酸鼻な殺人現場が……という導入部は、恐らく谷崎潤一郎の「白昼鬼語」(1918)の影響であろう。肌に指で文字を書く暗号の代わりに、「妖虫」では読唇術による会話の盗聴というアイディアを導入している。かくして女優・春川月子の惨殺現場に立ち会った相川の心情は、「ともかくも、大犯罪事件の渦中に身を投じたのだ。それが、彼の探偵本能に一種異様の満足を与えた」と描写される。「世の中にこんな面白い仕事があるもんか」と言い放つ三笠探偵と同様、相川にとって探偵行為はスリリングなゲーム(娯楽)なのである。しかし、兇賊は月子に続いて相川の妹・珠子、さらには恋人の桜井品子に魔手を伸ばす。当初は犯罪との関わりに興奮を感じていた相川青年の態度が、ラストでは変化する。「探偵小説は面白い、しかしそれが一とたび現実の事件となると、面白いどころではなかった。(中略)探偵小説なんて呪われてあれ! それで、彼は沢山の探偵本の蔵書を、一と纏めにして、屑屋に売り払ってしまったということである」。
つまり、「妖虫」とは「探偵さん」が探偵趣味から訣別する物語──アンチ「探偵」小説なのである(勿論、連載当初からそうした構想が乱歩の中にあったとも思えないが)。三笠や相川といった「探偵」役に人間的な魅力が乏しいのは、「探偵小説」に対する、乱歩の心理的な距離感に起因しているように思う。事実、乱歩は並行して連載していた「妖虫」「黒蜥蜴」「人間豹」の全てが完結した1935年5月から、再び休筆期間に入る。
半年ほどして休筆から復帰した乱歩は、1936年1月から『少年探偵団』シリーズ第1作「怪人20面相」の連載を開始している。シリーズは戦後も継続し、「妖虫」は換骨奪胎されて「鉄塔の怪人」(1954)に改作される。怪人20面相が巨大なサソリならぬカブト虫に扮して暗躍し、小林少年は「七つ道具」を駆使して、三笠の脱出劇と同じ役回りを演じている。人間大の怪虫が大暴れする荒唐無稽なイメージや、「七つ道具」というアイディアは、むしろジュブナイル向きだったのかもしれない。
こうした経緯を踏まえると、「妖虫」成立時期的にも内容的にも、成人向けの通俗探偵小説路線から少年向け探偵活劇路線への過渡的な作品と位置づけることが可能になる。
併録の「湖畔亭事件」(1926)は、主人公が覗き眼鏡で殺人を目撃してしまうという内容で、乱歩が初めて完結させた長編小説である。「覗き」というモチーフは「妖虫」の導入部とも共通する。最後に一応の真相は語られるが、幕切れに不穏な余韻が残る。
春陽文庫版1冊で、乱歩の初期の長編小説「湖畔亭事件」と、名人芸の域に入った頃の長編小説「妖虫」とを読み比べられるのは、なかなかに贅沢な読書体験となろう。
文・乾 英治郎(流通経済大学准教授)
┃この記事を書いた人
乾 英治郎(いぬい・えいじろう)
神奈川県生まれ。現在、流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)。「『新青年』研究会」会員、怪異怪談研究会会員、国際芥川龍之介学会理事。
著書に『評伝永井龍男─芥川・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017・3)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016・10)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015・4)等がある。
神奈川県生まれ。現在、流通経済大学准教授(専門は日本近現代文学)。「『新青年』研究会」会員、怪異怪談研究会会員、国際芥川龍之介学会理事。
著書に『評伝永井龍男─芥川・直木賞の育ての親』(青山ライフ出版、2017・3)、共著に 松本和也編『テクスト分析入門』(ひつじ書房、2016・10)、庄司達也編『芥川龍之介ハンドブック』(鼎書房、2015・4)等がある。