差別はなぜ繰り返されるのか
語り手・中村隆之
『野蛮の言説 差別と排除の精神史』は、世界中で差別の問題が取り上げられるいまだからこそ、読んでいただきたい1冊です。刊行から少し時間が経っていますが、いまの時代状況を鑑みて、著者の中村隆之さんにお話を聞いてきました。前半では、BLM=ブラック・ライヴズ・マターという言葉と運動の歴史・社会的背景について、コロナ禍で新たに生まれつつある差別について、そして本書に込めた思いを語っていただきました。
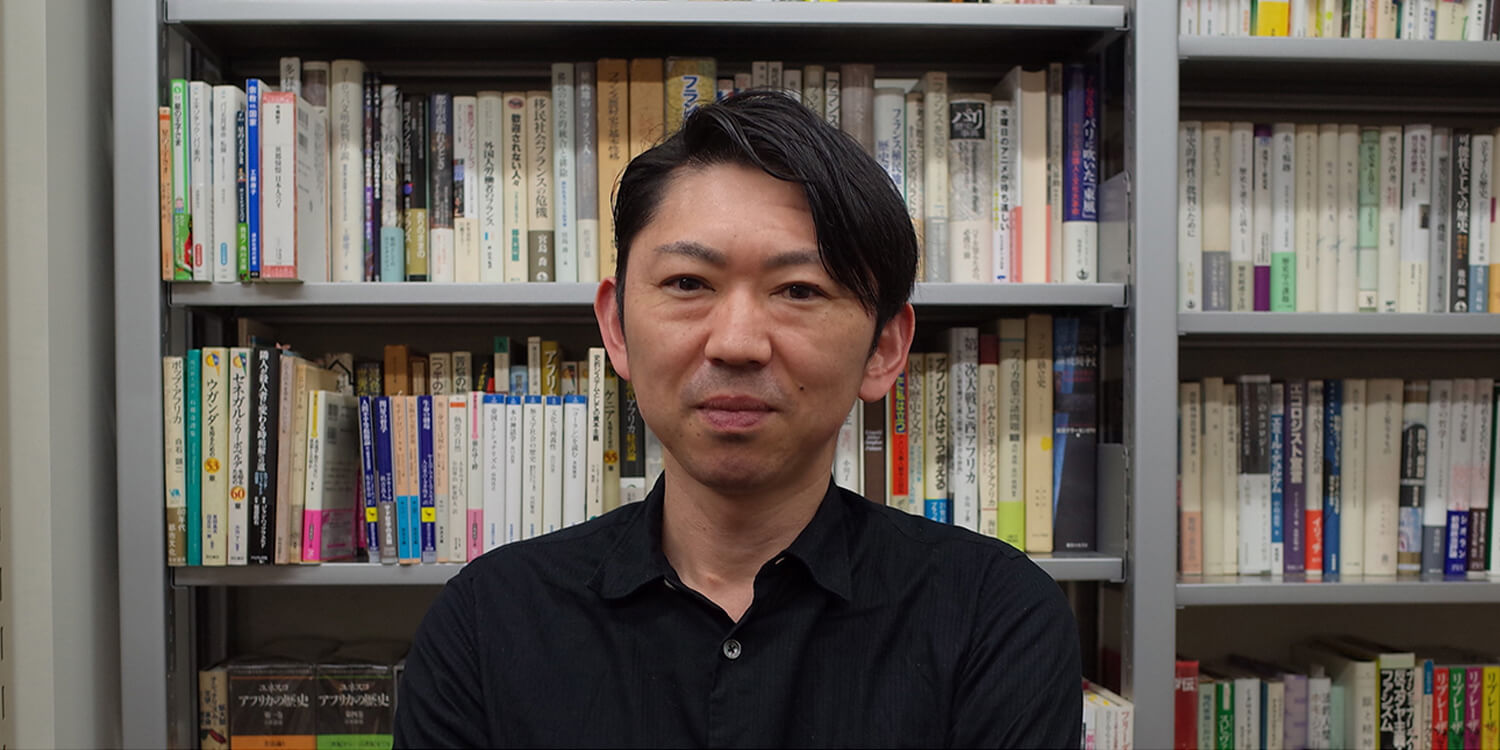
『野蛮の言説 差別と排除の精神史』(春陽堂書店)中村隆之・著
コロンブスの新大陸発見、ダーウィンの進化論、ナチ・ドイツによるホロコースト、そして現代における差別意識まで、古今東西の著作を紐解き、文明と野蛮の対立を生む人間の精神史を追う。ブレイディみかこさん推薦!
コロンブスの新大陸発見、ダーウィンの進化論、ナチ・ドイツによるホロコースト、そして現代における差別意識まで、古今東西の著作を紐解き、文明と野蛮の対立を生む人間の精神史を追う。ブレイディみかこさん推薦!
──本書刊行から数ヶ月が経ちましたが、図らずも、人種差別の問題がいままた表面化しています。
中村 本書は「野蛮」というテーマでまとめた一冊ですが、執筆にとりかかる前、このテーマに関連する本を数多く手に取りました。それらを読み進める中で、「人種」という問題がおのずと前景化した結果、この本で書いたことのほとんどは、「人種」と「差別」をめぐる議論となりました。「野蛮」という言葉から、ここまで話が展開するとは思ってもいませんでしたね。他者表象という観点から「野蛮」という言葉を考えた結果として、そこまで裾野を広げた本になったのだと思います。
ご存知のように、5月25日、ミネアポリスの警官による殺人の現場を撮った動画がSNSを通じて世界中に拡散し、大規模な抗議運動になっていきました。暴力をふるう警官のほうが「白人」で、押さえつけられ、息ができないで死んでしまったジョージ・フロイドさんのほうが「黒人」でした。この結果、アメリカでは「黒人」であるというだけで命が軽んじられる危険にあることが知れ渡り、BLM=ブラック・ライヴズ・マターという標語が改めて広がりました。
さらに、アメリカで今回の新型コロナウイルス感染症にかかり、命を落とす人々のうち、「黒人」の比率が高いことが報道されていましたね。感染リスクの高い労働現場にいることを余儀なくされたり、経済格差に結びついた居住区域の衛生環境、病院施設の問題などが考えられます。ブラック・ライヴズ・マターが切実さを帯びるのは、アメリカ社会における差別が構造的なものだからです。
ところで、気になっているのは、日本での報道のあり方です。この間、大手メディアは「黒人」や「人種」といった用語を平然と使っていますね。ですが、たとえば、目の前の人に向かって「黒人ですか?」と言うでしょうか。あるいは、だれかに「肌、黄色いね」とか、「肌の色で言うと、何人?」などと聞かれたら、どうですか。それこそが人種差別的な発言ではないかと思ってしまいます。
「黒人」や「白人」という言葉が差別的だから使うべきではない、と言いたいのではありません。そうではなく、使うならば、きちんとその言葉の意味や効果を考えて使ってほしい、ということです。アメリカでは自由人の「白人」が「黒人」を奴隷としてきた長年にわたる差別の歴史があることを絶えず念頭に置かなければ、思わぬ誤解を呼び起こしかねません。
いまの報道を見ると、まるで「人種(レイス)」は生物学的に存在しており、だから「黒人」という用語を使っているのだ、といわんばかりです。これは、差別主義者が古くから使ってきた論法です。差別をする側にとっては、差別することが大事ですから、「人種」という区別を作り出し、その指標をもって差別しようとします。これが「人種主義(レイシズム)」です。だとすれば、「人種主義」という意図が先にあり、そこから「人種」がつくられるのだ、と言い換えることができます。
もちろん、そんな意図を日本のメディアが有しているとは思えません。ようは無自覚なだけです。しかしそうした無自覚さが今回の人種主義化した物言いにも見られます。最近、NHKの番組によるステレオタイプ化した「黒人」表象が批判されました。番組の制作サイドが無自覚に共有していた価値観が表出したわけです。このことをきちんと批判し、そのうえで、「人種」をめぐる無自覚さを、メディア・言論にたずさわる人間が率先して自覚していく必要があるのだと思います。
2 知性の後退
──『野蛮の言説』の内容といまの現実が重なっているようにも思えます。
中村 『野蛮の言説』で書いたことと、いま日本で、世界で起こっていることがリンクするのは、まず「線引き」という問題です。相手と自分とのあいだに線を引いて区別する、というのは当たり前のことですが、この線引きした境界から、差別もはじまります。本書は主にはるか昔のことを論じていますが、こうした「線引き」自体はいまも昔も変わりません。
例えば、本書の第二部から第三部では、ダーウィニズムが差別思想にどのように貢献してしまったのかを考えています。優生思想が生まれたり、人種差別が強化されたり、など、進化論という科学的発見の裏面を考察していきました。
本書を執筆する過程で、あらためてダーウィンの著作を読み返してみて、つくづく凄い人物だと感じました。ダーウィン自身、かなりのバランス感覚を持った人で、自分の議論が差別にも利用されてしまうという危険性も自覚していたと思います。しかしながら、19世紀の科学の主体はヨーロッパ人にありました。そこには、知性を基準とした「世界の序列」が明確にありました。ダーウィン自身、『種の起源』では「進化論」を動植物に限定しようとしていましたが、のちに書いた『人間の由来』では、それを人間にまで拡張せざるを得ませんでした。
なぜ拡張しなければならなかったのか。まず、ダーウィンの進化論を支持する周囲からの期待がありました。進化論によれば、人間は動物から進化したはずですが、『種の起源』を発表した1859年の段階では、人類は多起源であり、生物は進化しないという学説も強固だったのです。『人間の由来』が出版されるのは1871年です。人間の進化にまで至る学説を提示することがダーウィンにおいてもようやく整った、ということです。
しかし、とても難しいのは、やはり線引きの問題です。というのもダーウィンの進化論を人間社会に応用して捉える社会進化論(社会ダーウィニズム)がここから登場するからです。社会ダーウィニズムは、人間の序列化をおこないます。未開で野蛮な人種が進化の過程でだんだんと知性を獲得していく、というストーリーのもとに捉えられます。もちろん19世紀におけるもっとも進化した人種は「白人」です。「黒人」は人間のなかでもきわめて下位の「人種」として表象されてきました。
もちろん「人種」によって人類が序列化されるなど馬鹿げています。だから、社会ダーウィニズムは、ユダヤ人大量虐殺という「野蛮」をなしえたナチズムへの反省から、負の知的遺産、似非科学として糾弾され、社会ダーウィニズムの思想は封印されたわけです。そして、この線引きによって切り離されたのが、ダーウィンの進化論でした。以後、社会ダーウィニズムは「進化論の誤用」だと理解されます。
ひるがえって現在、社会ダーウィニズムに近い言説や価値観に回帰しつつあります。現在、社会的な物事の判断基準が経済に置かれていることが、明確に見えるようになっています。その結果として、これまでの戦後社会が培ってきた、ある種の理想主義的な言葉が、ガラガラと崩れてきているようにも思えます。理想主義的な言葉が、多くの人に届かなくなっている。そこに思考の後退、知性の後退が見えてしまいます。
そのひとつの明確な兆候が、自民党広報がインターネットに投稿した漫画における、憲法改正のプロパガンダを目的としたダーウィンの進化論の参照ではないでしょうか。立ち止まってその論理を追えば、そこに詐術があるのは明白なのですが、そんな詐術すらも悪びれずに用い、SNSで拡散させるやり方を見過ごすわけにはいきません。識者がすかさず「進化論の誤用」を指摘しましたが、この広報漫画の背後にある一番の危険は、社会ダーウィニズム的な価値観を是とする、弱肉強食的な風潮であるように思います。
3 非常事態の言葉
──近年、「まっとうな言葉」がどんどん伝わらなくなっているように感じています。
中村 21世紀に入ってからの20年で、経済的な基盤がなければ、文化の言葉を発信することが難しいということが明らかになりました。日本の経済停滞、もしくは日本だけでなく先進諸国といわれる国々の経済停滞は、人々が本を読んだり、文化的なものに触れる機会さえも奪っている。日々の生活に追われて、時間的・金銭的・精神的余裕がなくなっています。そうなると、弱肉強食の時代に戻ってしまう。弱いものは切り捨ててしまえばいいといった、戦時下に展開されていたような考え方が、全般化している傾向があります。
新型コロナウイルスが広がる状況下で、それはより一層明確になっていますよね。いまの社会情勢は、まるで第二次世界大戦後に作られた国際秩序がなかったかのような社会になりつつある。新型コロナウイルスの問題が出てくる以前から、差別主義的な、排外主義的な主張や行為が目立つようになっていましたし、自国民を優先していくような価値観が強まっていることも、その表れです。みなが利己主義的にならざるを得ない状況に追い込まれてきています。
新型コロナウイルスの感染拡大の比喩として、戦争の語彙が使われています。「コロナとの闘い」という表現は、つまりコロナという「敵」がいて、そのコロナに打ち勝つということです。でも人間ではないコロナウイルスを「敵」と名指すのは、とても危険なことです。「コロナを保持している人間も敵である」という言説、ヘイトスピーチにもつながってしまうのです。新型コロナウイルスによって人が亡くなっていますので、それを「敵だ」と名指すことは説得力があるようにも思われているのかもしれませんが、そのウイルスを保有しているのは人間です。この戦争の比喩が定着してしまうと、結果として、罹患した疑いのある人間が差別/排除される可能性がでてきます。ここで、この本で考察していった「野蛮の言説」が発露しかねない。また、呼吸器が足りないなど医療の限界に達した時、命の選択も行われます。誰が生かされて、誰が生かされないか、という選択が迫られてしまう。その時、優生思想のような価値観が噴出しかねない。コロナ禍の現状は、そう展開していく可能性が大いにあります。
この状況下で、思考力も想像力も後退していて、目の前のことしか見えなくなっている傾向もありますね。インターネットから与えられる情報だけで想像を広げざるを得ない状況でもあって、さらにはその情報を精査することすら難しくなくなりつつある。これから社会全体がどうなっていくのか、まだ見えていません。いま私たちは、とても危機的な状況にあると思います。この状況というのは、『野蛮の言説』で取り上げた19世紀の状況とも重なって見えてきます。本書では、歴史を深く掘り下げながら、長いタイムスパンで「野蛮」という問題を取りあげましたが、過去を学ばないと、未来なんて見えないんです。そして、あらゆる思想は、すべて過去をどう解釈するのかによって成り立っている。そういう意味で、『野蛮の言説』は過去の歴史から、問題提起をしています。これを読むと、「人間って変わってないぞ」ということが伝わるとおもいます。
4 「歴史意識」を持つために
中村 僕はこの本の中で、自分のことを「アマチュア」と表現しました。ここで伝えたかったのは、エドワード・サイードが『知識人とは何か』でも語っているように、プロフェッショナルではなく、アマチュアである、愛好者であるということが、知識人として重要なんだということです。僕はこれがすごく好きな言葉なんです。だからアマチュア的に、越境的に、いろいろなものに興味関心を持つようにしています。
これは、教養教育の本でもあります。専門的なものを希釈してわかりやすくするのではなく、知的刺激を与えること、こんなに面白いものがあるんだということを提示することが、教養教育の重要な理念だと思っています。文学なら文学の専門家がとか、大文字の哲学を教えるとか、かっちりしている必要はなくて、いま自分たちがこうやって生きている世界を成り立たせているものは何なのかを考える、この社会の足元をみていく。それが大事だと思っています。
いま社会全体が近視眼的になっていて、過去を、歴史を軽視している気がします。みんな、どこか薄っぺらい現在を生きている気がするんです。回想する、過去を思い出す、想起するという行為は、人間にとってとても豊かな行為です。でも、思い起こすことがほとんどできないほどに、自分の人生が線にならずに、点のままになっている。そういう生き方をしているので、過去を振り返ることができない。いまはそういう時代なのかもしれません。
歴史にしても、それまでの学校教育で形成される歴史意識は、与えられるもの、教員主体のものになっています。そうではない、公定の教科書、文科省から認定された教科書からは得られないような「歴史意識」を、託したいという思いがあるんです。
だから、僕はこの本は、学生に読んでもらいたい。自分たちの考え方、信じている価値観がどんな過去を背景にしたものなのかを考えるきっかけに、この本がなればいいなと思っています。(後半へつづく)
┃この記事を書いた人
中村 隆之(なかむら・たかゆき)
早稲田大学准教授。カリブ海フランス語文学研究。著書に、『フランス語圏カリブ海文学小史』(風響社、2011年)、『カリブ-世界論』(人文書院、2013年)、『エドゥアール・グリッサン』(岩波書店、2016年)、訳書に、エメ・セゼール『ニグロとして生きる』(共訳、法政大学出版局、2011年)、エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(インスクリプト、2012年)『痕跡』(水声社、2016年)、ル・クレジオ『氷山へ』(水声社、2015年)、『ダヴィッド・ジョップ詩集』(編訳、夜光社、2019年)がある。
中村 隆之(なかむら・たかゆき)
早稲田大学准教授。カリブ海フランス語文学研究。著書に、『フランス語圏カリブ海文学小史』(風響社、2011年)、『カリブ-世界論』(人文書院、2013年)、『エドゥアール・グリッサン』(岩波書店、2016年)、訳書に、エメ・セゼール『ニグロとして生きる』(共訳、法政大学出版局、2011年)、エドゥアール・グリッサン『フォークナー、ミシシッピ』(インスクリプト、2012年)『痕跡』(水声社、2016年)、ル・クレジオ『氷山へ』(水声社、2015年)、『ダヴィッド・ジョップ詩集』(編訳、夜光社、2019年)がある。
























