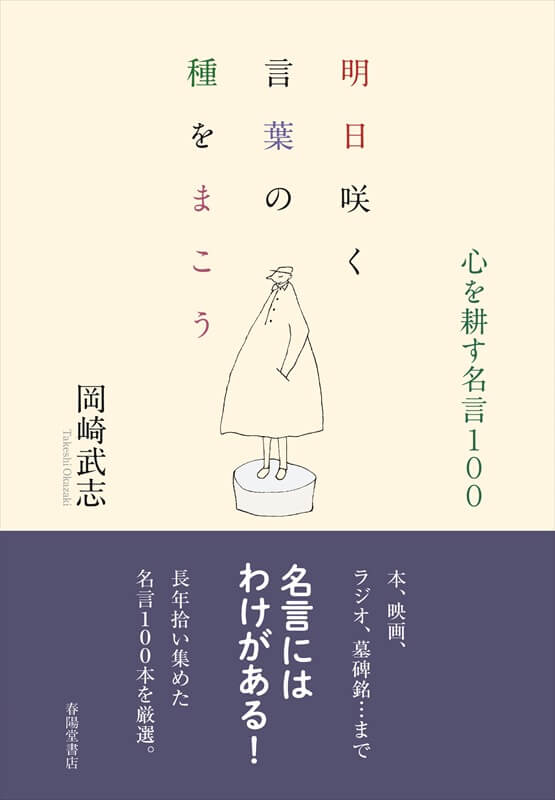【第49回】
日記の中の「1992年」
前々回に引きつづき、発見された古い日記の話を。
ひまだったのだろうか、1990年春の上京後、克明に日々のことを書き記している。1992年10月24日に「勝どきリクルートへ」とあるのは、小さな雑誌社を退職、ライターの仕事と並行して校正の派遣アルバイトをした時のこと。雑誌社で席を並べていた青年Oくんが私と一緒に退社後、校正の派遣会社に登録し、すでに始めていたのを紹介されたのだ。Oくん周辺のフリーター仲間とここで親しくなり、仕事帰りに一緒にお酒を飲んだりして一時期つるんでいた。彼らはおおむね20代で、すでに30代半ばとなる私が一番年上であった。みなおとなしい若者ばかりで、年長の関西人として、引き立てるように率先して声をかけバカ話をしている私を、「まるで寅さんみたいですね」と言われたりもした。
Oくんから紹介された必殺仕掛人の元締めみたいな女性がきりもりする校正会社で、我々は命を受けてあちこちへ出かけていく。そのうち多数の校正者を必要とする大口がリクルートの月刊海外旅行情報誌「エービーロード」だった。検索したら、その後、紙の雑誌からウェブに移行し、それも2021年3月いっぱいで全サービスが終了するようだ。電話帳みたいな厚さを分担し、「コンドミニアム海側〇〇万円」など、半角の数字が混じる細かい情報を、ただひたすらチェックする苦行であったが、単純作業でもあり、終わった解放感は格別であった。
リクルートの本社であろうか、勝鬨橋南詰に巨大なビルが建ち、そのワンフロアにある編集部まで数日、詰めて通うのだった。まだ都営大江戸線が開通する前で、最寄り駅は日比谷線「築地駅」。晴海通りから勝鬨橋(かつて開閉した)を川風に吹かれて歩き(トラックが通ると橋が揺れた)、リクルートビルを目指す。この光景は懐かしいなあ。
校正派遣会社に登録しているのは、我々のような20代30代のフリーターとおばさん連中だった。ひんぱんに仕事をしている人とは、方々の派遣先で再会し、休憩時などに口をきくようになる。和気あいあいとしたいい職場であった。10月24日に書き留めているのは「Tくん」のことで、先に別の職場でも一緒になった。休憩時間に話して、彼についていろいろなことを知る。会話を交わしたのはこの日が初めて。
「Tくん(日記では実名)は26歳、ギタリスト鈴木茂に似た風貌。京都出身。幼いころ両親を亡くし、祖父母に育てられたという。大学入学で上京、しかし大学へは行かず編集の仕事についた。たった一人で自然食品のPR雑誌を制作。2年半続けて先ごろ失職した。私の境遇と重なるところあり。親しみを持つ。異色は古楽器で中世ヨーロッパ音楽を演奏する楽団に所属していること。
最近の若者には珍しく、通好みの本をたくさん読んでいる。古本屋へもよく行くという。大正期に活躍し、その後消えた作家の本を探している。話が合うので熱が入る。彼『引っ込み思案で、人と話すのが苦手』というが、たしかに声が小さく、能弁とはいえないが、人を引き付ける魅力を持っており、年上の人と多くつきあっているというのが分かる。同世代の若者ではちょっと物足りないだろう。
『Tくん、君はいい男だなあ』と私が言うと、彼も『岡崎さんと話していると吸い込まれそうになる』などと言う。休憩所に一緒にいた若い女の子2人は、その表現に驚いたようであった」
T君とはその後、一緒に古本屋へ行ったり、我が家へ遊びに来たりしてしばらく交流があった。彼が演奏に参加した古楽器のライブへ出かけたりもしたがその後交流は途切れた。別に関係が悪くなったわけではなく、なんとなくそうなった。こうして日記を読み返し、記憶がよみがえった友人の一人である。今、どうしているだろうか。
『風船』の主人公は村上春樹
大佛次郎『風船』を読んだのは、川島雄三監督による同名映画(1956年)を見たから。どっちから話そうか。まずは原作の小説から。大佛次郎(ちなみに「おさらぎじろう」と読む)は本名・野尻清彦(1897~1973)。大佛は一高から東京帝国大学政治学科卒のエリートで、大衆文学の作家としては珍しく高学歴であった。
また「鞍馬天狗」シリーズから『赤穂浪士』、戦後の『帰郷』『旅路』そしてこの『風船』と新聞小説の分野でヒット作を書き(いずれも映画化)、『天皇の世紀』といった歴史ノンフィクションに手を染めるなど、幅広い活躍をした大作家であった。現在、質量ともに比肩すべき作家はいないと思われる。
さて『風船』の話。私が読んだ(再読であった)のは新潮社刊の「小説文庫」と呼ばれるビニール装、軽装小型本の1冊で、文庫と名乗りながら新書にほぼ近いサイズだ。「毎日新聞」連載をまとめたものでこれが元本。1955年刊で定価が160円というのは、当時公務員初任給が8700円だったことを考えると(現在その20倍として)3000円以上という感覚で、やや高く感じられる。書籍の値段が、ほかの諸物価に比して上がっていないとも言えるのだ。
時代は新聞連載時(1955年1月~9月)における「現在」。主人公のカメラ会社社長は妻と2人の子を持つ58歳男性で、その名は「村上春樹」。当時の人は別にその名を聞いて、特に反応することはなかったろうが、我々はちょっと驚きますね。ちなみに、あの「村上春樹」は1949年生まれだから、父親が長男誕生時に命名する時、『風船』の男の名が頭をよぎった可能性がある。村上春樹の父親は教師であった。今回の原稿の眼目はここにあり、もう終わってもいいのだが、それでは愛想がなさすぎる。映画の配役も合わせ登場人物紹介を。
村上(森雅之)はかつて若き日、日本画壇で注目された画家だったが筆を折って会社を興した。彼の師であり日本画の大家だった男の息子が都築正隆(二本柳寛)。酒場「ミノトオル」経営者であるが、正体の知れない戦後混乱期の産物だ。シャンソン歌手の三木原ミキ子(北原三枝)を愛人に持つ。村上には2人の子どもがいて、長男圭吉(三橋)達也)を社の重役に据えているがバーの女・久美子(新珠三千代)との関係をずるずる引きずっている。娘の珠子(芦川いづみ)は明朗な画学生だが、胸を病み、幼き日の小児麻痺により左腕が不自由である。原作を読み、映画を観返すと、これがいかに見事なキャスティングであるかがよくわかる。
大佛はこれらのコマを自由に動かし、敗戦後10年の痛手で荒廃した日本人の心を描く。特に圭吉はエゴの塊として恋人の久美子を冷たくあしらいながら、ミキ子と接近し、結果久美子を死に追いやる。戦争からの復員兵だろうか。病的と思わるニヒリストである。その冷めきった気持ちを父の村上は強く憤り、会社から放り出してしまう。圭吉がいる前で、ミキ子に正隆がこんなふうに言うシーンがある。
「戦後の人間の虚脱の時期は過ぎたがはずだが、続いて新しく、別の虚脱が始まろうとしている。風船だ。漂うところを知らずさ」
小説でも映画でも、正隆が経営する「ミノトオル」の天井に行き場を失った風船が一つ、ふらふらと天井を移動する場面を印象的に描いている。やがて風船は浮力を失くし、力なく落ちていくだろう。大佛は理屈っぽくなりすぎずに、大衆小説の形を借りて戦後日本の荒廃を「風船」になぞらえて読者に示す。きわめて知的な操作で、読後感はフランスの心理小説を読んだような気にさえなる。
村上もいわば行き場を失った「風船」のごとく心を空しくして、単独で若き日修行した京都の部屋を借り、再び筆を取ろうと決意する。彼の救いは娘の珠子だ。珠子は兄の恋人だった久美子と生前親しくなり心を開いていた。生きる道を決めた父の村上に珠子はこう告げる。
「(久美子は)良い人だったのよ。」(カッコ内引用者)
春樹は、うなずいて見せてから、笑って言った。
「珠子にかゝると、人間が、みんな、いゝひとなんだね。」
珠子も首を曲げて微笑した。
「多分、そうなの。けれど、花の咲く木や草とお話ししている方がいゝこともあるのよ。」
春樹は思いがけず娘の心に触れて、一言もなかった。
このような「木や草とお話している方がいゝ」などという、妖精のようなセリフを言えるのは芦川いづみしかいない。芦川は映画『陽のあたる坂道』でも足の悪い少女に扮し、殺伐とした家庭環境にあってひまわりのような存在だったことを、『風船』の珠子に重ねて思い出していた。
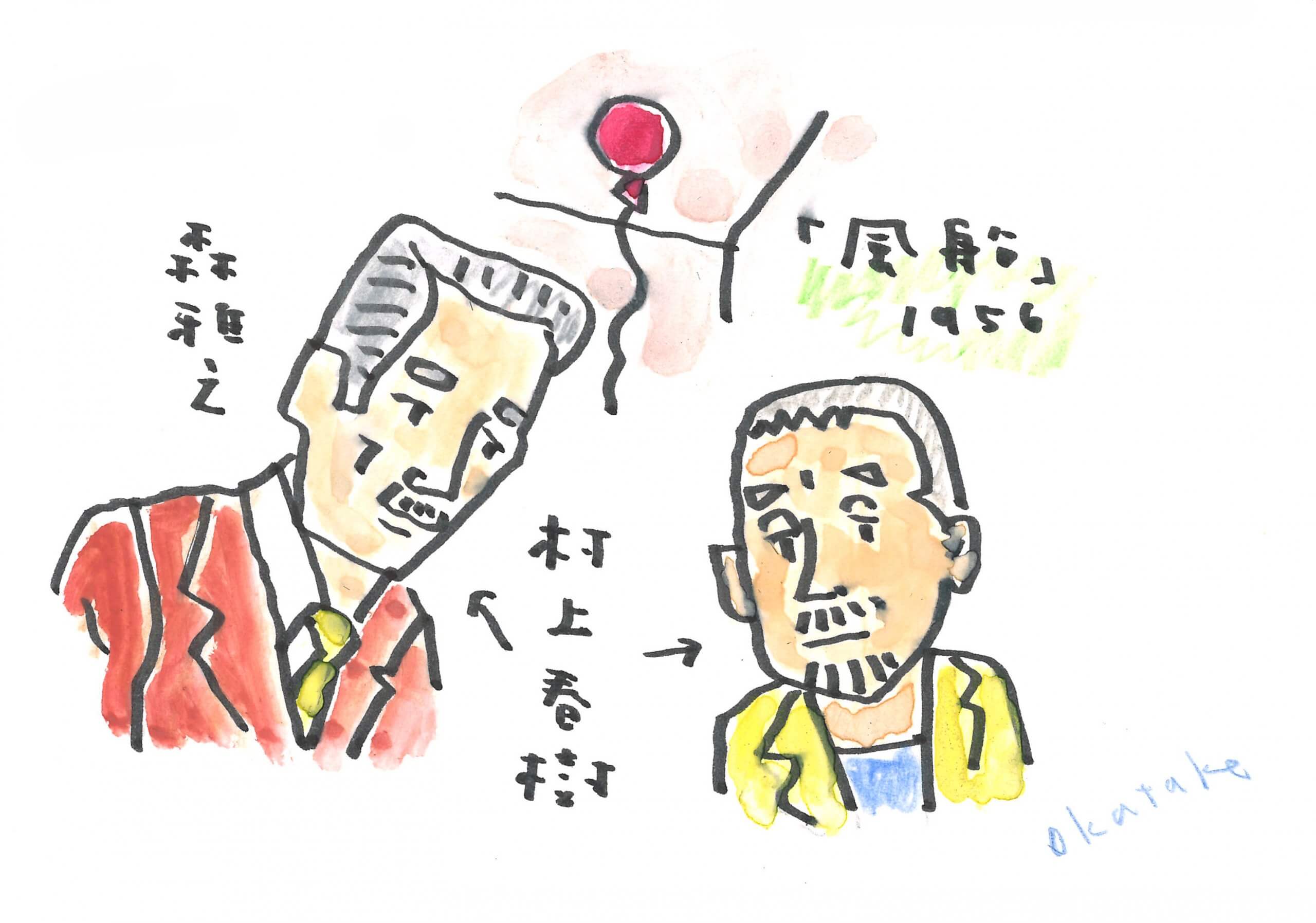
(写真とイラストは全て筆者撮影、作)
『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
┃この記事を書いた人
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。