
吉田 篤弘
第三話 カモフラージュ[其の二]時が移り、ミサキをアパートへ送り届けると、除夜はそのまま帰ることなく部屋にとどまっていた。その部屋で暮らしていた仰太郎の娘について、ミサキに話しておく必要があると思ったからだ。
「彼女の名前は菜緒さんといいました」
除夜は中庭に面した窓のカーテンを開け、庭の花々に午後の日差しが降り注いでいる様に目を細めた。
「亡くなられたんですよね」
ミサキはそう云って遮光眼鏡を外し、その眼鏡をかけていた菜緒に想いを寄せている風だった。
眼鏡を外して露わになった右の瞳は、庭の花々に匹敵するような青さをたたえている。除夜はその青さに見入り、しばし言葉を失ったが、
「菜緒さんとは、先ほどの霊安室で初めて対面したのです」
と、どうにか言葉を継いだ。
「まさか──」
と今度はミサキが絶句する。
「ええ」
と除夜は頷いた。
「彼女の遺体には、うなじの生え際に『E』と刻印されていました」
「E──ということは、二人目の犠牲者でしょうか」
「それで、いよいよ事件であると疑われ、いつものように僕は権田に呼び出されたのです。しかし、手を尽くしても何ら手がかりが見つからず、ほどなくして三人目が──」
「ほどなくして」とミサキは反復する。
「僕が仰太郎さんの時計屋の二階に寝泊まりするようになったのは、それからです」
そう云うと、除夜はそうすることが礼儀であるかのように自らの眼帯を外した。ふたつの青い瞳がお互いを確かめ、ふたつの黒い瞳が冷静に観察している。
「ミサキさんの右目と僕のこの左目が合わさると、一対の青い瞳になります。その瞳が見るものは、おそらく黒い瞳には見えないものでしょう」
「そうかもしれませんね」
ミサキは頷きながら、遮光眼鏡をかけた。
「でも、それはきっと幻のようなものでしょう」
ミサキは意識的に除夜の方を見ず、ライティングデスクのあたりを遮光眼鏡越しにぼんやりと眺めていた。
誰かがその机に向かって書きものをしている姿を見たような気がしたからである。
✻
それから数日の後、仰太郎に遣いを頼まれて除夜が塔にほど近い繁華街を歩いていると、突然、視界の端に見覚えのある顔がよぎった。それが、あの廊下ですれ違った貴島刑事であると脳裏で照合された途端、反射的にその背中を追っていた。
追跡し始めて気づいたのだが、貴島も誰かを追っているようで、誰かを追っている男を自分は追い、となると、自分も誰かに追われているのではないかと、何度も振り返りながら除夜は尾行し続けた。
やがて貴島が足をとめたので、その視線の先を見やると、得体の知れない二人の男が対峙しているのが窺えた。おそらく、その二人の内の一人が、「爆弾男」と呼ばれる輩に違いなく、もう一人は協力者もしくは共犯者であろうか──。
除夜の直観はそう読み取り、事態を見守っていると、二人はいくつかの言葉を交わして、一人が相手の上着のポケットに小さな紙きれを忍ばせるのが見てとれた。その一瞬を見逃さなかったのは、先だっての宝石店における一件で目が鍛えられたせいかもしれない。
無論、貴島刑事も見逃すはずはなく、二人の男が頷き合って別れると、ポケットに紙きれを忍ばせた男の方を貴島は追い始めた。除夜は慎重に貴島の背中を追い、やがて、その背中がポケットの男に追いつくと、目にもとまらぬ素早さで、男のポケットから紙きれを盗み取った。その身のこなしに、これもまた宝石店の一件が思い出されたが、貴島はさっそく折りたたまれた紙きれをそっと開き、おそらくは重要な文言が記されていると思われる紙面に目を通すなり、驚いたことに、無造作に紙きれを丸めて投げ捨てた。あたかも、吸い終えた煙草を投げ捨てるかのようにである。
除夜は意表をつかれたが、貴島が視界から消えたのを見はからって、その丸められた紙きれを拾い上げて中を検めた。
はたしてそこには、拙いカタカナ文字で、
ジュウハチニチ ゴゴイチジ トウノシタスイゾクカンイリグチ
と記されていた。
「十八日 午後一時 塔ノ下水族館入口」
除夜は暗唱するように繰り返しつぶやき、紙きれを忍ばせていた男が立ち去った方へ足早に移動した。一旦は見失ったかに思えたのだが、男が払い下げの時計を叩き売っている屋台で物色しているのを見つけると、そこから尾行を続けることができたのは幸いだった。
「爆破時刻?」
〈エデン〉の窓ぎわで、除夜の説明を聞いてミサキは声を震わせた。
「十八日となると、明後日ではないですか。明後日のこの時刻に水族館の入口で爆発が起きるということですか」
「この一行が示しているのは、おそらくそういうことです。問題は、この事件を追っていた貴島刑事が、なぜ、これほど重要な証拠を投げ捨ててしまったかです」
「まるで、証拠を隠滅するみたいに」
「隠滅──か」
「もちろん、刑事として確認する必要はあったのでしょうが、見てしまったけれど、見なかったことにしたかったのではないでしょうか」
「なぜなんだろう。なぜ、見なかったことにしたいのか」
「つまり──」
ミサキは自らの耳たぶを細くしなやかな指先でつまんで引っ張った。それがどうやら彼女が考えをめぐらせるときの癖で、あたかも耳たぶを引っ張ると頭の中が活性化するかのようだった。
「この時刻に、この場所が爆破されることを──まさかとは思いますが、貴島刑事は望んでいるのではないでしょうか」
「なぜだ」と除夜は繰り返す。
「権田さんが云ってましたよね。貴島刑事のライバルは除夜さんかもしれませんって。でも、その様子ではライバルに負けているんじゃないですか」
「そうか」
と除夜はそこでようやく貴島が証拠を「隠滅」した理由に近づいたような気がした。
「しかし──とはいえだ」
試しに耳たぶを引っ張ってみたが、除夜の推理は確信を得られるまでには及ばない。
「これはもう、この時刻に水族館へ出向くよりほかないのか」
疲労を帯びた声がため息まじりとなった。
✻
確信のないまま「明後日」が訪れ、除夜はミサキを伴って、〈塔ノ下水族館〉の入口へ向かっていた。「大丈夫でしょうか」
とミサキは疑心暗鬼で、確信を得ていない除夜に従うのが正しいかどうか、賭けに挑む心地だった。
大体、どこの世界に、爆破が予定されている場所へ、のこのこと出かけていく者があるだろう。
「水族館の入口というのは、ひとつしかないんですか?」
ミサキが不安を露わにすると、
「よくよく調べてみましたが、ひとつきりしかありません。しかも、今日は水族館の定休日で休館のはず」
除夜の説明を聞くまでもなく、遠目に水族館が見えて、たしかに休館らしくひと気がなかった。
「なぜ、犯人は休館日に?」とミサキは首を傾げる。
「ようするに、犯人はいたずらに大量殺人を目論んでいるわけではないということです。おそらく、人々に恐怖を与えたいだけなんでしょう。あとは、僕の推理が正しければ、僕らだけではなく、誰かが水族館にやって来るはずです」
除夜の云うとおり、水族館の入口にはすでに人影があり、少々くたびれてはいるが焦茶色の細身のスーツを着ていた。ミサキには、その姿に微かな記憶がある。
さて、誰であったか──。
ミサキは手首に巻いた腕時計を確かめると、爆破時刻まであと二分しかないと知って、血の気が引いてしまった。しかし、除夜は迷わず水族館へ突き進み、入口の前に立っているスーツの男に、
「どなたか、お待ちですか」
と声をかけた。男は除夜の顔──その広く知られた眼帯に気づくと、
「どうしてこんなところにいらっしゃるのですか」
と物腰低く訊ねてきた。除夜は脳裏に写しとられた面貌を呼び戻し、眼前の青年が、あの日、警察署の廊下を走り抜けた新米刑事であることを確認した。
「やはり、そうか」と背筋が冷たくなる。
「何があったんです?」と訊ねる青年刑事に、「これを見てください」と件の紙きれを手渡した。
「それは、あなたたちが追っている犯人が記した次の爆破計画です。分かりますか? 時刻はたった今で、場所はまさしくここです」
青年刑事は慄いた。
「いえ、心配はいりません」
除夜は極力落ち着いた声でゆっくり話した。
「犯人の隠れ家は僕が尾行して突きとめました。ただちに権田警部補が秘密裏に犯人を捕らえ、この爆破計画は無効となったのです。本来、そうした任務は貴島刑事が為すべきでしたが、彼はこの爆破計画を知りながらも、犯人を捕らえようとしませんでした。そればかりか、爆破を阻止しようともしなかったのです。その上で、あなたをここへ呼び出しました。この時刻にです。そうですよね?」
「まさか、そんな──」
青年刑事は起きていることをなかなか飲み込めないようだった。
「貴島刑事にも尾行をつけているので、おそらく今頃、取り押さえられているでしょう」
除夜がそう云うと、
「信じられません」
とミサキは首を振った。
「犯人は休館日を選んで爆弾を仕掛けようとしたのに」
「爆弾男には憎しみが募るようなライバルがいなかったのでしょう。しかし、貴島刑事には消えてほしいライバルがいた。消えてほしいけれど、自分の手を汚したくなかった。そういうことです」
除夜は空を見上げた。
〈希望の塔〉は何事もなかったかの如く風に吹かれている。
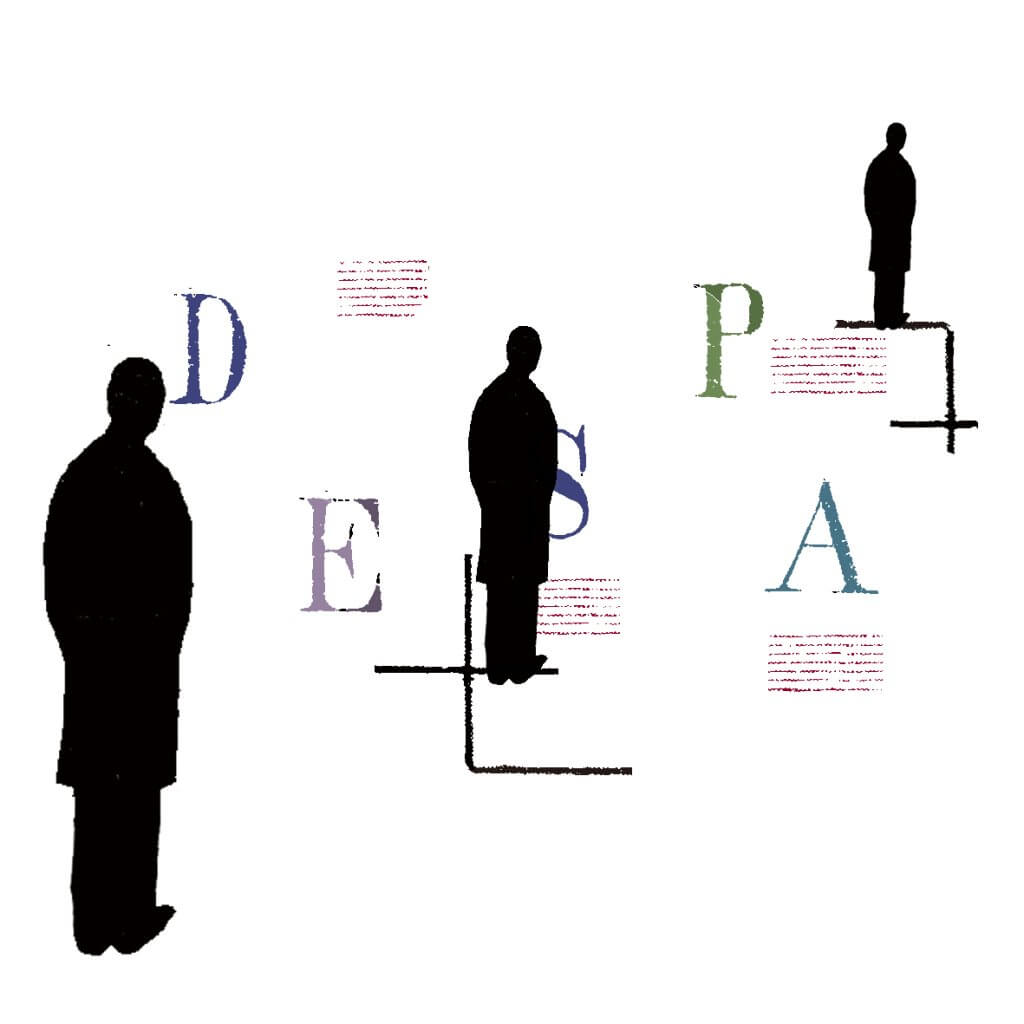
Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida
(「第四話」へつづく)
┃著者紹介
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。






















