
吉田 篤弘
第五話 ひと目惚れ[其の二]「今度の木曜の夜に、〈パンドラ〉へ行ってみようと思うんです」
除夜がミサキにそう伝えると、
「ユイコさんに会えるかもしれないからですか?」
ミサキはとどめを刺した殺し屋の如く目を細めた。
「というか、一応、探偵の仕事として──」
除夜は言葉を探しあぐねたが、
「それはそうですよね。あのひと、ご主人を殺しちゃうかもしれないんですから」
「ええ。僕が知りたいのは、なぜ、そのような思いに至ったかです」
除夜のその疑問は、ミサキが目を細めて予期したように、木曜日の夜に〈パンドラ〉のカウンターで答えが見出されることになった。
相馬由比子本人の口からである。
除夜はどことなく浮かない顔のミサキとカウンターに並び、
(木曜日にパンドラへ来るのは、やはり初めてのようだ)
と、がらんとした店内を見渡した。
商店街に並ぶ店々のあらかたが木曜定休で、きっと、休日の夜にバーへ繰り出す店主たちでカウンターが溢れ返っているのではないかと敬遠してきたのである。しかし、実際はこのとおり客の姿はなく、思うに、バーの常連たちは、除夜と同じ考えを辿って、木曜日は〈パンドラ〉へ近づかないようにしてきたのだろう。
そうした中、相馬由比子だけが木曜日の常連となり、
「毎週、決まった時間にいらっしゃるの」
マダムが明言したとおり、ほの暗い〈パンドラ〉のカウンターに、白い花が運ばれてきたかのように彼女は現れた。
彼女──ユイコさんは除夜とミサキから離れた席についたので、マダムが気を利かせて、「ご紹介しましょうか」と除夜に耳打ちした。
「いえ、今夜のところは──」
除夜はなるべく気配を消し、いつもの深紅の酒を舐めるように飲みながら、マダムとユイコさんの会話をそれとなく聞いていた。
すると、ほどなくしてユイコさんは、「あいつ」と口にし、「どうしても許せません」と声を低くした。
「本当に──殺してしまいたいんです」
「どうしてなの?」
マダムが語気を荒らげると、
「あの人、ひと目惚れしたんですよ。あの娘に」
ユイコさんは鷹を思わせる険しい目つきになった。
「あの娘?」
「花屋の娘です。わたし、見てしまったんですよ。彼があの娘の肩を抱いて囁いているのを。そのとき、彼は指輪を外していました。いや、指輪だけじゃなく、時計もです。わたしが修理に出して直してあげた、あの時計──」
ユイコさんは自らの薬指に輝く銀の指輪を眺めていた。
「それだけじゃありません。その花屋の娘は、わたしと同じ──この頰のところにです、そっくり同じ傷あとがあるんです。信じられないでしょう? わたし、どうしても許せないんです。あの人を殺して、あの娘も──」
「駄目よ」
マダムがぴしゃりと云った。
除夜とミサキは顔を見合わせ、
(殺意の動機が──)
(判明しましたね──)
声には出さず、唇だけを動かして頷き合った。
除夜はミサキをアパートに送り届けて時計屋に帰ると、作業台に向かって懐中時計の修理に余念のない仰太郎に、
「相馬由比子という女性を知っていますか」
といきなり訊いてみた。意表をつかれた仰太郎は、
「相馬──由比子ですか」
と作業の手を止め、六月と同じように顎を上げて、
「ああ、あの人ですか」
と頷いて記憶を反芻した。
「なんだか、おかしな人でしてね、いらっしゃったのは、一年ほど前のことでしょうか。ずいぶんと古い時計をお持ちになられて。旦那の時計だと云っていました。ぴかぴかに修理してほしいと──」
「どんな時計でしたか?」
「どんなも何も、中を見たら油が固まっていて、ひさしぶりに手こずりましたよ。あれは、かれこれ二十年は止まったままだったんじゃないですか」
「二十年──」
除夜は自分の頭の中も古びた油で固まっているんじゃないかと思わず首を振った。
「そうか──もしかして、そういうことなのか」
ゼンマイと歯車が嚙み合って動き出し、頭の中で止まっていた時計が正確な時刻を刻み出していた。
✻
それから、ふたたび木曜の夜がめぐってきて、除夜とミサキは〈パンドラ〉のカウンターにいたが、やはり他に客はいない。「そろそろ、時間よ」
マダムが店の時計を見ると、生真面目な性格を体現するかのように、相馬由比子が店に入ってきた。
先週と同じく除夜とミサキから離れた席につき、先週もそうであったように、最初はなごやかにマダムと言葉を交わしていた。
だが、徐々に酒がまわり始めると、背筋がゆるみ、声の調子もオクターブ下がって口調も荒れ始めた。
「あいつが」と云い出し、「あの娘とね──」
先週の繰り返しになった。マダムが、
「それは本当のこと? 本当に、その娘とシンイチさんが──」
念を押すように確かめると、
「探偵を雇って調べさせたんです。だから、残念ですが本当なんです」
「探偵」の響きに除夜は反応し、おもむろに席を立って相馬由比子に近づくと、
「奇遇ですね。じつは、僕も探偵なんです」
と自己紹介の機を得た。
「除夜と申します。あなたのことは、かねてマダムから伺っていました。ユイコさん──とお呼びしてもよろしいでしょうか」
「ええ」とユイコさんは咄嗟にマダムの方を見て、マダムは、「ごめんね、心配だったから」と詫びている。
「ユイコさんがおっしゃる花屋の娘さんなんですが──」
除夜はいつになく喋りがまろやかだった。
「花屋というのは、〈塔ノ下〉の目抜き通りにある花屋のことでしょうか」
「ええ、そうです」
頷いたユイコさんの隣に除夜は座り、
「あの花屋には、たしかに若い女性がいらっしゃいます。きびきびと働く快活なお嬢さんです。ですが、彼女の頰に傷あとはありませんでした」
まろやかな声でそう云うと、
「そうでしたか? でも、わたし見たんです」
ユイコさんは怯まなかった。
「いや、それはあなたの頭の中にある、お話ではないでしょうか」
除夜もまた怯まない。
「あなたがどのような探偵を雇ったのか、非常に興味深いですが、おそらく、その探偵というのも、あなたの頭の中にしか存在していないのではないですか」
「そうなの?」とマダムの目がひと回り大きくなった。
「僕は本物の探偵です」
除夜は一貫して穏やかだった。
「しかし、探偵というのもおかしなもので、常に自分の頭の中にあるお話を追いかけているようなもんです。ですから、これは僕の頭の中のお話として聞いていただきたいのですが──」
除夜はまっすぐ自分を見据えているユイコさんの瞳を、眼帯のない右目で覗き込むように見返した。
「どうやら、ご主人が花屋の娘さんと懇意になっているというのは、あなたの妄想のようです。では、なぜ、そのような妄想を抱いたのか? それは、あなたがご主人を葬るための動機が欲しかったからです。あなたはご主人を深く愛していました。その情熱は誰にも負けないでしょう。しかし、あなたはそれほどまで愛していた彼を葬らなくてはならなかった」
ユイコさんは目を閉じた。
「大変申し訳ないことですが、僕はこの一週間、あなたがどのように過ごされているか観察させていただきました。あなたは驚くばかりに几帳面で、決まった時間に銀行へ出勤し、同じ時間に同じマーケットで買い物をして、ほとんど外出することもありません。その繰り返しでした。ただひとつだけ例外であったのは、昨日の夜──水曜日の夜です──あなたは、とある男性と銀行の帰りにひと気のないコーヒー・バーで待ち合わせをし、差し障りのない云い方をすれば、いわゆるデートを楽しんでいらっしゃった。背の高い口髭をたくわえた紳士です。あなたは、あの方に──」
「はい」とユイコさんは目を開いた。「ひと目惚れをしたんです」
「そうだったんですね」とミサキは驚き、
「ちょっと待って。ということは、それでまさか、シンイチさんを──」
マダムが先走りそうになるのを、除夜は制し、
「あなたは恋に落ちました。もう二度と恋などすることはないと思っていたのにです。ですから、ずいぶんと悩まれたのではないですか? そして、さんざん悩んだ結果、あなたはシンイチさんを葬ることに決めた。あなたは、彼の蔵書を売り払いました。僕が調べた限り、本だけではなく、彼の衣服をはじめ、身のまわりのありとあらゆるものをことごとく処分しています。この半年ほどの間にです」
「どういうこと?」とマダムが首をかしげた。「シンイチさんの服を?」
「ええ、そのとおりです」
ユイコさんは、ふたたび目を閉じた。
「ワードローブにあったものを、残らずすべて──」
「残らずすべて?」
マダムは納得がいかないようだった。
「ここに」──と除夜は上着のポケットから一通の封筒を取り出し、中から折りたたまれた薄紙を引き出すと、
「ここに、相馬真一さんの戸籍謄本の写しがあります」
と広げてみせた。
「知り合いの警察関係者に頼んで入手した正式なものです。この謄本を確認する限り、現実の世におけるシンイチさんは二十年前に亡くなられています。病院の記録を調べてみたところ、死因は肺炎とありました。二十年前というのは、お二人が結婚された翌年にあたります」
「そんな──」とマダムは絶句した。
「ユイコさんは、その現実を受け入れられなかった──いえ、いまのは僕の云い方が間違っていました。たとえ現実がどうであろうと、ユイコさんの頭の中にシンイチさんは生きていて、つまりは未来永劫、亡くなることはありません。ですから、彼が身に付けていた服や靴、あるいは、鞄、財布といったもの──そう、時計もです、そうしたものの手入れを欠かさず、頭の中のシンイチさんが満足できるよう努めていたはずです」
除夜は神妙な顔になった。
「しかしです。半年前にあの髭の紳士と出会い、ご自分でおっしゃられたとおり、ひと目惚れをされたのですね。そこからすべてが変わったのでしょう。現実を受け入れないことには、前へ進めなくなりました。几帳面なあなたは苦悩しました。そして──」
「教えてほしいんです」
ユイコさんは除夜の話を遮った。
「どうか教えてほしいんです。すでに死んでしまったあの人を、一体、どうしたら殺すことができるんでしょう?」
沈黙が時を止め、誰もが眉ひとつ動かすことなく口を閉ざしていた。
ユイコさんは指輪の光る薬指の先を頰の傷あとに当て、
「どうか、教えてください」
と静かに目を閉じた。
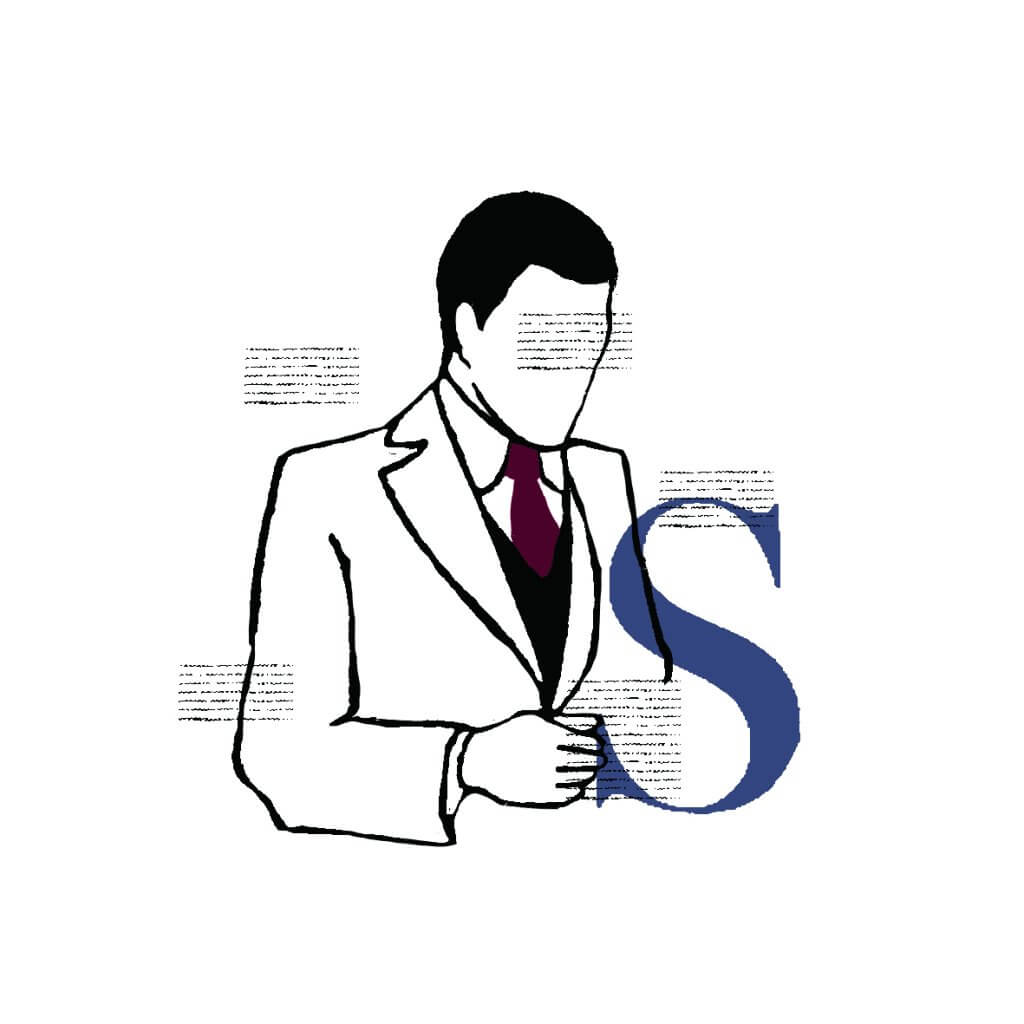
Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida
(「第六話」へつづく)
┃著者紹介
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。






















