
一般的な新聞の半分のサイズを用い、一般的な新聞に比して、いささか大衆向けの記事を主体としたローカル・ペーパーの判型および媒体そのものをタブロイド判と云う。
相手の勢いに押されて興醒めすることを鼻白むと云い、物事を独自な先入観もしくは偏見および決めつけによって眺めることを色眼鏡と云う。
書物の体裁において、紙を綴じた背表紙の反対側にあたる断裁面を小口と云い、その小口を断裁せずに袋状のまま製本することをアンカットと云う。そして、このアンカット仕様の書物を読む際、袋状の小口を頁ごとに切り離す道具をペーパーナイフと云う。
とある昼下がり、除夜とミサキが〈エデン〉で食事をしていると、
「あの──」
一人の少年が二人のテーブルの脇に立ち、
「ぼくは、こういう者です」
品のいい薄手の紙を使った名刺を差し出した。しっかりと打たれた活字のインクは乗りもよく、とても子供が遊びでつくったものとは思えない。
「上岡──智司──君」
除夜が名刺の名を読み上げると、
「君はいりません」
少年は大人びた口調で反発した。
「〈塔ノ下新聞社〉?」
除夜が少年の肩書を確認すると、
「ええ。〈塔ノ下新聞社〉の、ぼくが社長で、記者で、編集者で、印刷者でもあります」
「君が一人でつくっているわけね」
ミサキが笑いかけると、
「決して遊びではありません」
少年は肩から提げていた布かばんの中を探り、「ええと」と、そこはいかにも少年らしく、もたついた動作を見せた。
「ありました、これです」
刷りたての、まだインクの香りが残るタブロイド判を除夜に手渡した。二つ折りにした四頁の簡易新聞ではあるが、一面には、〈TOUNOSHITA NEWS──塔ノ下ニュース〉と誇らしげに紙名が謳われている。こちらもまた、見てくれからして、子供が一人でつくったものとは思えない。
除夜が記事を読み始めると、ミサキも顔を寄せて一緒に読み、「中身もしっかりしているわ」と感心した。
「本当に君が一人で書いているの?」
「もちろんです」
少年は得意げに小鼻をひくつかせた。サイズが大きいのか、鼻の上の丸眼鏡が、いちいちずり落ちてくる。それをしきりに直しながら、
「今日は除夜さんに取材をお願いしたいと思いまして」
あらたまって一礼した。
「なるほどね」
除夜より先にミサキが応えた。
「いまをときめく名探偵が、どんな人物であるか、紹介しようというわけね」
「いえ、そうではありません」
少年は即座に否定した。
「そのような下世話な発想は、ぼくにはありません」
「あら、そうなの」
ミサキは、あたかも自分が「下世話」と断定されてしまったようで、一気に鼻白んだ。
一方、除夜は、少年の大人びた言動に自らの子供時代を見るようで、
「では、どうして取材を?」
色眼鏡を引っ込めて、少年に向き直った。
「小説を書こうと思っているんです」
少年は意外なことを云い出した。
「この新聞で連載をしたいんです。その号で十号目になるんですが、何か、もうひとつ足りなくて──何が足りないのかとよくよく考えて、思い当たったんです。そうだ、連載小説を書こうと」
「なるほど」
「ちょうど、書いてみたいものがあったので」
「しかし、君の書いてみたい小説が、どうして僕に関係するんだろう」
「謎めいた殺人事件が起きるんです。連続殺人です。その謎と犯人を、探偵が解明していくお話なんです。それで、是非、名探偵の除夜さんにお話を伺いたく──」
「僕はいま、探偵の仕事は休業中なんです」
「本当にそうでしょうか?」
少年は除夜の独眼を射抜くように見つめていた。
「ぼくが調査したところによると、最近の除夜さんは、事件が起きる前に事件を解いてしまうとか。それこそが、本当の名探偵ではないかと──」
「いや、『名探偵』なんて言葉、僕は口にしたこともないけれど」
「では、云い直します。それこそが、本当の探偵ではないかと宣言されたそうですね」
「そのとおり」とミサキが口を挟んだ。「世間の皆さんは知らないと思うけど、本当に事件が起きる前に──とりわけ、殺人事件が起きる前に謎を解いて、何人かの命を救ってきたんです」
「宣言だけではなく、すでに実行しているんですね」
少年は明らかに興奮していた。興奮のあまり、「それって」と急に少年らしい口調になり、
「それって、現実の事件だけじゃなく、お話の中の架空の事件でも同じことでしょうか」
「どういう意味?」
ミサキが問い質すと、
「ぼくはこれから、お話の中で殺人事件を起こそうと思っています。つまり、お話の中で誰かが殺されてしまうのです。架空の犯人は架空の事件を起こし、架空の誰かが命を落とす。すべては僕の頭の中にある架空の話ですが、殺人は殺人です。しかも──」
「しかも、連続して何人も殺される」
除夜が後を継いで、口を歪めた。
「それは、やはり聞き捨てならないな──」
「ですよね」
少年は我が意を得たり、という顔になった。
「おかしな話かもしれないけれど──」
除夜は、しばしの沈黙を置いてつづけた。
「かもしれないけれど──現実であろうが、架空であろうが、誰かが事件を起こして誰かが殺されてしまうと分かっているなら、僕としては、なんとかして阻止しなければと思ってしまう」
「では──ぼくが小説を書き始める前に、ぼくの頭の中に、どんな殺人事件が用意されているのか、推理を働かせて云い当ててください」
「え? 君は一体、何を云っているの?」
ミサキは少年の無茶な要求に眉をひそめたが、
「もし、当てることができたら?」
除夜はその気になっている。
「除夜さんが見事に言い当てたら、名探偵に敬意を表して、いさぎよく探偵小説を書くのはあきらめます。別の何かを──冒険小説か恋愛小説を書くことにします」
「どう思うって──どういうことですか?」
店を訪れた除夜とミサキに、古本屋の六月は首を傾げて問い返した。
「つまりですね──」
ミサキは六月を前にすると妙に言葉遣いが柔らかくなる。
「この新聞をつくっている少年が、はたして、どんな殺人事件を起こすか、ということです」
「いや、そうじゃなく──」
除夜があわてて訂正した。
「どんな殺人事件を物語に書くか、ということなんです」
「どちらでも同じですよ」
六月は大げさに肩をすくめて除夜を睨んだ。
「僕に分かるわけがないじゃないですか」
「しかし、君はここでこうして本に囲まれて、一日中、本の頁をめくっているわけでしょう?」
「それはまぁ、そうですが──」
「手がかりは、ここにこうしてあります。少年からもらった〈塔ノ下ニュース〉一部と、彼の名刺です。ありとあらゆる書物の頁をめくってきた君であれば、なにかしら感じるところがあるのではないですか」
「さぁ、どうでしょう」
「何でもいいんです。ささいなことであっても」
「そうですね──」
六月は新聞と名刺を交互に眺め、しばらくすると、「ほう」と何ごとか得心した様子になった。
「ひとつだけ云えるのは、この新聞と名刺は、同じ印刷所で刷られたものであるということです」
「なぜ、それが分かるんです?」と除夜はいま一度、ふたつを見比べた。
「使われている活字が同じ書体なんです」
「いや、それは僕も気づいていたけど、同じ書体が使われているからと云って、同じ印刷所で刷られたかどうかは分からないのでは? 活字はどこの印刷所にもあるわけだし」
「いえ、それがそうでもないんです」
「というと?」
「僕の目が確かであれば、この書体は特別につくられたものに違いなく、一般の書籍や新聞、雑誌で使われているのを見たことがありません」
「そんな活字があるのですか」
ミサキが控えめに声を落とした。
「おそらくですが──」
除夜ではなく、六月が名探偵の顔になった。
「この書体は、この印刷所が自ら鋳造した独自なものではないかと思います。昔はさしてめずらしいことではありませんでした。いまも、その名残で、活字の名前に印刷所の名前が使われていたりします。もとは、その印刷所だけの書体だったんです」
「しかし」と除夜が疑問を呈した。「仮に独自であったとしても、この印刷所で刷られた書物なり雑誌なりが世に出回っているのでは? 出回っていれば、この店にも流れてくるはず」
「おそらく、名刺や葉書の印刷を専門にしている、巷の小さな印刷所ではないでしょうか」
ミサキが新聞を手に取り、隅の方に極小の活字で刷られた印刷所の名前を読み上げた。
「〈上岡印刷所〉──少年の苗字と同じですね」
「そうか、彼は印刷屋の息子だったのか」
除夜の瞳に光が宿った。
「時計塚三丁目十七番地」
ミサキが印刷所の住所を読み上げると、それは少年の名刺に刷られていた〈塔ノ下新聞社〉の住所と完全に符合していた。
「よし、彼に会いに行こう」
自分の心が少年時代に戻りつつあるのを除夜は自覚していた。
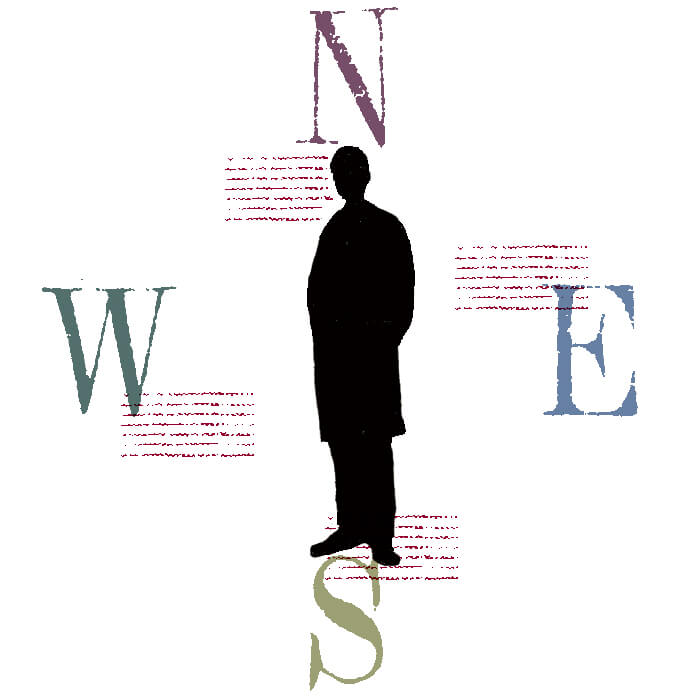
Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。






















