
吉田 篤弘
第七話 ペーパーナイフ[其の二]除夜とミサキが〈上岡印刷所〉を訪ねると、推測どおり、迎え出たのは少年で、彼は意表を突かれたのか、あわてふためきながら、作業机の上に広げていたものを、素早く背後の本棚に移した。
机上には一冊のノートが残され、その脇にインクを吸い上げた太軸の万年筆が転がっている。少年は何かしら書きものをしていたに違いなかった。(あるいは、まさに探偵小説を執筆していたのかもしれない)と除夜は少年の背後の本棚に目をくれた。
そこに並んでいたのは、特にどうと云うこともない雑本の類で、ただひとつだけ目を引いたのは、こちらに背表紙を見せず、逆向きに本棚に押し込まれた一冊だった。
どうやら、除夜とミサキの訪問に驚き、机上から咄嗟に隠し入れたものと思われる。咄嗟ではあったが、書名を見られたくなかったので、逆向きに入れたのだろう。こちらには小口が──頁の断面だけが白く見えていた。
「ずるいですよ、急に来て」
少年は除夜の方を見ずに云った。
「ぼくがどんな小説を書いているか、覗きに来たのではないですか?」
「まさか、そんなことはしません」
除夜はなるべく丁寧な口調を心がけた。相手は少年だが、只者ではない。
少年のノートが置かれた作業机の向こうには、無数の──ともすれば、無限とも思われる──活字が整理棚に入れられて並んでいた。六月の云うとおり、主に名刺の印刷を請け負っている小さな印刷所のようだが、それでも、ひと通りの文字を揃えているようだ。
「君はもしかして──」
除夜が云いかけたことを察し、少年は「ええ」と先んじた。
「ご覧いただいたとおり、活字を拾って文字を組むのがぼくの仕事です。以前は優秀な植字工がいたのですが、急に辞めてしまって。そのうえ、父が胸の病気で倒れ、仕方なく、ぼくが代わりに──」
「そういうことだったのね」とミサキが事情を飲み込むと、
「ところで、除夜さん」
少年は唐突に身構えた。
「ぼくがお話の中で、どんな殺人を試みるか、推理できましたか」
そう云いながら、どこに隠し持っていたのか、少年の手にちょうどよく収まったナイフを、ぐいと突き出して除夜を威嚇した。
「ひっ」とミサキは声を上げたが、除夜は注意深くナイフを観察し、
「それで、人を殺すのは簡単じゃない」
とナイフに手を伸ばした。慄いたミサキには構わず、刃の部分を握りしめて少年から奪い取ると、
「よく、ご覧なさい。木製のペーパーナイフですよ」とミサキに見せた。
「いえ、ペーパーナイフだって、凶器になり得ます──」
少年は悪戯めいた笑みを浮かべた。
「でも、ぼくが考えているのは、そんなことではありません」
「ヒントが欲しい」と除夜が云うと、
「ヒントは、いまさっきお伝えしました」と少年は冷静だ。
「いまさっき?──となると、辞めてしまった植字工の話とか?」
「さすが、名探偵。目のつけどころが違いますね。そのとおりです。じつを云うと、ぼくが書こうとしている探偵小説は、彼がモデルになっているんです」
「その植字工が?」
「ええ。彼は自分について多くを語らず、いかにも謎めいていました。探偵小説が好きで、時間さえあれば読みふけっていたんです。だからなのか、妙なことに詳しくて、たとえば、人はどうなると絶命するのか、ぼくが訊いたわけでもないのに、そんなことを話してくれました。それで、ふと思ったんです。この人はもしかすると、人を殺めたことがあるんじゃないかって。だから、彼が急に仕事を辞めて出て行ってしまったとき、活字棚からアルファベットの活字が三組なくなっているのに気づいたんです。それからというもの、その理由を、ずっと考えていました」
「三組も?」とミサキが驚きの声を上げる。
「いえ、アルファベットや平仮名は何十組もあるんです。ですから、三組ばかり無くなっても、普通は気づきません。でも、ぼくは気づきました。彼に不信感を抱いていたからです」
少年はそこで少しばかり得意げな顔になった。
「それで、ぼくは考えたのです。彼をモデルにした男が殺人を企てる小説を書いたらどうだろうかと。なぜ、彼はアルファベットの活字を持ち去ったのか? これがヒントです。どうですか、除夜さん、これで分かりますか? ぼくの小説がどんなものになるか」
「もしかして」と除夜もまた得意げに見えた。「こんなふうに始まるんじゃないですか? 探偵のもとに、ある日、一通の封書が届く。封を切ると、中には銀色の活字がひとつ。それはアルファベットのAで──」
「どうして分かったんですか──」
「何日かすると、謎めいた殺人事件が起こり、その事件の起きた場所の頭文字がAで始まるところ、たとえば、AOIKE──青池であると探偵は気づく。そして、またしばらくすると、今度はBの活字が送られてきて、その数日後にBUNRAKUDO──文楽堂で第二の殺人事件が起きてしまう。つまり、A、B、C、D、とアルファベットに従って連続殺人が起きるわけです」
「どうして──」
「君は、連続殺人事件を書くと云っていました。連続するものには法則があった方が面白い。そこへ、おあつらえ向きにアルファベットの活字を持ち去った男が現れた。まぁ、僕の推理では、別に謎めいたことではなく、彼はただ記念に持ち帰っただけなのかもしれませんが──」
「でも、いいアイディアだと思いませんか?」
「そう──いいアイディアかもしれないけれど、僕が知っている外国の探偵小説に、ちょうどそんなお話があるんです。その作品はまだ翻訳されていませんが、向こうでは人気のある有名な作品です。君はその小説を読んで、影響を受けたのか、あるいは、そのまま引き写して書こうとしているのか。いまなら、そっくり同じ話を書いても、誰も気づかないでしょう」
「どうして、そんなことまで分かったんです?」
除夜は過去を振り返って目を細めた。
「君が〈エデン〉で布かばんから新聞を取り出そうとしたとき、うまく取り出せなくて、少々もたついていました。そのとき、かばんの中から英和辞典が覗き見えたんです。それと──僕たちがここへ来たとき、君はあわてて何かを棚に隠しました。あわてていたけれど、背表紙がこちらに見えないよう、一冊の本を慎重に棚に差した。そのおかげで、その本の小口が見えました。小口はアンカット仕様になっていて、あらかたのページが切ってありましたが、あの本はおそらく、外国でつくられた本ではないですか?」
「アンカット仕様?」とミサキが除夜に問うた。
「頁が断裁されていない本のことです。そうした本を読むときは、自分でひとつひとつページを切りながら読んでいくんですが、その際に使うのが、ペーパーナイフです」
少年は驚嘆していた。
「何もかもおっしゃるとおりで──降参です」
「では」と除夜は声を硬くした。「君は約束どおり、探偵小説を書くのを中止し、架空の殺人を実行することを断念しますね?」
「ええ、約束ですから」
「いずれにしてもです、先行する作品を引き写して発表したら、小説の中だけではなく、小説を書いた君自身も探偵に追われることになるでしょう」
「除夜さんは、この本を読んだことがあるんですか」
少年が逆向きに差し入れた本を本棚から引き出してきた。それは除夜の憶測どおり洋書であり、表紙に「The ABC Murders」とある。
「いや、噂には聞いていたけれど、こうして手に取ったのは初めてです。こんなめずらしい本を、君はどうやって手に入れたんだろう?」
「あの人がくれたんです」
「あの人というのは、その植字工のことですか」
「そうです」と少年は快活に答えた。「あの人は僕が新聞をつくり始めたとき、『すごく、いいことだ』と応援してくれました。子供だって──いや、子供だからこそ、自分の視点で世の中を捉え、それがどんなふうに映っているのか、世の人たちにしっかり伝えるべきだと思うって。そんなふうに云ってもらえたのが嬉しくて、ときどき、どうしていいか分からなくなると、あの人に相談していました。じつは、『小説を書いたらどうだろう』と提案してくれたのも、あの人だったのです」
「そうでしたか──」
「ええ。でも、小説なんてとても書けないと怖気づいていたら、『大丈夫、参考になる本があるから』と言って、この本を、この『The ABC Murders』を僕にくれたんです。英和辞典とペーパーナイフも一緒に。『これを読んで書けばいい』って」
✻
「そうでしたか、当たっていましたか」と六月は複雑な表情になり、「よく気づいたものです」
と除夜は手放しで賞賛した。
「この機会に、僕も手もとにある本を開いて、いくつか活字を見比べてみました。しかし、容易に見分けがつかないものが多々あるし、驚いたことには、一冊の本の中で、二つや三つの違う書体を併用しているものもありました」
「ええ、同じ字が──たとえば、『の』や『た』や『が』といった、よく使われる字があまりに多用されると、いくらストックしておいても足りなくなることがあります。そういうときに、仕方なく別の書体を交ぜて使うことがあるんです」
「それにしても、虫眼鏡をあてて覗かないことには、『の』の字ひとつとっても、違いが分かりづらい──」
「ええ。もし、手がかりが名刺だけだったら、判断できなかったと思います。しかし、新聞の方にアルファベットが使われていました。漢字や平仮名はそれほど特徴のある書体ではなかったんですが、あのアルファベットは、かなり癖のある書体で、僕は初めて見ました」
「アルファベットか──」
除夜は感慨深く息をついた。
なぜ、辞めていった植字工は、三組のアルファベットを持ち去ったのだろう。少年には、「記念に持ち帰っただけ」とその場しのぎの推理を口走ったが、その男が『The ABC Murders』を読んでいたことを考え合わせると、何かもっと不穏な理由があったのではないかと勘繰りたくなる──。
除夜がいま一度、頭の中を整理しようとしたところへ、突然、仰太郎が古本屋の中へ駆け込んできて、
「やはり、こちらにいらっしゃいましたか」
と息を切らしながらそう云った。
「権田さんから、『急な用件で』と連絡がありまして、急いで来て欲しいそうです」
「急な用件? さて、何だろう」
除夜は権田の「急な用件」が、おそらく、いい知らせではないだろうと確信していた。
「さぁ、何でしょうな」
仰太郎は何かを思い出そうとするように視線を頭の上へ送り、
「そういえば、新たなアルファベットが、どうのこうのとおっしゃっていたように思います」
「アルファベットか──」
除夜はまた深々と息をついた。
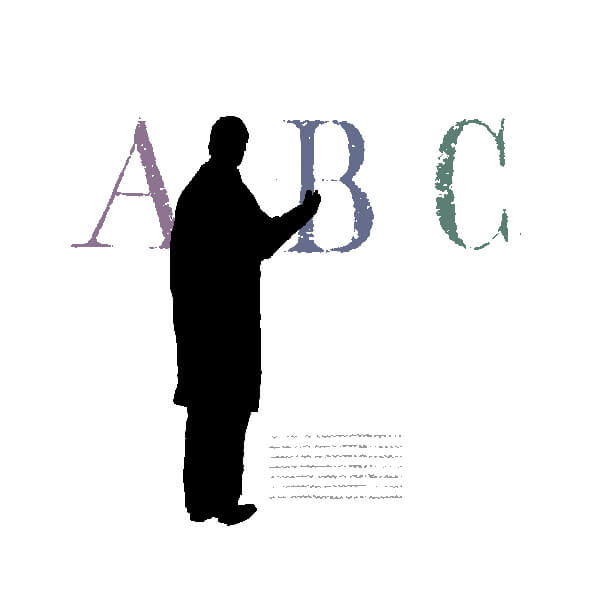
Collage Illustration──Atsuhiro Yoshida
(「第八話」へつづく)
┃著者紹介
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。
吉田 篤弘(よしだ・あつひろ)
作家。
1962年東京生まれ。小説を執筆するかたわら、「クラフト・エヴィング商會」名義による著作と装幀の仕事を手がけている。著書に『奇妙な星のおかしな街で』(春陽堂書店)、『つむじ風食堂の夜』(筑摩書房)、『それからはスープのことばかり考えて暮らした』(暮しの手帖社)、『おやすみ、東京』(角川春樹事務所)、『月とコーヒー』(徳間書店)、『中庭のオレンジ』(中央公論新社)など多数。






















