
南條 竹則
第3回 鏡花と焼芋【後編】
散髪を済ませて店を出ると、「泉さん」と声がかかる。呼びかけたのはレストランの女性である。じつは、このレストランはさる料理屋が経営していて、女性はそこのお座敷で会った顔見知りだった。それで、鏡花は店に上がり、ビールだけ飲んで帰るわけにもゆかないから、鳥肉料理を食べる。
少々散財してしまって懐が寂しくなり、心のうちもそぞろ寂しくなってビルの前に佇んでいると、流しの円タクが来て、運転手台から、仰向けに指を三本出した。これはもちろん、この値段で乗りませんか、と料金を示したのだ。
三本指を見て、鏡花は例の支配人と焼芋の話を思い出した。それで、こんなことを考えつく。
然うだ、焼芋の事を、ここにちなんで(真珠)としよう。
ものは称呼も大事である。辻町糸七が、其の時もし、真珠、と云つて策を立てたら、弦光も即諾して、こま切同然な竹の皮包は持たなかつたに違ひない。雪に真珠を食に充て、真珠を以て手を暖むとせむか、含玉鳳炭の奢侈、蓋し開元天宝の豪華である。(『鏡花全集』巻二十四、509頁)
「含玉鳳炭」という言葉はよくわからない。ものは称呼も大事である。辻町糸七が、其の時もし、真珠、と云つて策を立てたら、弦光も即諾して、こま切同然な竹の皮包は持たなかつたに違ひない。雪に真珠を食に充て、真珠を以て手を暖むとせむか、含玉鳳炭の奢侈、蓋し開元天宝の豪華である。(『鏡花全集』巻二十四、509頁)
昔、中国で葬礼の際、死者の口に玉を含ませる習慣があり、それを「含玉」というが、ここで言うのはそれではあるまい。
本物の玉は触るとヒンヤリすると考古学者の先生から聞いたことがある。それ故だろう、楊貴妃が玉を口に含んで夏の暑さをまぎらしたという話が、『開元天宝遺事』という書物に載っている。「含玉」はそこから来ていると思うが、鳳炭の方は何に基づくのだろう。
ともかく、「開元天宝の豪華」はふるっている。楊貴妃がハフハフと焼芋にかじりつく図が目に浮かぶではないか。いや、焼芋ではない、真珠だった──クレオパトラは真珠を溶かして飲んだというから、楊貴妃がこの真珠を食べても悪くはあるまい。
それにしても、「薄紅梅」という小説は何と焼芋への愛着に満ちているのだろう。ちなみに、これは鏡花の最晩年の作品である。青春時代を懐かしむ老人の気持ちが伝わってくるような気もする。
焼芋に関しては、「春着」という小品にもこんな話が出て来る。
神楽坂の「川鉄」という鳥屋は尾崎紅葉が贔屓にする店だった。紅葉がここで
御飯をあがつて居ると、隣座敷で盛んに艶談のメートルを揚げる声がする。紛ふべくもない後藤宙外さんであつた。そこで女中をして近所で焼芋を買はせ、堆く盆に載せて、傍へあの名筆を以て、曰く「御浮気どめ」プンと香つて、三筋ばかり蒸気の立つ処を、あちら様から、おつかひもの、と持つて出た。本草には出て居まいが、案ずるに焼芋と餡パンは浮気をとめるものと見える……が浮気がとまつたか何うかは沙汰なし。ただ坦懐なる宙外君は、此盆を譲りうけて、其のままに彫刻させて掛額にしたのであつた。(巻二十七、287頁)
焼芋がどうして浮気を止めるのか、その理屈はわからないが、色気がないということだろうか?餡パンに関しては、「雑記」所収の「説林」に、鏡花はこう記している──
天外子が説を聞けば、腹の痛む時(チキン・ロース)を食べれば直り、宙外子の説によれば、人餡パンを多食すれば美人に遠かる。(巻二十八、259頁)
「天外子」とは小説「魔風恋風」の作者小杉天外のことで、この人は後藤宙外らと共に丁酉文社を結成した。餡パンの方はともかく、チキン・ロースはたしかにお腹に優しそうだ。
※本稿および前稿は実践女子大学の学科誌「歌子」第26号所載の拙文「書生の羊羹」の一部を増補改訂したものである。
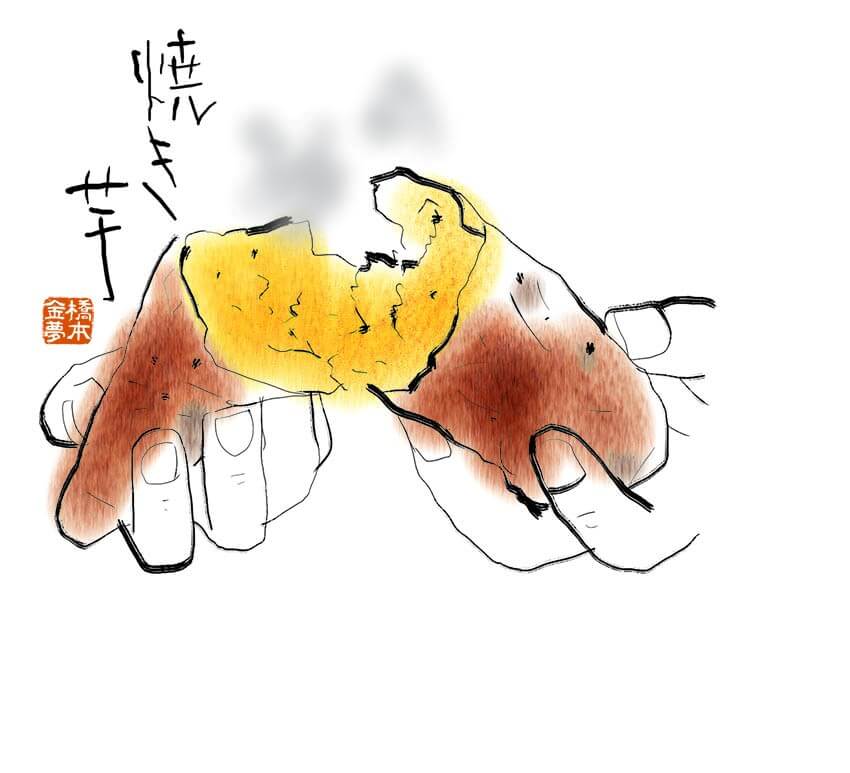
┃この記事を書いた人
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)
文/南條 竹則(なんじょう・たけのり)
1958年生まれ。東京大学大学院英語英文学修士課程修了。作家、翻訳家。
『酒仙』で日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。以後、幻想小説、温泉、食文化への関心が深く、著書も多い。主な著書に小説『あくび猫』、編訳書『英国怪談珠玉集』など多数。
絵/橋本 金夢(はしもと・きんむ)






















