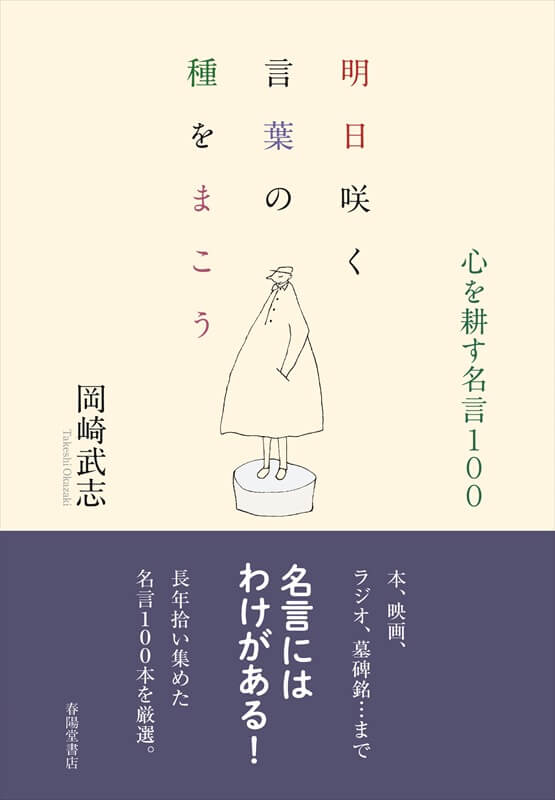【第40回】
脇役という名のヒロイン
ディック・フランシス『横断』(ハヤカワ・ミステリ文庫)の話がしたい。ほぼ毎年新作が発表される長編競馬ミステリーシリーズも、これで25作目。毎回、違った職業や設定がなされるが、ベースは競馬界にからむ事件(殺人)が発端である。
今回は「名馬、馬主、競馬ファンを満載してカナダ各地の競馬場を巡り、車内ではミステリ劇が演じられるという大陸横断競馬列車」(カバー解説)が舞台。そこに身分を隠し、乗務員(ウェイターのトミー)として乗り込むのが英国ジョッキー・クラブ保安部員のケルジイ29歳。彼は親の遺産を受け継ぎ、一生働く必要のない富豪だが、退屈を拒み危険な役職に就いている。
この列車に競馬界を汚染する邪悪な男が乗り込んでいて、ケルジイの役目は彼が企む陰謀を阻止すること。そのため、絶対に身分を知られてはならない。ケルジイは毎日のようにことの経過をカナダの同職にあるビルに連絡を取ることになるが、直接の電話の接触は避けなければならない(相手は胸が悪くなるほどの悪党)。そこで連絡係に指名されたのが、まったく存在を知られようがない、ビルの母ミセス・ボードレアであった。彼女がいわば「伝書鳩」となり、ケルジイと息子ビルの間をとりもつ。
しかし、話を聞いてジョッキー・クラブの上司が反対する。というのも、ミセス・ボードレアはベッドに寝たきりの老婆であった。彼女は小説の上では電話のみの出演で、容貌や姿の描写はない。声だけ。ところが、この余命いくばくもない老婆が、本作において素晴らしいヒロインとなる。
彼女は好奇心が強く明敏で、1を聞いて10を悟る知性の持ち主だった。それに競馬界にも通じている。ビルの伝言を教え、ケルジイからの情報を聞き直すことなく理解し、書きとめる。有能きわまる「伝書鳩」、それに加えた人間的魅力に感嘆し、電話を切る間際にケルジイは言う。
「あなたは本当に素晴らしい人だ」
以後、姿が見えず、声だけのやりとりによるミセスとの逢瀬が、陰惨な物語を彩ることになる。2人とも電話によるおしゃべりが楽しみになっているし、読者もボードレアの登場を心待ちとするようになるはずだ。毎回、競馬シリーズには主人公のお相手を務めるヒロインが用意される。『横断』では、この横断競馬列車を企画した旅行会社の社員で、道中を随行するネル・リッチモンドだ。ケルジイは彼女に恋をし、向こうもまんざらではなくロマンスは進行する。
しかし、解説で高橋直子が指摘するように「この年とった御婦人に比べてみれば(中略)どうも存在感が希薄」だ。それほどミセス・ボードレアの存在が生き生きとしている。この声のみのベッドにしばりつけられた老女こそがヒロインなのだ。作者も当初、そんなつもりではなかったが、書き進めるうちに老女に心が移っていったのではないか。どうもそんな気がする。
事件は無事解決し、ケルジイはボードレアに会いに行こうと思う。いつものように電話したところ、出たのは息子のビルだった。そして彼の口から母の死が告げられる。茫然とするケルジイ。彼女は自分が余命いくばくもないことを知っていた。そして逝った。涙を抑えてようやく「お母さんは……素晴らしい人でした」とケルジイ。ビルがそれに答える。
「母もきみに対して同じ気持ちを抱いていた。きみは母の最後の一週間を楽しいものにしてくれたのだ。事の結末を知るまで生きていたがった。最後に言ったことの一つは……「この話が終わるまでは行きたくない。あの見えない若者に会いたい……」その間、次第に意識が薄れていったのだ……やがて亡くなった」
これは泣きます。会えなかった2人の強い結びつきに感動するのだ。凡庸な書き手なら(たとえば私が書くなら)、ボードレアを生かしておいて、事件解決後ケルジイと対面させる。つまり安易な感動シーンをこしらえるのだ。ベッドのボードレアが言う。「あなたがあの若者なのね?」。「そうです私です」とケルジイが近づき、手を差し伸べる。これでも泣くだろうが、まあ安易ですね。
ディック・フランシスは読者を裏切り、さらにダメを押して、次の詩を引用して悲しみを引き締める。
「あの良き夜に静かに入って行ってはならない、/老年は一日の終わりに燃え、叫ばなければならない──/消えて行く光に怒り怒るのだ……」
これは現代イギリスを代表する詩人、ディラン・トマスのもっとも有名な詩の一節で、この詩を刻んだ記念碑が、イギリスには方々あるそうだ。
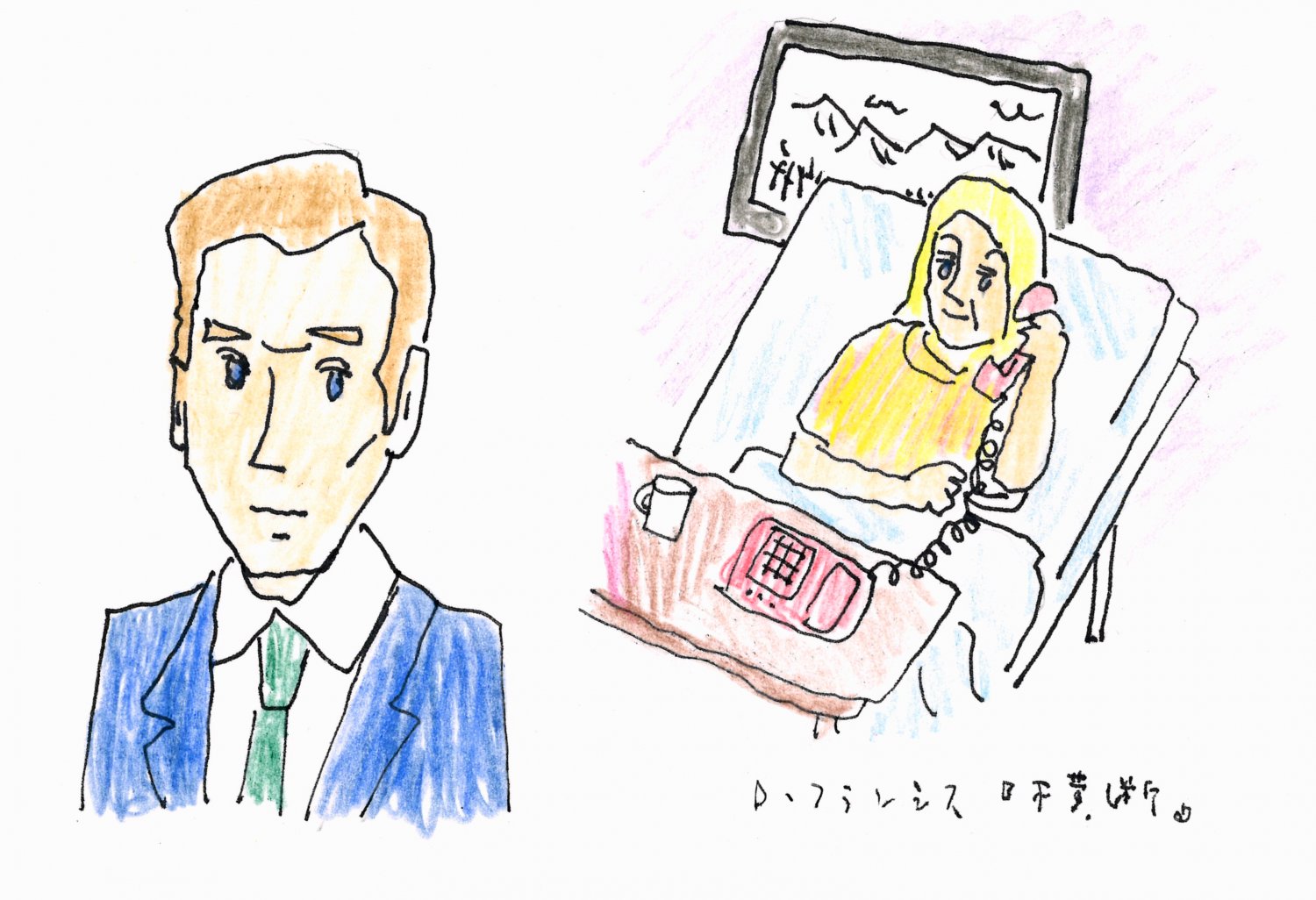
やればできるじゃないか「むさしの号」
松本清張のミステリー小説には、しばしば時刻表を使ったトリックが登場する。『点と線』における、東京駅13番線から15番線を見通せる「4分間の空白」は有名。妻にも言われるが、私は40代になるまでは時刻表の読み方も知らなかった。「青春18きっぷ」を使ってあちこち出かけるようになって習熟していったし、その面白さも知ったのである。
現在は「ナビタイム」というサイトの「乗換案内」を駆使して、出発駅から到着駅までのルートを下調べする。「条件」次第で、さまざまなルートの候補がただちに表示され、まことに便利で重宝している。その場合、東京西郊の私が利用する最寄り駅から、北関東、東北方面へ向かう際、最初に提示されるのが「大宮」駅乗り換えである。これは「東京」駅経由より乗り換え本数が2本多くなる。細かく言うと、「西国分寺」駅で武蔵野線、「武蔵浦和」駅で埼京線に乗り換え、「大宮」駅で北上する列車(「新幹線」を含む)を捕まえる、という段取りになる。面倒だが、この方が「東京」駅経由より少し早くなる。
「西国分寺」駅の中央線から武蔵野線への乗り換えは直結していて1分ぐらいしかかからない。これはまだいい。面倒なのが埼京線への乗り換えで、ホームの両端に乗り換え口があり、大変混雑するし、また移動距離が長い。埼京線ホームで電車を待って、「大宮」に着く頃にはもう疲れていたりする。
ところが、朝夕の数本だけ「むさしの号」という特別列車の運行があり、これに乗れば「西国分寺」駅での1回、あるいは最寄り駅からノンストップで「大宮」駅まで運んでくれる。すこぶるラクチンな便なのだ。私がこの存在に気づくのにしばらくかかった。ある時、先述の「乗換案内」ナビで(これは利用するホームや乗る便の名称まで明示される)、「むさしの号」を使えば楽であることを知った。便が少ないのが難点だが、大げさに言えば夢のようなショートカット列車である。
松本清張の小説ならと、こんなシーンを想像してみた。追う容疑者のアリバイが、このルートによるものだ。そこで新米と老齢刑事の会話。
「いや、それは無理ですよ。容疑者は大宮から八王子へ行くのに、最低2回は乗り換えねばなりません。所要時間は○○。殺人の現場と時間にまにあいっこないです」
「そうか、山形出身なら仕方ないか。君、知らないのかね。『むさしの号』ってのがあるんだよ。朝と夕方から夜の数本、途中、乗り換えなしで大宮から八王子へ行ける。普通車で乗り換えるより20分は早くなる」
「ええ、だって武蔵野線と中央線は乗り入れてませんよ。無理じゃないですか」
「ところがだね、鉄道路線図には記載されていない「支線」というのがあってだな……」
と、まあこんな調子。
私も今回、調べて初めて知ったのだが、これは大宮駅発着の新幹線へのアクセスを想定して設定された路線である。中央線と武蔵野線は、ふだんは走らない「支線」を使って相互乗り入れをする。たしかに地図帳を見ると、「西国分寺」駅の西側、西恋ヶ窪2丁目から3丁目にかけて、中央線と武蔵野線を結んで放物線のカーブが破線で示されている。これが「支線」であった。
武蔵浦和で埼京線、南浦和で京浜東北線に乗り換える場合は「大宮支線」と「東北貨物線」を使って電車は通過していく。つまり、2か所、通常のルートでは使われない線路を利用してのリレー運行なのである。電車に乗っている間は気づかない。最初に利用した時は、「あれ、おかしいな。いつのまに中央線に乗り入れたんだろう?」と不思議に思っていた。
すばらしい。やればできるじゃないか。いまや他社の鉄道がどんどん乗り入れて、客の利便を図る方向にあるなか、JRは1社で、なぜ、もっと「むさしの号」を増やして利便を図らないのかと考えるのは一般人の浅はかさで、いろいろ事情があるのだろう。
近頃は私、帰りの際には「大宮」駅で30~40分待ってでも「むさしの号」を利用する。夕方ラッシュ時の混雑を避け、しかも始発だから席を確保できる。「ありがたや、ありがたや」と、思わずシートをなでてしまうのである。
武蔵浦和で埼京線、南浦和で京浜東北線に乗り換える場合は「大宮支線」と「東北貨物線」を使って電車は通過していく。つまり、2か所、通常のルートでは使われない線路を利用してのリレー運行なのである。電車に乗っている間は気づかない。最初に利用した時は、「あれ、おかしいな。いつのまに中央線に乗り入れたんだろう?」と不思議に思っていた。
すばらしい。やればできるじゃないか。いまや他社の鉄道がどんどん乗り入れて、客の利便を図る方向にあるなか、JRは1社で、なぜ、もっと「むさしの号」を増やして利便を図らないのかと考えるのは一般人の浅はかさで、いろいろ事情があるのだろう。
近頃は私、帰りの際には「大宮」駅で30~40分待ってでも「むさしの号」を利用する。夕方ラッシュ時の混雑を避け、しかも始発だから席を確保できる。「ありがたや、ありがたや」と、思わずシートをなでてしまうのである。

《『Web新小説』開催イベントのお知らせ》
岡崎武志さんと行く 春爛漫の早稲田界隈~漱石&春樹散歩
※新型コロナウイルス感染拡大の影響から、4月11日開催予定のイベントの開催を延期しておりましたが、感染拡大に収束が見られない昨今の状況に鑑み、やむなく中止とさせていただきました。
チケットをご購入いただきましたお客様、開催を楽しみにお待ちくださいましたお客様には深くお詫び申し上げます。
詳細はこちらをご覧ください。
岡崎武志さんと行く 春爛漫の早稲田界隈~漱石&春樹散歩
※新型コロナウイルス感染拡大の影響から、4月11日開催予定のイベントの開催を延期しておりましたが、感染拡大に収束が見られない昨今の状況に鑑み、やむなく中止とさせていただきました。
チケットをご購入いただきましたお客様、開催を楽しみにお待ちくださいましたお客様には深くお詫び申し上げます。
詳細はこちらをご覧ください。
『明日咲く言葉の種をまこう──心を耕す名言100』(春陽堂書店)岡崎武志・著
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
小説、エッセイ、詩、漫画、映画、ドラマ、墓碑銘に至るまで、自らが書き留めた、とっておきの名言、名ゼリフを選りすぐって読者にお届け。「名言」の背景やエピソードから著者の経験も垣間見え、オカタケエッセイとしても、読書や芸術鑑賞の案内としても楽しめる1冊。
┃この記事を書いた人
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。
岡崎 武志(おかざき・たけし)
1957年、大阪生まれ。書評家・古本ライター。立命館大学卒業後、高校の国語講師を経て上京。出版社勤務の後、フリーライターとなる。書評を中心に各紙誌に執筆。「文庫王」「均一小僧」「神保町系ライター」などの異名でも知られ著書多数。